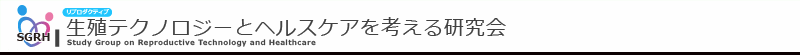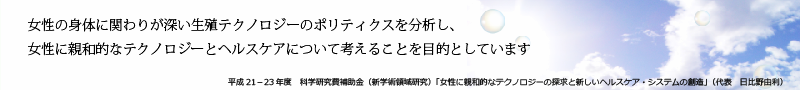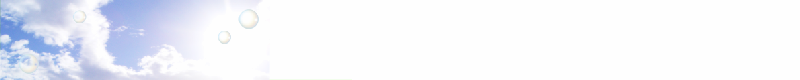安藤泰至(鳥取大学医学部准教授)
「生命操作システムにおける『見えざるもの』-生殖技術を中心に-」

安藤: 安藤です、こんにちは。
私が金沢に寄せていただくのは今日で四度目です。とても好きな町で、これまで三回、観光で参りました。今回仕事で来られることになり、とても喜んでおります。生殖医療をめぐる講演会やシンポジウムで、今日のように宗教学者が二人呼ばれ、しかも二人とも男性というのは非常に珍しいと思います。
これまで公の場で語ったことはないのですが、生殖医療については、私は研究者としてこの問題を研究しているというだけでなく、実は「当事者」でもあります。私と妻の間には子どもはいません。いわゆる不妊カップルです。それで、もう15年以上前になりますが、体外受精を二回やりました。私は、今は医学部に勤めていますが、当時は前の職場にいて、生命倫理や医療倫理にはまったくノータッチだったころで、生殖医療については何の知識もありませんでした。
幸か不幸か、二回とも失敗しました。その時点で私と妻は、またこういう技術を使って子どもを作るかどうかについて話し合い、結果「やめる」という選択をしました。妻は、絶対に体外受精ではないと子どもができないというわけではなかったのですが、自然妊娠する可能性は非常に低い。ということで、自然にまかせて子どもができればもちろんそれでいいし、できなかったら諦めようということになりました。妻はもう一回やってみたいという感じが少しあったのですが、私のほうが「やめよう」と、かなり強く言いました。
その大きな理由を、この場でお話しするのは少々気恥ずかしいことですが、女性にとって生殖技術は、精神的にも肉体的にもかなり暴力的なところがあります。男性と女性では、子どもを産むまでの過程において担っている役割の多さが違います。男性は精子を出すだけですが、女性は卵子を排出する、体内で受精してそれが着床、妊娠する、10カ月胎児おなかの中で宿すなど、多くの役割を果たしています。私はその時の経験で、生殖技術は女性に対して非常に酷な技術だと思いました。たとえば、卵子を採るときは全身麻酔をかけますので、妻が採卵を終えて帰ってくると、ヘロヘロになっているわけです。あるいは、受精卵(胚)を子宮の中に戻すと、48時間動いてはいけない。そのときの彼女の精神的に不安定な状態も見ていて、自分の愛する大切な女性にこのようなことをされるのは何か「許せない」という気になり、私は、かなり強く「やめよう」と言いました。結果、今は二人で幸せに暮らしていますが、そういう意味で、私には不妊の問題や生殖医療について「当事者」という面があります。
それでは、お配りしたプリントを基にお話ししていきます。二枚綴じられている字だけのレジュメと、右側に新聞記事があって、左側に数字がたくさん並んでいるもの、そして図が描いてあるもの、合わせて三種類あると思います。
今日のお話の題を「生命操作システムにおける『見えざるもの』―生殖技術を中心に―」としました。「生命操作」という言葉は否定的な、どちらかというとよくないニュアンスで語られることが多いですが、その言葉で何を指しているのかは、少し曖昧なところもあります。たとえばこれを英語で表現しようとしたらどうなるのか。「生命操作」をそのまま直訳すると「manipulation of life」となりますが、おそらく、ただ「life(生命)」と言っただけではだめで、たとえば、「human life(人間の生)」というように、「人間の」という語をつけないと、たぶん分からないでしょう。また、何を使ってそれを操作するのかということ、たとえば「医療技術による(through medical technology)」とか「バイオテクノロジーによる(through biotechnology)」といった言葉をつけ加えないと、正確に表現できないのではないかと思います。
島薗先生がおっしゃったように、この技術は、たしかに私たちが生きる上での選択肢を広げていくということがあります。当然、それをどうしても使いたい人がいる。使いたい人がいて、使える技術があって、ほかの人に迷惑をかけなければいいのだから、一体何が悪いのか、というのが賛成派・肯定派の人たちの意見で、ある意味では単純です。しかし、生殖技術に限りませんが、新しい技術を「使っている」つもりでいて、実はわれわれが技術に「使われて」しまう、あるいは踊らされてしまう。そのことによって、人間にとって大切なものを失っていくという側面があります。
もちろん、新しい技術というのは、最初に登場したときには何かしら「気持ち悪さ」のようなものがつきまとうことが多いものです。たとえば最初に写真の技術がやってきたときには、写真に写ると魂が抜けていくとか言って、それを怖がったり、嫌ったりした人が大勢いました。しかし今では、私たちは何も考えずに日常的に使っています。また、交通手段の発達や、パソコンなどのコンピューターの発達は、私たちからいろいろな時間を奪い、私たちの生活自体を何か悪い方向に変えている面もありますが、やはり便利だから、そういうことはあまり気にせずにどんどん使っているということがあります。
生殖技術をはじめとする生命操作も、その種の問題なのでしょうか。つまり、技術の進歩によってだんだん慣れていくと、今の私たちが「生命操作」と聞いて感じるような「気持ち悪さ」が薄れていくのでしょうか。あるいは、悪い面もあるが、やはり良い面が多く、それが私たちの生活をもっと豊かにしていくものだと言えるのでしょうか。そこを、少し立ち止まって考える必要があるのではないかと思います。島薗先生の話とは逆に、非常にラフな話になりますが、私たちのある意味素朴な実感のようなものから発するこのような論点を、きちんと言葉にして議論のなかに組み込んでいくことが大切です。
さて、私が生殖技術について最初にびっくりしたのは、1978年に、世界初の体外受精児がイギリスで誕生したときのことです。ルイーズ・ブラウンという女の子で、その後看護師になり、今は結婚して子どもが産まれているはずです。このとき私は高校3年生で、今でもよく覚えているのですが、新聞の第一面に大きく「世界初、試験管ベビー誕生!」と報じられました。今だったら、おそらくクローン人間が誕生したとでもいうような感じだと思いますが、非常にセンセーショナルでした。私は最初、試験管ベビーというのは、試験管の中で赤ん坊が培養されて、そこからパッと出てくるのかと想像しまして(笑)、すごいことができるようになったものだと驚きましたが、内容をよく読むと、試験管の中で精子と卵子を混ぜ合わせて受精卵を作って、それを産む人の子宮の中に入れて、赤ちゃんは普通にお母さんのおなかの中から出てくることを知って、少しガッカリしたような記憶があります。
この「試験管ベビー」という言葉は、もうほとんど死語になっていますね。今は日本でも、年間1万人以上、60人に1人ぐらいは体外受精で産まれた赤ちゃんです。なのでこのような技術は、もはや実験段階の技術ではなく、すでに通常医療の中に入っているとみなす人もいるわけです。
さきほど島薗先生は代理出産の話をされました。滑りやすい坂(slippery slope)の話ではないですが、いったんあるものが認められると、その次、その次と行って、前のものは当たり前となる風潮、これは生殖技術や臓器移植についてもかなりあると思います。もう少し立ち止まって考える必要があると思います。つまり、生殖技術を本当にわれわれは主体的に「使えて」いるのか、あるいはそれを利用したいと思っている人は、いろいろな選択肢が与えられた中で本当に「選べて」いるのか、そこのところが非常に疑問に思います。
世界初の体外受精児が産まれた1978年、これは後で知ったことですが、礼賛派の人たちは「不妊の女性に福音がもたらされた」と言い、反対派の人たちは「神の領域を人間が侵犯している。入ってはいけないところに人間が入りだした。怖ろしいことだ」という反対の仕方をしました。こういう際に「福音」や「神様」といった宗教的な言葉が使われるのは、子どもを産み育てることが、やはり人間にとって、単に便利になればよいというようなものではなく、非常に根源的な価値や意味などに関わっているからだと思います。
生殖医療だけではないのですが、いわゆる「先端医療」と呼ばれるいろいろな生命操作技術を論じるときに、アメリカをはじめとする英語圏の生命倫理でよく使われるメタファーに「神を演じる Playing God」という言葉があります。これは、実は正反対の二つの意味で使われています。一方では、先ほどの例のように生命操作に反対する側の人たちが、人間は神の領域に踏み込んではならない。人間の勝手な都合でもってそこに踏み込んではいけない、という意味で使います。逆に、日本ではあまり聞いたことはないのですが、礼賛派の人たちのなかには、「人間というのは、どんどん自分の殻を破って神に近づかなくてはいけない。最終的には神にならないといけない」と主張するキリスト教の神学者が結構います。彼らは「神を演じる」という言葉を「人間は神を演じてはならない」という意味とは反対に、「人間は神を演じるべきだ、神になるべきだ」という意味で使うのです。
キリスト教では人間は被造物(creature)、神によって創造されたものですが、こうした神学者は、人間はただの被造物ではなくて、神と共同の創造者(co-creator)として、世界を共同で創造しているのだとか、あるいは、人間というのは今あるような人間存在すなわち「human being」ではなくて「human becoming」である、つまり今の人間を超えていく「超人」のような存在になっていかないといけないということを、あからさまに言っています。このような宗教的な語彙が持ち出されるのは、やはり生命操作に関する畏怖とある種の魅惑の両方が混ざっているからだと思います。
私の話としては(タイトルにありますように)「生命操作」という全体的な視点を保ちながら、まずは生殖技術を中心にお話し、島薗先生のお話にも出た、脳死臓器移植との比較を少ししたいと思います。まず「生殖技術」とは何を指すのか、についてはプリントの最初のところをご覧ください。一応、「生物医学的な知識に基づいて開発、応用されたヒトの生殖に関わる技術」を「広い意味の生殖技術」として定義し、それを「Ⅰ、産まないための技術」、「Ⅱ、産むための技術」、「Ⅲ、胎児や受精卵を操作、選別するための技術」という三つに分けました。狭い意味で生殖技術や生殖補助技術と言うと、このなかのⅡを指すのが普通だと思います。ただこの三つのタイプの技術は、いろいろな意味でお互いが非常に深く関係し合っていますので、一つ一つを見るだけではなくて、総合的に見ていく必要があります。
たとえば、「出生前診断」というものについてお聞きになったことがあると思います。出生前診断は「診断」ですから、おなかの中にいる胎児について、いろいろなことを調べるわけです。診断というのは、普通は「治療のため」にあるものです。もちろん治療ができない場合もありますが、障害のように治療ができないものについては、障害を持ってどう生きていくかをサポートするために、診断があるのです。そういうことからすると、出生前診断それ自体は別に「選別のための技術」ではないとも言えます。
ところが、日本でも海外でもそうですが、出生前診断でダウン症のように、トリソミーといって染色体の一組が本来は2本ずつしかないところが3本ある障害をもった子どもが生まれる確率が非常に高いとわかったときに、9割ぐらいの人が中絶する、ということがあります。今の日本の法律では「胎児に障害がある」という理由では中絶できませんので本当は違法なのですが、実際には行われています。つまり出生前診断そのものは中絶のためにするわけではないのですが、それがIの人工妊娠中絶と結びつくことによって、ある種のいのちの選別に利用されるかたちになるわけです。
また、体外受精というのがなぜそれほどセンセーショナルになったかというと、それで不妊の人がたくさん救われるというだけではなくて、それまでになかった新しい倫理的問題を生み出すからです。本来、女性の卵子も受精卵も、自然な状態では女性の身体の外にはないものです。ところがそれが身体の外にあるということが可能になると、結局それは、いったいどのような存在なのかという問題が出てきます。特に、それが冷凍保存できるようになりますと、受精卵は物なのか人なのかという問題が切実なものになってきます。古くから、人工妊娠中絶をめぐる議論の中で、胎児にはわれわれと同じ人権や生命権はあるのかないのかが問題になっていたのですが、それが新しいかたちで再燃することになったとも言えます。受精卵が女性の身体の外にあることで、もしそれが物であるなら、それはいったい「誰のもの」なのかという問題も出てきますし、その受精卵をES細胞研究など、難病の人を助けるための治療法を開発する医学研究などに用いることもできます。こういったいろいろな新しい技術につながっていく意味で、体外受精は非常に重要な問題であると、当時から意識されてきたことがあります。
このように、先に分類したI、Ⅱ、Ⅲの生殖技術は、それぞれ非常に密接につながっています。「こういう問題で困っている人には、これこれの技術が利用できる、役に立つ」ということだけを考えるのではなくて、やはり技術全体のシステムを、何がそれらを推進する力になっているのかを考えないといけません。私が「生命操作システム」と名付けたのは、個々の技術を見るだけではなく、全体を見る必要があるということを強調したいからです。また、生殖技術は人のいのちの始まりをめぐる生命操作ですが、人のいのちの終わりに関しても、実は同じようなことが起こっていて、両方を合わせて「生命操作システム」の全体像を見ることも必要です。今日、脳死臓器移植の話を少ししたいと思ったのはそのためです。
いのちの始まりと終わりというと、よく話題になりますが、日本では自宅で死ぬ人と自宅で生まれる人がどんどん減ってきたのはご存じのとおりです。「人口動態統計」で調べますと、1950年ぐらいから自宅で死ぬ人が徐々に減ってきて、病院で死ぬ人が徐々に増えてきています。最近は、病院より自宅で死にたいという人も少し増えてきて、在宅ホスピスなどのサービスがある所ではある程度そういう要望をかなえることも可能なので、今後は少しずつ変わってくるとは思いますが、1950年には自宅での死亡率が82%以上だったのが、現在では12~13%ですから、自宅死と病院死の割合は完全に逆転しています。
死に場所の変化と比べてみると、出産の場所に関しては、実はこの変化が非常に急で、1950年から1970年までの20年で圧倒的にガラッと変わっています。1950年には95%以上の人が自宅で生まれていたのに、現在はわずか0.1~0.2%です。私は1961年生まれで、自宅で生まれたのですが、このことを今の学生に言うと、「自宅で生まれたような人が、まだ生きているのか」と、化石人類でも見るような目で見られます(笑)。でも統計を見ると、1960年で自宅出産の率(全国平均)が49.9%ですから、このころはちょうど半々ですね。
こうして誕生と死という人生のメインイベントの場が、ほとんど病院に移ることによって、それまで医療あるいは医学の対象として見られていなかったものがその対象として見られるようになってくる、いろいろな事柄に対する視線が変わってくるということがあります。こういった現象について、ここでは「生と死の医療化」あるいは「誕生と死の医療化」という、少しラフな言葉を使ってみることにします。
不妊の人、子どもがほしくてもできない人は昔からいます。古くは、『旧約聖書』に出てくるアブラハムの奥さんのサラがたぶんそうですし、江戸時代にも「嫁して3年子無きは去れ」といった非常に差別的な決まり文句があるように、(本当は男性に原因があるかもしれないのですが)子どもを産めない女は実家に帰されるようなことがありました。ところが、「不妊症」という言葉はそのころはなかったのです。あるいはそれを「治療」しようということもなかった。それでは「不妊症」「不妊治療」という言葉は、いったいいつ発生したのでしょうか。
私は大学で、看護学生の卒業研究を受け持っていますが、一昨年、私のところで卒業研究をやった三人の女子学生が、不妊治療をテーマに研究し、熱心に勉強して、いろいろ調べてきました。たとえば、体外受精などで有名なクリニックを経営されていた70代半ばぐらいの医師が、引退後に大阪ロータリークラブで講演されたときの講演録があるのですが、その医師は、自分が医学生や研修医だったころには、「不妊症」などという言葉を聞いたことがなかった、と発言しています。時代的にいつごろかというと、1960年代初めぐらいのことです。つまり、自宅で人が生まれていた割合がまだ半分ぐらいあった時代には、不妊の人たちに「不妊症」という言葉は使われていなかったということです。病院出産が当たり前になり、出産や誕生が「医療化」されることによって、不妊が病気として「不妊症」と名付けられ、それを「治療」しようという動きが生じた、すなわち「不妊の医療化」が起こってきたことになります。
先ほど申しましたように1978年に世界初の体外受精児が生まれたのですが、これも非常にラフな話をしますと、このあたりから新しい医療あるいは生命科学の技術が、実際の医療現場で「先端医療」として脚光を浴びるようになってきて、それまでとは非常に質の違った生命操作技術が発展してきた、という印象があります。放っておいたら死ぬような病気の人を治療して治すのももちろん広い意味では生命操作であるには違いありませんが、1980年前後ぐらいから、そこにある種全く質の違ったものが入り込んできた印象を持っています。もちろんこれは質の差ではなくて量の差であると言う人もいますが、やはり技術というのはスーッとなだらかに進んでいくのではなくて、ある段階で飛躍的に進むところがあります。だから、還元すれば量の差なのだけれども、技術のある種の切れ味みたいなものがストンと増してきたときに、あたかもそれが「質の差」であるかのように見える瞬間があります。それが、私は1980年前後に起こっていると思っています。
それを象徴するのが1978年という年です。大学の講義などでもよく話すのですが、この年は世界初の体外受精児が生まれただけでなく、「奇跡の薬」といわれた免疫抑制剤、シクロスポリンが開発された年でもあります。臓器移植についてはある程度ご存じだと思いますが、1967年に南アフリカでクリスチャン・バーナードという医師が最初に心臓移植をやりまして、その後1960年代の後半に、日本の悪名高き「和田移植」をはじめとして心臓移植ブームが起こりました。ところが、ブームはすぐにすたれてしまいました。移植を受けた患者の拒絶反応が非常に強いために長くは生きられず、移植を受けないほうがかえって長生きしていたりして、手術自体は成功してもあまり効果がないということで、拒絶反応を抑える薬がきちんとできるまでは進まなかったのです。それがシクロスポリンの登場で一つ大きな壁が破られて、欧米では1980年代から臓器移植が本格的に浸透していきます。
また、この1978年は、IVHが医療現場に導入された年でもあります。ご存じだと思いますが、IVHというのは中心静脈に直接栄養を入れる技術です。人間であれ他の動物であれ、口から食べ物を食べられなくなったら、死は遠くありません。それまでは口から食べられなくなった人は点滴ぐらいしかなく、点滴では延命にも限界があります。そこでこのIVHとか、少し後には胃ろうとか、現代的な延命治療の最たるものが開発されていきました。このように時期的にだいたい同じころ(1980年前後)に、人の生まれるところと、人の死ぬところで、今はほとんど通常医療になっているような技術が、医療現場に導入されたわけです。
ここからは「不妊治療」として進められてきた生殖補助技術で、先ほどの生殖技術の分類でいうとⅡに当たるものについて少し詳しくお話しします。図と表がセットになっているプリントをご覧ください。図1、図2、表1、表2、表3です。
先ほど体外受精は、今や60人に1人ぐらいがそれを使って生まれる、非常にありふれた技術になっているという話をしましたが、実態はどのようなものなのでしょうか。私がかつて当事者として体外受精の説明を受けたとき、そのクリニックの医師から、成功率はだいたい30%だと言われました。30%という確率についてどう思うかはそれこそ人それぞれでしょうが、たとえば野球で3割打者というのはかなりの強打者です。チャンスに打席に立てばヒットを打ってくれそうな気がしますね。それで私は、そのとき30%と聞いて「結構高いな」と思ったわけですが、この数字は、ある意味でまやかしなのです。
成功率を出すときの出し方ですが(表1)、日本産科婦人科学会などが体外受精の成功率と言っているのは、実は一番上の計算式で、胚移植件数に対する妊娠件数の割合です。普通の体外受精の場合は、受精卵が4個から8個ぐらいに分割された段階(胚)で女性の子宮に戻しますから、それを何回戻したか(何個戻したかではありません)、それに対して、何回妊娠が起こったかということを成功率として出しているわけです。それに対して、普通の人が「成功率」と言って思い浮かぶものは何かというと、三つあるうちの一番下の計算式のものですよね。たとえば、自然では妊娠しにくい、あるいは妊娠できないということで体外受精の適応になり、それをやってみることに同意して体外受精の準備をしはじめた件数に対して、実際に元気な赤ちゃんが生まれてくる割合です。
産科婦人科学会が出している成功率と患者の立場での成功率で、その分母を比べると、胚の移植まではいかない人、たとえば卵子がうまく採れないとか、採れても卵子の質が悪かったり、受精しなかったり、受精卵も体外受精に使えるようないいものがなかったりする人もたくさんいます。つまり、分母は学会の計算式の方が小さいです。逆に分子の方を比べると、体外受精で妊娠はしたが途中で流産する人もたくさんいますから、分子は学会の計算式の方が大きくなります。つまり、本当は学会や医師が成功率として公表しているものよりも分母が大きくて分子が小さいわけですから、当然、実際の成功率はずっと低くなります。
実際に、2006年の体外受精の治療成績を見てみましょう。表2は卒業研究で私のところの学生が作ったものですが、産科婦人科学会の学会誌から数字を抜き出して、自分たちで計算したものです(産科婦人科学会で学会誌に出している数字は件数だけで、学会がこのような表を出しているわけではありません)これを見ると、医師が説明しているような胚移植件数に対する妊娠件数の割合(表でAと書いてあるところ)は28.9%です。これはあくまで全国平均ですから、実際には病院やクリニックによってそれより高い所も低い所もあるでしょう。それに対して、実際に患者の立場から見た成功率(表でBと書いてあるところ)は12.0%です。
そうすると、私がかつて聞いた30%という数字は何なのか、これはAの数字です。おそらく、技術力は病院によって差がありますから、病院によっては30%、40%の所は当然あると思います。だから嘘を言っているわけではないとも言えますが、われわれが実際に体外受精を始めてみようと思ったときに、実際に元気な赤ちゃんが産まれてくる確率は10%ちょっと、いくら技術力の高い病院でも20%行くか行かないかぐらいだと思います。さっきの野球の例でいいますと、打率1割2分の打者というのは、代打でも使ってもらえそうにない感じがします。本当にこれだけ差があるんです。
実は卒研の学生がこの表を作ったのは、ちょうどこの10年前の1996年に『生命操作事典』という本の中で、長沖さんという方がその下の表(表3)を作られていたので、学会誌の新しいデータを入れて同じ計算をしてみたというわけです。1996年と2006年の治療成績を比べてみると、ほとんど成功率は変わっていないことがわかります。10年間で体外受精の技術はそんなに進歩していないということです。非常に変わっているのは実施数で、体外受精だけで倍ぐらい増えています。凍結胚の使用は十何倍に増えて、桁が違っています。「顕微授精」というのは、男性の精子の側に非常に運動量が足りないなどの問題がある場合に、体外受精で女性の卵子にピンポイントで精子を当てる方法でして、これが飛躍的に増えていますが、全体の成功率はこの10年間大して変わっていません。
日本で体外受精児が初めて生まれたのは東北大学で1983年のことです。びっくりするのは、その1983年から1986年までの体外受精の治療成績が、産科婦人科学会の翌年の大会の講演記録として載っているのですが、これを見ると、医師の立場からの成功率、すなわち胚移植に対する妊娠率ですら9.7%、患者の立場で見た場合の実際の成功率はたった2.4%です。これを、産科婦人科学会は「成功率10%」と発表したわけです。つまり、本当は2~3%、30人に1人成功するかしないか、というレベルです。「人体実験」という言葉の使い方は人によっていろいろ違いますが、これはどう考えても「実験」です。とてもまともな通常医療のレベルとは言えません。
1986年という年は、初めて東北大学で体外受精を成功させた鈴木雅洲医師が、体外受精の専門病院、スズキ病院を東北で開設した年です。技術力がこの程度のレベルで、その専門病院ができている。いかにこの技術が、技術を利用する人たちの立場ではなくて、技術を推進して、実施例をたくさん増やして実験で精度を高めていく、推進していく側の人たちの理屈で進められているかということが、非常によく分かる例だと思います。
さて、先に「不妊の医療化」という言葉を使いましたが、不妊とはそもそも病気なのかどうか。これについては、私は何か回答を与えようとは思いません。「病気だ」と言う人がいてもいいと思うし、「病気ではないから、不妊でも全然困らない、治療する気はない」という人がいても別にいいと思います。ただ、図1を見ていただくとおわかりのように、「不妊治療」という言葉を無反省に使うことは、大いに問題があると思います。先ほど島薗先生のお話の中に、代理出産について、それが「正当な医療」なのかどうかという言葉があったと思いますが、最初からそれを「不妊治療」というふうに言ってしまうと、「これは治療なんだから正当なんだ」と、ある意味同語反復になってしまいます。
そもそも人工授精とか、体外受精とか、卵子・精子を第三者から借りてくるとか、代理出産とかというのは、「治療」という枠に入るんだろうか、ということを問い直してみる必要があるように思います。もちろん私は、そういったものは「治療」には入らないから、絶対にやってはいけないという気はないんです。ただ、「不妊治療」という言葉を無反省に、そういったものにまで延長して使うことによって、抜け落ちてしまう問題があるということを強調したいと思います。
二つある図の左側に「本来の不妊治療」というふうに書いてあるのは、たとえばホルモン療法みたいに、不妊の原因になっているものを、何か薬とかそういうもので治すような治療法を指しています。あるいは、今はちょっと技術的に無理ですけども、たとえば卵管が細くて詰まっているために妊娠できない人に対して、卵管を拡げるための外科手術ができるとすれば、そういうものも含まれます。つまり、不妊の原因になっている部分を治療することで妊娠・出産ができるということであれば、それはおそらく「治療」という範疇に入ると思うんです。
ところが、今問題にしているような、人工授精や体外受精、あるいは第三者の卵子・精子の利用とか、代理出産といったものは、結局不妊の原因になっているものを治療しているんじゃなくて、それによって生じている障害を別の人工的なものでもって代替しているわけです。だから、本来それは「治療」という概念の延長線上に使えるのかどうかも、ちょっとやっぱり疑問があります。もちろん、その病気の根本を治すのではなくて、その障害を代替するようなものは全部「治療ではない」と言う気は、私には毛頭ありません。そんなことを言ったら、たとえば人工骨とかペースメーカーを入れたりとか、人工透析とかは全部治療じゃないということになってしまいますが、そう言う気はまったくないんです。
ただ、この生殖補助技術の非常に特徴的なところというのは、その技術の本性として、不妊の人以外にもいろんな利用可能性があるということですね。それから人の生殖、出産ということにかかわっているために、非常に社会的なインパクトが大きいということ。さっきの島薗先生のお話の中にも出てきましたが、私たちのアイデンティティだとか、親子関係だとか、そういうことに重大な影響を及ぼすという、そういう面があります。
そうすると、本来は下の図に書いたように、こうした生殖(補助)技術全体を見渡しながら、私たちは、不妊の人々に対してはどういう技術をどういうときに、どういう条件を満たせば使っていいのか、あるいはいけないのかということを、一つ一つ細かく論じていく。そして、不妊以外の目的でそれを使うことは、どういう場合だったら許されるのか、あるいは許されないのか、ということを論じていかなければならないはずです。
たとえば、先ほど分類した生殖技術のⅢ、すなわち胎児や受精卵を「選別」する技術の一つとして、着床前診断というものがあります。着床前診断というのは、受精卵の遺伝子診断です。体外受精をやって、ある特定の病気の遺伝子をもっている受精卵を捨ててしまって、ないものだけを選んで子宮の中に入れます。要するに、ある特定の病気の子どもを産まないために、たとえば、親とか親の兄弟(姉妹)とかにその遺伝子を持っている人や、実際に病気を発症しているような人がいた場合に、同じ病気の子を産まないために使う、体外受精にはそういう利用の仕方もあるのです。また、アメリカなんかは生殖医療の商業化が非常に進んでいますから、別に不妊でもないのに、独身の女性がたとえば精子バンクなんかで精子を買ってきて、自分の好みの精子を人工授精して子どもを産めます(精子ドナーの髪の毛の色から、体格から、学歴から、宗教から、全部選べるんです)。結婚して男性と一緒に暮らす気はないが、自分の子どもは産んで育てたいという女性もこの技術を利用できるわけです。
本来は、そういうことはどこまで許されるのかということを含めて全体的に議論をしなければいけないんだけれど、そこに「治療」という言葉が使われることによって、なし崩し的にそれはいいものなんだと、その治療を求めている人々がいて、さっき「善意」という話が出ましたけど、その人たちを助けてあげる、サポートするのは当然なんだというふうにもって行かれちゃうということです。
ちょっと話が長くなってきたので、次に行きます。不妊(症)で悩み、苦しんでいる人に対して「不妊治療」が必要だと言われるのですが、実際に、不妊の人たちが「何に」悩んでいるんだろうかということを考えてみると、けっして単純ではないことがわかります。たしかに、表面だけ見ると、ほしいのに子どもができないということで悩んでいるんだ、とは言えるのですが、子どもができないことによって、その人は「何に」苦しんでいるんだろうかということを考えた場合に、そこにはいろんな問題があり得るわけです。
たとえば、子どもができないことで、自分のアイデンティティが揺らぐとか、あるいは近所の同年代の女性とか、夫婦とかと話が通じないとか。あるいは、何も事情を知らない他人から「何で子どもをつくらないの?」などと、非常に無神経に聞かれて傷つくとか。そういういろんな要因がそこにはあるわけですよ。
(幸い私と妻の場合は、いろんな好条件に恵まれていたおかげで、それほど深い悩みや苦しみには至らなかったように思いますが)そうした人たちの悩みとか苦しみというのがいかに深刻なものかということは、不妊の人たちのブログや掲示板、メーリングリストなどを見ていると、非常によく分かります。ただ、それがどういう仕方で解決されるのかというのは、いろんなパターンがあり得るということです。つまり、生殖補助技術を使って自分の子どもを持つ以外にも、養子をもらって育てるという選択肢もあるだろうし(現在の日本ではかなりハードルが高いのですが)、自分が若い次の世代の人を育てていくということだったら、別に対象が自分の子どもでなくてもいいわけで、たとえば、地域の子どもたちのサッカーチームの指導をするということでもいいわけでしょう。もちろん、子どもをあきらめて夫婦二人の生活を満喫することも、はじめから一つの選択肢としてあるわけです。
だから不妊の悩みを解決するためにはいろんな方法があり、いろんな選択肢があって、そのいろんな人たちをサポートする手段もあるにもかかわらず、それが一義的に、子どもを持てないんだから、子どもを持てるようにするのが一番いいんだ、そうしたら医学でこういう技術があるから、それを使うことがいいんだというふうに、予め敷かれたレールにスッと乗せてしまうような働きを、この「治療」という言葉がしているんじゃないか。そこをやっぱりちょっと問い直したほうがいいんじゃないかと思います。
臓器移植についても非常に同じようなことが言えるんですが、さっき「システム」ということを言ったのは、この不妊治療の成功率、体外受精の成功率とかを考えてみても、成功者というのは本当にごくわずかだということです。ほとんどの人は失敗する、そういう構造になっているにもかかわらず、「成功の夢」だけがいささか誇大に宣伝されています。体外受精で失敗し続けている人の場合、もう20年以上やっている人もいます。もう女の人は、身体がボロボロ。排卵誘発剤などの害も非常に大きいですし、体力的にも精神的にもボロボロ、そうなっても、もうあきらめざるを得ないという最終通牒を突きつけられるまでがんばってしまう。
変なたとえなんですけど、これはギャンブルに似ています。ギャンブルっていうのは、掛け金が多くなればなるほど、負け込めば込むほどその負けを取り返そうとしてたくさんつぎ込んでしまうものです。「次こそは」と思うんですね。私も競馬をちょっとするんですが、負ければ負けるほどたくさんつぎ込まないと回収できない仕組みになっています(笑)。ギャンブルで大負けしないためのコツは、運の悪いときにはいったん「降りて」、いい風が吹いてくるまで待つことなんですがね。そういう意味で、変な言い方ですが、不妊治療から「降りられない人」がいるんです。ここまで頑張って、これだけお金も時間もつぎ込んで、精神的にもこれだけ集中して頑張ってきたのに、ここでやめたら今までの苦労はいったいどうなるんだというわけで、もうやめられない、非常に深刻な事態が発生します。問題は、生殖補助医療の構造自体、あるいはそれを「不妊治療」として推進していくシステム自体が、そういう人を非常に大量に生みだしてしまうということです。
だから本来は、最初にホルモン治療みたいなものから始めて、それではダメだったので次に生殖補助技術を使うか使わないかという段階で、やっぱりいろんな実態を知って、そこでいったん立ち止まって(他のいろんな選択肢を並べた上で)「選択」をするということが必要なんだけども、どうもそういう実態を知らない(知らされない)ままに、医療側の主導でスッとそういう「治療」に入ってしまい、みんながはまり込んでいっている、というのが今の状況じゃないかと思います。
もっとも、そういう技術を使って妊娠して、子どもが生まれた人は「成功者」なのかというと、これもいろんな問題を聞きます。たとえば、私は看護学の講座にいるので、看護師さんから聞くのですが、長い間不妊治療(体外受精)をやってきた人で、実際に子どもが生まれると、わりと出産後の鬱になる人が多いらしいです。子どもに対して愛情がわかないとか、どう接していいか不安で鬱になる、そういう人が非常に多い。(今はもう死語かもしれませんが)「五月病」といって、希望する大学に入ったけど、5月ぐらいになったら全然無気力になって、やがて大学に出てこなくなる、そういう学生のことが問題になったことがありますが、それとちょっと似たようなところがあります。「不妊治療」ということにあまりにも頑張りすぎて、もうそこで燃え尽きてしまう。本当に子どもが生まれることだけが、その人の一番大事なことになってしまっていたために、実際に生まれてきたら、ハーッと力が抜けてしまう。そういうのは何となく分かるわけです。
つまり、本来だったら性交、妊娠、出産、子育てというのは連続した一連のプロセスなんですけど、それを人工的にぶつ切りにして、どこかを人工的に代替してしまうことによって、そういう自然なプロセスを途切れさせてしまうということです。そこがやっぱり大きな問題だと思うんです。
2枚目のプリントのほうに急いで行きます。生殖補助技術は、さっきの着床前診断(受精卵遺伝子診断)なんかもそうなんですが、いのちの選別にかかわるような技術(生殖技術の分類のなかのⅢ)とも非常に深いつながりがあります。実際、体外受精で使うときには、精子というのはそのまま精液をボンと混ぜるということじゃなくて、精製というのをやります。具体的にいうと、精子のいいやつだけを濃縮するんです。このときの精子の精製に使う技術と、(みなさんも名前を聞いたことがあるのではないかと思いますが)「パーコール法」という男女産み分けのための技術(X精子とY精子を比重の差によって分離することで男女を産み分ける技術)は、実は同じ遠心分離の原理を使って、同時に開発されてきたものです。つまり、同じ原理を使った基本的に同じ技術が、一方では男女産み分けのために使われ、一方では体外受精の開発・改良のために使われるわけで、日本では慶応大学が一番早かったんですけど、同じ研究機関で研究が進められてきました。
だから、テクノロジーというのは、それが正当化されるときには必ず、こういう困った人がいる、その人を助けるためにはこういう技術が必要なのだ、こういう技術を使わないとそういう人たちを助けられないんだと言われます。そういう目的は、もちろん「タテマエ」としてはあるんです。研究のときに、必ずこれはどういうふうに社会の役に立つかとか、どういった人を助けるかということをアピールしないと、研究費がもらえませんから。ただ、そうした技術に、どういった利用の仕方があり得るか、他のどういった技術の開発に結びつくかについては、技術を推進している側で「本音」としてはもっているけど、それをはっきり言うと叩かれるので隠しているために、世間には全然伝わらないということもいっぱいありますし、そういう推進者たちにすら予測もできないような技術の展開可能性もあります。こういうことはよく考えていかないといけません。
それから、私たち人間、ヒトの生殖を人工的にコントロールするということになると、やっぱりかなりの人が「気持ち悪い」というイメージを持つでしょうが、動物ということでいえば、いわゆる畜産というのはその最たるものです。先ほど代理出産の話がありましたが、代理出産が一番よく使われている動物は牛なんです。肉牛の子どもを、乳牛のメスに代理出産させるんです。そうすると、肉牛よりも乳牛のほうが身体が大きいですから、乳牛が肉牛の子どもを妊娠することで、母体にかかる負担が少なくなるんです。しかも、子どもを産むことで、乳牛のお乳が、牛乳がたくさん出ますから、一挙両得で非常に経済効果が高くなる。家畜は人間のための経済動物ですから当たり前なのですが、そういう「経済的な価値」に基づいた生殖の操作ということが、ここでははっきり前面に出ています。
どうしても生殖技術の問題は、いわゆる優生思想とか、優生学とかいったものと切り離せないところがあります。「価値のある人間」と「価値のない人間」の選り分け、後者を抹殺していこうとするような優生思想は、かつては国家政策としてやられたわけですが、このごろは、一見「個人の選択」というようなかたちに任されているように見えて、実際には同じようないのちの選別が行われているんじゃないかと、警告をしている人が少なくありませんが、こういう傾向は生殖技術という技術の本性のなかに必然的に含まれているということ、生殖技術というのは(一見そうは見えないものも含めて)全体としていのちの選別ということと深くつながっているんだということを、やっぱり押さえておかないといけないんじゃないかと思います。
プリントの3の2のところにある「選択」と「選別」の連続性についての話は、本当はしたいんだけれども、時間の都合で今はカットしまして、次に、もう一度臓器移植の話を簡単にやりたいと思います。2枚目のプリントの最後のところに、私の書いた最近の論考で今日のお話に参考になるものを挙げているのですが、その一番下に書いてある『宗教と現代がわかる本』という本、(別に本の宣伝に来たわけじゃないですが)1,680円にしてはかなり内容が詰まっていて、大変お得です。その中に私は、「臓器移植医療における『弱者』とはだれか?」という短い論文を書いていますので、お読みなっていない方はそれを読んでいただければと思います。
それから、生殖技術と臓器移植という、ほぼ1980年前後に同時に進行してきた二つの医療の比較みたいなことは、その上の『生命の産業』という本、これは大阪市大の佐藤光先生という方がやっておられる「バイオエコノミクス研究会」という研究会のメンバーの四人で執筆した本なんですが、その中の第4章にかなり長い、100ページぐらいの論文を私が書いていて、そこで詳しく論じていますので、ご参考になさってください。
脳死臓器移植については、この中にもおそらくいろんなご意見を持った方がおられると思うんです。去年、国会で臓器移植の改正案についての審議が行われ、提出された案のなかで最も移植推進を唱っているA案が衆議院、参議院を通って、今年から施行が始まることになるわけですが、そのときに、前の旧臓器移植法の論議でもそうなんですけど、「脳死というのは人の死なのかどうか」ということが非常に議論の的になったのです。実は、私は少なくとも、脳死は人の死かどうかということだけに議論の焦点を当てるのはおかしい、とずっと思い続けています。
まず、「脳死」というのは言葉を使った瞬間に、実は初めに置かれるべき大問題がクリアされてしまっているというか、それが問題だということが隠されてしまっていると思うのです。たとえば、脳死は人の死だと思うということと、脳死臓器移植をもっと推進すべきだということは、イコールでは結びつきませんし、逆に脳死は人の死だと思わないということと、脳死臓器移植はやめるべきだったということともイコールでは結びつきません。そこにはいろんな立場があり得るのですが、一般的に言うと、「脳死は人の死だ」という人は、脳死臓器移植に対して許容的な方向へ行って、逆だと反対的な方向や慎重な方向に行くというのはたしかにあります。
ただ、この「脳死」という言葉というのは、最初に人工呼吸器がICUの現場に導入されたときは使われていなかったということが重要です。現在「脳死」というように呼ばれている状態は、最初は「超昏睡」(フランス語でle coma depasse、「一線を越えてしまった昏睡」という意味)とか、「不可逆的昏睡」(もう逆にはならない、回復することはけっしてない昏睡)とか、そういうふうに言われていたわけです。こういう状態について、「脳死 brain death」という語が使われるようになったのは、実は臓器移植との絡みの中においてなのです。つまり、そういう、もう回復の望めない状態の人にそのまま人工呼吸器をつけておいて、心臓が止まるまで(かつての普通の死の基準に達するまで)生かしておくことで、結局何が問題かというと、一つは経済的な問題があるんです。そういう状態の人を一日「生かして」おくだけで十数万円ぐらいの医療費がかかりますし、もう回復が望めない人がICUに入っていることで、集中的に治療すれば回復可能なほかの人がICUに入れないとか、そういう医療資源の配分という問題もあります。それから、回復もしないのに、機械的にただ延命だけさせられているのは、その人の尊厳みたいなのを無視しているんじゃないか、という問題ももちろんあります。
だけど、それだけの話だったら、別にその人が「死んでいる」という必要はまったくありません。その状態の人を何と呼ぶか、「脳不全」と呼んだって「不可逆的昏睡」と呼んだっていいと思うんですけど、そういう状態になった人は、もう延命しても意味がないし、本人の尊厳を傷つけるから人工呼吸器を外して死なせてあげましょうという、今で言うと、消極的安楽死とか、延命治療の停止とか、それが是か非かという問題だけで済むはずです。その人はすでに「死んでいます」というようなことを言う必要はないわけです。
ところが、そこに脳死臓器移植というのが絡んできたときに、「その人は死んでいるんですよ」というようなレトリックが出てきた。これは、多くの人が非常に誤解しているところなんです。まず「脳死」という事態が先にあって、そういう状態になった人の臓器を誰かほかの人に使ってもらうんだというように、「脳死」というのが先にあって、その後で臓器移植の問題が出てくるんだというふうに誤解しているんだけど、これは、私は根本のところで違っているんじゃないかと思うんです。ここで、お配りしたプリントにある図の2と3をご覧ください。この図についてきちんと説明しようと思うと長くなってしまうので、ここではごく簡単な説明にとどめます。
よく脳死臓器移植を美化するキャッチコピーとして、「いのちの贈りもの」だとか、「臓器移植は愛の医療です」とか言われたりしますが、ドナーになる人、臓器をあげる側の人は、臓器をもらう人に対して、直接「何かをあげる」わけではないのです。実際にはドナーとレシピエントは匿名関係であるのが普通なので、ドナーは贈り物の場合のように、「この人に」臓器をあげたいといってあげるわけではないのです。もちろん主として近親の間で行われている生体移植(生体肝移植や生体腎移植)は例外です。脳死臓器移植に関しても、日本の今度の新しい法律では親族間の優先提供というのが認められるようになっていますけれども、実際にどれぐらいそんなものが起こるかと考えたときに、脳死になる確率なんて100分の1ぐらいのものですから、そういう人の親族にたまたま臓器移植を必要としている人がいる確率は相当低いはずで、実際にはおそらくほとんどないんじゃないかなと思います。
そうすると、本当はドナーの臓器というのは、直接レシピエントの人に贈られているわけではなくて、この図のように、脳死臓器移植を動かしているこのシステムに「提供」されて、そのシステムにおいて医学的な適合性や、待機の順番や待ち時間など、いろんなものを勘案しながら、一つ一つの臓器が特定のレシピエントに「配分」されていくというかたちになっているわけです。
脳死臓器移植の場合、ドナーになる人というのは、そのちょっと前までは、なんとかその人の生命を救うために医師(救急医)によって懸命な治療が施されていた「患者」だったというのが決定的に重要です。その人の救命があきらめられたときに、その人の臓器が、今度は「別の患者を助けるために」利用されるということです。そうすると、一番の問題点というのは、このドナーになる人というのが、一体いつの時点から「ドナー候補」になるんだろうかということなのですが、これについてはほとんどの人が誤解しているように思います。つまり、「脳死」ということが診断として確定した後に、その人がドナーになるかどうか(その人の臓器を移植に使うかどうか)ということが問題になるのだ、というふうに想像している人が多いのですが、これは誤解です。
プリントの右の図(図3)を見ていただきたいんですけれども。この図はけっして医学的なものではありません。「イメージ図」と書いたのはそのためです。脳に重大な損傷を受けた人が「脳死」状態を経て死んでいくときのプロセスをイメージしたものです。横軸が時間軸だと思ってください。縦軸が、人がどのぐらい身体的に(脳の状態も全身状態も含めて)死というものに近づいていくかを表している、つまり下に行けば行くほど状態が悪くなっていくというふうに考えていただければけっこうです。
この図で、Aの状態にあるときには人は生きていますし、適切な治療を施せば回復可能な状態にあります(もちろんそういう治療技術をすべての医療機関や医師がもっているわけではありませんし、救命・回復はあくまで可能性にすぎません)。Cの状態になってしまった人というのは死んでいるわけですが、現在一般に「脳死」と言われているような人というのは、この図ではBの状態にある人ということになります。AとBの境にある点線で書いた線が、「蘇生臨界点(point of no return)」を表していると考えてください。Bの領域に入ってしまった人はもうこの線を越えてしまっているので、いくら治療しても回復する可能性はありません(こういう意味で、現在「脳死」と呼ばれている人につけられた最初の命名「超昏睡=一線を越えてしまった昏睡」というのは非常に事態を正確に言い表しています)。
大切なことは、脳に大きな損傷を受けた人がいつの時点で、この臨界点を超えたのか、ということはわからない、ということです。まだAの状態にいる人(救命可能性のある人)であっても、適切な治療が施されなかったり、救命のための治療をあきらめられてしまったら、その患者はすぐにBの状態に至ってしまいます。いわゆる「脳死判定」というのは、その人の身体がいかに治療しても回復しないような状態にあるんだということを確かめるために、つまりもうその人はAの状態にはなくて、Bの領域に入り込んでいるんだということを確定するためにあるわけです。
実際にアメリカでは、脳死に近い状態で医師に「脳死」だと言われ、「臓器提供されますか?」と勧められたけど、家族が「いや、そんなのは絶対嫌です」と断って、「最後まで懸命に、心臓が止まるまで治療を続けてください」と言ったために、懸命な治療が続けられた結果、仕事を探せるぐらいまで回復された方がいます。これは、普通は、「脳死」というのが嘘だったとか誤診だったというような話になるのですが、私は、これは必ずしも「誤診」という、診断の精度を上げれば多くが避けられるような問題ではなくて、脳死臓器移植という医療の構造から来ている問題だと思います。この患者は、治療によって回復したわけですから、医師に「脳死」だと言われ、救命治療をあきらめて臓器ドナーになることを家族が打診された時点では、Aの状態にいたということです。
その医療現場の技術力とか、どのぐらい懸命に救命治療をやるかということによると思うんですけど、Aの状態にある人であっても、要するに、治療をあまりしないでおいたら、もう当然Bの状態に移行していくわけです。Bに移行してしまった時点で、今の日本で言うと「法的脳死判定」みたいなことをやったら、当然「脳死です」という判定が出ます。しかし、先ほども言いましたように、一体いつの時点でこの線(蘇生臨界点)を越えて、Aの状態からBの状態に移ったのか、ということは分からないわけです。脳死についての初期の文献で、ジャーナリストの中島みちさんが1980年ごろに書かれた『見えない死』という本がありますが、この「見えない死」という言葉は「脳死」という事態を非常によく表現しています。医師でも脳死は見えないんですよ。いろんなテストをして、多分こういう状態なのだろう、もう救命・回復は期待できないだろう、ということは分かる。ただ、いつその一線を越えてしまったのかは、見えないし、分からないのです。
先ほどのような例が示しているのは、いわゆる脳死臓器移植において、それまで懸命な救命治療を受けていた患者がある時点で「ドナー候補」になる、そういう視線を向けられる時というのはいつかというと、(もちろんすでにBに行ってしまった場合もあるだろうけれども)まだAの状態にある時でもあり得る、ということです。ここで重要なのは、その人を脳死にさせないための治療法というのと、臓器移植に向けてその人の臓器を新鮮に保つための医学的な措置というのは、まるっきり逆だという事実です。
つまり、簡単に言うと、脳死にさせないためには、脳の腫れをできるだけ取らなくてはいけません。そのためには、体を脱水状態に近いような状態にもっていく。点滴の量を必要最小限に減らし、尿をどんどん出して脳の腫れをできるだけ取るわけです。体を冷やした方が脳の腫れは抑えられますので、日大板橋病院の林医師がやっているような脳低温療法という治療法もなされています。ところが、臓器を移植に使おうと思ったら、これは野菜なんかと同じですが、臓器をみずみずしく保つために、点滴で輸液をたくさん入れて、抗利尿剤を入れて、要するに体の水分を増やすわけです。つまり、まったく逆のことをやるわけです。だから、もしまだこのAの状態にある人に、もうこの人はいずれ脳死になるからと、救命治療をあきらめて臓器ドナーにするための措置を施したら、確実に一直線にBの状態、すなわち「脳死」になってしまいます。だから、こういうことは「脳死」判定の確実性とかいった問題ではなくて、脳死臓器移植というシステムの構造上の問題なのです。
よく、日本で脳死臓器移植が進まないのは、「和田移植」の後遺症で、医療界に対する不信があるからだ、というようなことが言われるのですが、たしかにそういう部分は否定できません。ちなみに、和田移植は、検証したらはっきり分かるように、まったくの「殺人」です。ドナーになった人も脳死でもないし、レシピエントになった人も、あの手術をやらなければ絶体絶命っていうような人ではなかった。だから二重に殺人なんです。
それはもちろんあると思うんですけど、それではそういう不信感がなくなったら、つまり強引に移植医療を推進するために医師が脳死でもない人から臓器をとるようなことがなくなったら、脳死臓器移植への不信感は消え去るのかというと、それは違うでしょう。私は脳死臓器移植という医療システムを支えているのは、根本的に人のいのちを天秤にかけて、「こっち側を犠牲にして、こっち側を助けましょう」という思想だと思うんですね。だから、そのあたりのことをきちんと理解しないと、「移植を受けないと助からない、かわいそうな人がこんなにいます。この人たちを見殺しにするつもりですか」という推進派のレトリックにまんまと乗ってしまうのです。
先ほどの生殖医療の場合と非常に似ているのですが、レシピエントになる人、つまり実際に移植手術を受けられる人というのは本当に少数です。アメリカのように非常にバンバン臓器移植をやっている所でも、移植を希望している患者さんのうちの、本当に小さな割合の人しか移植は受けられないんです。多くの人がずっと移植を待ち続けて、希望だけは持たされながら、そのかいもなく亡くなっていくわけです。
そうすると、ドナーになる人やその家族も、またこういう移植を待っている患者さんも全部含めて、脳死臓器移植というこのシステムのなかにみんなが巻き込まれていきながら、それによって幸せになる人はごくごく少数で、このシステムだけがどんどん増殖していくという、さっきの生殖医療と非常に似た構造になっていることがわかるでしょう。だから、そのシステムの全体を見ないで、一部分だけを見て、こういう素晴らしい技術を開発されたから、移植によって助かるこの人たちをもっとたくさん助けるべきだと、そこだけに注目したら、この医療をもっと進めるべきだという議論にしかいかないんです。これはさっきの不妊の人たちの場合と一緒なんです。
だけど、そういう議論で果たしていいんだろうかということは、やっぱり考えなければいけないことです。2枚目のプリントの右側のほうで少し書いていますが、私が講義で脳死臓器移植についてこういう話をした後で学生にレポートを書かせると、たとえば、「先生の言うことはよく分かるけれども、どうせ助からないんだったら、その人の身体を社会に有効に使ったほうがいいんじゃないですか」と書いてくる学生っていうのは結構いるんですね。だけど、これは本当に怖い考え方だと思います。
ここでは詳しくは説明する時間がありませんが、たとえば戦争中に、皆さんご存じのように、日本の「七三一部隊」みたいに、強制的に微罪で逮捕してきた外国の捕虜をわざと細菌に感染させて、そのまま生きたまま解剖するとか、そういったひどい人体実験が行われたわけです。ナチスドイツの医学者も同じようなことをやったわけです。ものすごく非人道的な、悪魔みたいな医師がそういうことをやったのかというと、ほとんどはそうじゃない。もちろんそういう医師もいたかもしれないけれども、ほとんどは平均以上の良心的な医師、家庭では良き父であって、普通に世間的にも尊敬されているような人たちだったわけです。
ところが、人の生命を助けるべき医師が、なぜそんなことに手を染めちゃったのか。やっぱり戦争という状況が彼らを後押しした面が大きいと思います。ナチスドイツの場合、収容所のユダヤ人について、医師や医学者には「どうせこの人たちは殺される人なんだ」という意識があったのでしょう。自分たちがわざわざ殺すわけじゃない。だから、「どうせ殺されるその人たちを、医学の発展のために、将来の病気の人たちを助けるために利用して何が悪いんだ」、という形で自分たちの行為を正当化したわけです。実際には良心の呵責とかを感じていただろうけれども、そういうのが自分に対する言い訳、大義名分にもなったわけです。日本の七三一部隊の場合も、人体実験の対象にされた当時の中国人などに対しては、まさに同じように、「どうせ(戦争によって)殺される人たちなんだ」という意識があったと思います。そうすると、先ほどのように、「どうせ助からない人なんだから、この人の身体を他の患者のために、あるいは医学の発展のために有効利用すべきだ」という考え方を進めていくと、やっぱり非常に怖い、と私は思ってしまいます。
最後にプリントの5のところです。私のような話をすると、大体生命倫理学のなかでは嫌われます(笑)。そもそも「生命倫理学」ってどういう学問なのか、どういう人たちがやっているかをご存じない方もいらっしゃると思うんですが、特にアメリカなんかの英米系のバイオエシックスというのが、今までどういう役割を果たしてきたかというと、大体次のようにまとめられると思います。「先端医療」と呼ばれるような新しい医療技術によって、それまでになかったような社会的な問題とか、倫理的・宗教的な問題とか、法的な問題が生じてきたときに、本来はそうした問題について根本的なところから考えるというか、それは結局は「生とは何か? 死とはなにか?」ということを私たちが徹底的に問うことを必要とするわけです。ところがいわゆる「バイオエシックス(生命倫理学)」というのは、そういう問題について徹底的に考えるのではなくて、あるいは徹底的に議論して結論が出るまではそういう新しい医療技術に待ったをかけるというのではなくて、そういう新しい医療技術が社会の既存の価値観などを揺さぶるような場合には、その地ならしをするというか、新しい技術をうまく社会に軟着陸させる、そういった技術に対する根本的な反対を押さえ込みながら、基本的には技術や研究を推進する方向を是認しつつ、それがあまり極端な社会的不平等をもたらしたり、弱い立場の人たちを食い物にするといった人権侵害を引き起こさないようにチェックしながら、ある種の調整役のようなものを果たしてきた、と言えるように思います。
私みたいに、「生命を操作するような医療技術というのは、実はきわめてうさん臭いんだよ」というような話をすると、生命倫理学の学会などではたいてい嫌われます(笑)。もっぱら生命倫理の専門的で細かい議論をやっている研究者には、私のようなラフな議論は「素人くさい」とバカにされることもあります。ただ、言いますけど、むしろこういう問題を考えるときには、学者の専門的な議論の蓄積よりも、素人が持っている感覚、何もそういう知識のない人が持っている感覚というのが非常に大事なものだというふうに思います。「生命操作」という言葉を聞いて、「何か気持ち悪いな」と思う普通の人の感覚が大切なのです。もちろん気持ち悪いから反対だというふうには言えません。「気持ちが悪い」という感覚は反対の根拠にはなり得ません。しかし、私は、そういう(ある意味素朴な)感覚っていうのは、いろんな技術が実際に使われるとき、あるいは実験的にそういう技術が推進されていくときに、私たちに「見えていない部分」「隠されている部分」というものを発見するためのアンテナのようなものとして、そのためのツールとしては、十分役立つのではないか思います。生命操作をめぐる全体のシステムのなかで、実際にそういった医療技術にどの程度の科学的な妥当性があるかということや、あるいはどの程度の人がいろんな選択肢が与えられているなかでそれを主体的に選ぶようなことができているのかということを、個々に見ていくときに、そのシステムの一部だけを見ていたのでは見えにくいような「気持ちの悪い」部分を発見しやすくなるということです。
たとえば、「生命操作」なんて言っているけれども、実際には「操作できていない」という事実があるわけです。臓器移植の原理は簡単で、いわゆる「パーツ交換」です。自分のものは使えなくなったから、ほかの人のパーツと交換しましょうという発想です。臓器移植が可能になったことで、実際に(人間の体のいくつかの部分については)すでにパーツ交換ができているんだ、と言う人がいます。たとえば、私の友人の生命倫理学者の中には、臓器売買についてもすべて反対じゃないという人もいるんです。その人に言わせると、「すでに臓器移植というパーツ交換ができている。パーツ交換ができるものは、自然に商品化していくのが世の中の流れだ。臓器の商品化を認めない、といくら頑張っても、長期的には絶対そうなるんだ」ということです。しかし、私がそのとき彼に言ったのは、「一体、パーツ交換って本当にできているんですか?」ということです。
つまり、臓器移植を受けた人が、拒絶反応を抑えるために一生免疫抑制剤を飲まなきゃいけないということ、移植を受けてもやっぱり助からない人もいっぱいいるということは、実際にはパーツ交換はできていない、ということです。移植を受けなかった人と、受けた人とで、どのぐらいその後の生存率の差があるかについてすら、はっきりしたデータがありません。母集団が限定されたデータはいくつかあるんですけど、全体的でかなり網羅的なデータはないです。だから、臓器移植は「パーツ交換の原理」に基づいた医療ではあっても、実際にそれによって「パーツ交換ができている」わけではないのです。
それから、生殖技術にしたって、体外受精がどれだけ普及して一般化してきたといっても、さっき言ったように、平均すれば成功率は1割ちょっとなんです。アメリカなんかはもうちょっと高いです。日本の場合は、少子化のせいで、本来はあまり技術力のない産科の病院とかが、赤ちゃんの数が減って経営難になるのを防ごうと、こういう市場に参入しているところがあって、そういう技術力のない病院が全体の成功率を下げているというところはありますが、少なくとも日本の場合は実際にこんな状態なわけです。そうすると「まだほとんど人体実験ではないか」というような技術が平気で使われているわけで、それをもって、「生命を操作できている」なんてとても言えないわけです。
ここで「生命操作」をめぐる象徴的な話を一つだけしたいと思います。そうした生命操作技術の裏側、見えない部分に一体どんな風景があるのか、ということがよくわかる例です。数年前ですけども、アメリカでクローン猫が初めてできたときに、テレビのニュースを見ました。そのときに、猫のクローンの作製を依頼した人、すごい金持ちそうなミンクのコートを着たおばあさんが、そのクローン猫を抱いて番組に登場したのですが、それを依頼した理由というのは、自分の長年かわいがっていた猫が死んで悲嘆に暮れてしまって、その猫の代わりというよりは「同じ猫」がどうしてもほしいということでした。(何の細胞を採ったのか忘れましたが)その猫の体細胞を基に作られた猫は、前の猫(の写真)と本当にそっくりでしたが、その猫を「かわいい~。もう、仕草までそっくりよ」とそのおばあさんがニコニコして抱いているんですね。それを見て、私はものすごく腹が立ったんです。「何だ、こいつは!」と思って、(私は猫を飼ったこともありませんし、特に猫好きでもないのですが)とにかく「こんなやつにだけは猫を飼ってもらいたくないな」、と思ったんです。
というのは、体細胞クローン動物というのがどのようにして作られるかについて、ちょっとした知識があったら、その猫を一匹産むために、ほかの猫が、罪のない猫が、どれだけ苦しい思いをして利用されたかというのが丸分かりだからです。つまり、体細胞クローンというのを作るためには卵子が要ります。卵子というのは女性や雌の身体から勝手に排出はされませんので、排卵誘発剤を使って卵巣をパンパンに膨らませて、全身麻酔をかけて取り出すわけです。当然、猫にインフォームド・コンセントはあり得ませんから、そうするとどこかの猫(そこらの野良猫でしょうか)がたくさん無理矢理引っぱられてきて、痛い注射を打たれて、麻酔をかけられて卵子を採られているわけです。その卵子の核を取り除いて、そこにクローンを作ろうとする元の猫の体細胞からとった核を入れて、その細胞を初期化したものを今度は猫の子宮に入れて妊娠させ、子どもを産ませるわけです。そういうのを何回も何回もやられて、おそらく1万回ぐらい試行して初めてその一匹の猫が誕生している。だから、その一匹の猫のために、一体どれだけの猫が痛い思いをして、苦しい思いをしたか。
体細胞クローンと動物いうのがどういうふうに作られるかということと、人間の体外受精で卵子を採るときに、どれだけ女性に身体的、精神的な負担がかかるかということについての、ごく初歩的な知識さえあれば、一匹のクローン猫を見たときに、こういう風景はすぐ見えるはずですよね。だけど、「クローン猫を嬉しそうに抱いているおばあさんを見て、なぜ私が、腹が立ったか分かりますか?」って、学生に話をすると、学生はキョトンとしています(一応、そのときまでの講義で学生は、卵子採取がいかに女性の身体に負担になるかといったことは学んでいるのですが)。種明かしをすると「はーっ」と言います。
この話に象徴されるように、実は生命操作システムというのは、そのある部分だけにスポットが当たっていて、その裏でどういうことが行われているのかというのは、見えないように、見えにくいようにできているんです。そういう「見えない部分」をやっぱりきちんと明らかにしていかないと、とんでもないことになる気がします。
臓器移植について一つだけ言うと、今回の臓器移植法改正審議はきわめてずさんなものだったと思いますけれど、A案に反対する人たち、特に子どもの移植に反対する人たちや慎重派の人たちがけっこう表(おもて)に出したのは、長期脳死の子どもの存在ですね。数としては少ないのですが、臨床的には当然脳死と判定されるような状態なので、もちろん回復はしないんだけど、人工呼吸器を付けて数年以上(心臓が停まらずに)生きていて、自宅で生活している。意思の疎通はできませんが、髪の毛も伸びているし、身体も大きくなっているし、ちゃんと普通に暮らしているわけです。そういう子どもを表(おもて)に出してきて、「脳死は人の死だという人は、この子は『死んでいる』と言うんですか?」と問いかけたわけです。
反対派や慎重派がとったこの戦略は、一言で言うと、脳死臓器移植という医療のなかでの「見えない部分」というのを、「見える部分」に引き出してきたということだと思うんです。「見えざる弱者」を、「見える弱者」として押し出してきた。だけど、こういう長期脳死の子どもの場合には非常によく見えますが、普通の脳死の人の場合にはきわめて見えにくいだけの話であって、基本は同じだと思うんですよ。普通、脳死になる人で多いのは、(日本だと)交通事故で頭を打って脳死になるというケースでしょう。そういう人のところに、たとえば、家族の人が急な知らせを聞いて駆けつけてきて、何とか助かるんじゃないかと最初は希望をもっていたのが、だんだん厳しい状況になっていく一方で、ついには「脳死です」と宣告されるような、そういう状況というのは、テレビには絶対に映りません。「見えない」んです。そこで家族の人たちがどういう気持ちになったのか、「脳死」と言われた人との間でどのような看取りの時間が過ごされたのかについては、もちろん後になってから(柳田邦男さんや杉本健郎さんみたいに)自分のそのときの体験について証言している人はいらっしゃいますが、長期脳死の子どもが家族と共に生活している姿のような形で、そういう現場がテレビで映されることはありません。
だから、いくらでも見えない部分というのが切り捨てられて、よけい見えないようにさせられる。臓器移植をしないと助からないという子どもだけを前面に出して、「この子をあなたたちは殺すんですか」と、そういうほとんど脅迫的なアピールばかりがなされている。ほとんどの人は一方的なものばかり見せられているわけです。
代理出産についても、さっき島薗先生が言われたように、いま世論調査みたいなのをすると、結構肯定派の人が増えているというのは、やっぱり、テレビ番組なんかで代理出産を求めているような人の物語ばかりが流されて、同情を集めているということが大きいでしょう(日本で言うと、向井亜紀さんのご夫婦をめぐるドキュメンタリーの影響力が大変大きかったと思います)。
そういう偏った、一方的な情報だけが流されている部分について、やっぱりきちんと冷静に、客観的に見ていくということをしないと、とんでもないことになるでしょう。時間を超過していますので最後のところは飛ばしますが、一つだけ言いたいことがあります。さっき島薗先生が厚生省の審議会について分析されたように、そうした公的な生命倫理の議論のなかで、各専門家からの意見として、「医学的な立場からはこうだ、倫理的な立場からはこうだ」というように意見が聴取されることが多いのですが、ここはちょっと問題だと思っています。そういうときに「医学的な立場から」発言する人は、きまって移植医だったり、生命操作技術の推進派の人だったりします。医学とか医療とかいうものは、人間の文化、社会の一部です。当然そうですね。医学は「科学」だと思っている人がいるんだけど、私は、医学は少なくとも、物理学とか工学なんかと一緒になるような「自然科学」ではないと思います。医学というのは、ある意味すごくアバウトな学問で、科学的な手法を使ってはいるけれど、真理の発見そのものを目的とするのではなくて(結果的にそこから何か人の役に立つものが生み出されるというのではなくて)、はじめから人を助けるという実践的な目的が前提になっているわけです。
そうすると、人のいのちというのをどういうふうに見て、どういうふうにそれに対して接していくべきか、これは広い意味での「倫理」だと思うんですけど、医学と倫理っていうのは、別々にあるものじゃなくて、実は、医学自体のなかに倫理的な要請がある、つまり倫理が含まれているわけです。物理学とか化学のような自然科学だったら、そこで得られた知識に基づいてそれを応用し、人の役に立つものを作っていく際に(もちろん人に大きな害を及ぼすものも作れます)、その技術を開発したり、それを使ったりするための倫理はあっても、物理学や化学そのものに倫理はないですね。あるとしたら、研究成果を発表するときに論文をねつ造したりするのはいけないといった、そういうレベルの話だけです。
ところが、医学とか医療というのは、人を助けるために生み出された文化的、社会的構築物ですから、それ自体のなかに倫理があるんだと思うんです。たとえば、脳死臓器移植にしても、生殖医療の問題にしても、「医学的」などと言ったって、医師や医学研究者の中にもいろいろな考えの人がいるわけです。みなさんもご存じだと思いますけど、脳死臓器移植に断固として反対している医師や医学者はいっぱいいます。にもかかわらず、「医学的な立場から」の発言というと、推進派の移植医とか病理医とか、そういう人たちばかりが出てきて、宗教家とか倫理学者とかに反対派や慎重派の役割が振られていることが多いのですが、これはおかしなことですよね。「医学・医療」対「倫理・宗教」などという、こういう不毛な二分法を基に考えるのではなくて、やっぱり私たちは、人がいのちをどのようにとらえ、いのちあるものにどのように接するのか、という原点に戻って生命倫理の問題を考えていかなきゃいけないんじゃないか、と私は思っております。ちょっと雑な話ですみませんでした。終わります。(拍手)