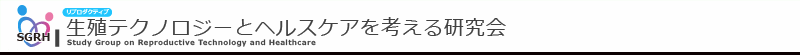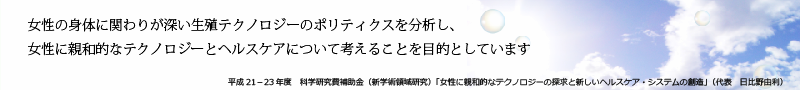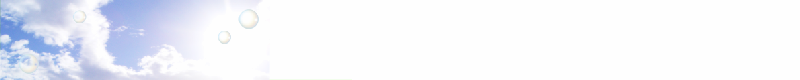質疑応答
島田啓子(金沢大学医薬保健研究域保健学系教授):金沢大学の島田です。齋藤先生のご講演は初めてお聞きしたのですが、雑誌等ではよく記事は拝見させていただいております。私は助産の教育をしていますので,今回のご講演で大変興味深い、ものすごく深いことを教えていただきました。もう一つ教えていただきたいのは、今、「リプロダクティブ・ヘルスライツ」から考えると、もし女性に自己決定権があるならば、都合の悪いことは決定しないと思うのです。私は、その人がその人らしく生きていけるための「ライツ」ではないのかと考えながら対応しているつもりです。
一つ教えていただきたいのは、いろいろな医療現場で出生前検査を行うとき、ドクターは妊婦さんに、「羊水検査をしますか」とアプローチをします。そのときに、問われた女性にとっては選択も任されているわけですが、通常は十分な情報を与えて、選択できる環境を作ってから決めてくれというのが、普通のあるべき姿だと思います。「どうですか、決めてください、来週返事をください」の間に、どこまでの情報が伝わっていて、どのような決める力量がその妊婦さんにあり、決めるまでの悩みやゆらぎみたいなものが、どこまで支援できる環境があるのかが非常に疑問なのです。
結論からいくと、女性に自己決定権があると、表向きはドクターが情報を提示されますが、決定したのは結果的に妊婦さんです。どんなベビーが産まれようが、その後の経過がどのようになろうが、「あなたが決めたのだから、自分たちはベストを尽くしたので、それ以上のことはもう考えないほうがいい」という結論になっていくことも少なくないと思います。
このへんをどのように理解したらいいでしょうか、倫理的な問題も含めて、自己決定できる問題を考えると、今、医療者はどのような認識でいたほうが望ましいのでしょうか。先生からぜひとも教えていただけたらと思います。
実はもう一つ、昔は刑法的にどこから人間なのかと言ったとき、頭が出たときとか、体が出たときという争いがありました。今は生前遺言のようなかたちで、私は教育上、二つの生命体を同時に扱わなければいけない専門性の中で、母体を優先するのか、胎児を優先するのか。多分将来ドクターになられる、ここにいらっしゃる皆さん方は、当然救急車で搬送されてくれば、まず母体が優先ではないかと思います。その女性が、もしも妊娠中に万が一のことがあったとき、「私の命よりも、おなかの中の赤ちゃんの命を優先して欲しい」ということを主治医に伝えておいたら、それはどこまで可能なのでしょうか、医療者はそういう希望をどのように受け止めて、理解して、説明なり対応なりをしていけたらいいのでしょうか。
齋藤有紀子:ありがとうございます。大変難しいご質問で、後で加代子先生からも名案のご提示があればと思いますが。
一つは、羊水検査のために、例えば紙1枚渡されて、1週間だけで、とても十分な説明を受けた上での決定になっているとは思いにくいし、その方がどれほどの気持ちで「検査します」とサインを書かれたかを推し量るすべが、医療職になかなかない中で検査が行われる。確かにそうかもしれないですが、一方で、本当に完璧な説明と理解も逆にないだろうと思います。当時は熟慮の上で納得して検査したつもりでも、後でものすごく女性が後悔することもあれば、あまり何も考えずにやって、後から振り返ってもあれで良かったと思う方もある。そのバリエーションを考えると、正しい検査の受け方、いわゆる“お作法”のようなものはないような気がします。
一般論というより個人的な見解かもしれませんが、当事者が悩んでしまったとき、それは説明が足りなかったと、後出しじゃんけんで当時の問題を評価したり、当事者が納得していれば、当時のものは問題なかったと考えるのは、少なくともやめたほうがいい気がします。もちろん、十分な説明なくいろいろな、母体血清マーカー検査なり、羊水検査なりが行われることは改めなければならないと思います。とはいっても、あとから「あな たのは本当の自己決定ではなかった。先生の説明も足りなかったし、あなたは不足した情報で決定したのだから」ということを、その妊婦さんの決定をあとから誤評価する言葉として付けるのは、逆にまたそれも酷です。偏った、いろいろ不足な情報の中でも、それでも決めているのが今の女性たちだと思います。その分のたくましさも含めて、自己決定という言葉を引き受けることも必要だという気もしています。
もう一つは救急のことですね。多分、「私はもう死んでもいいですから」と救急で言われて、それで良いという自己決定はないわけで、やはり医療者には女性に対する救命義務はあるし、救命する期待可能性が医師にはかかっています。赤ちゃんの命のためと言われても、妊婦さんの命を後回しにするのはあり得ないことだと思います。どちらの救命にも努め、どちらかを優先することはできないし、しないという原則で一応進めなければいけないと思います。その中で、手を尽くした上で、次にどうするべきかが出てくるのだと思います。
以前、このような話もありました。妊婦さんが瀕死の状態で救急に運ばれました。夫は、赤ちゃんだけは助けたい、もちろんそうですが、それを見守っている医療職の人が、お母さんはほとんど亡くなりつつあり、亡くなってもおかしくない状況でいるにもかかわらず、胎児のためだけに、胎児生命を維持させるための装置のように、妊婦を生かすことに抵抗を感じていました。お父さんたちの赤ちゃんを助けてほしいという気持ちももちろん分かるけど、それも妊婦さんの意思かどうかは分からない、当然赤ちゃんを助けてほしいと思っているだろうけど妊婦さんがそう言ったわけではない。そういうかたちの中で、妊婦さんを見ているのが痛ましい気持ちもあってつらい、現場で何を優先して考えればいいのか分からないと言われたこともありました。多分、救急の妊婦さんのケースは、いろいろなことがあるだろうと思います。
質問者1:医学部の人間ではないのですが、一つ質問させてください。始めのスライドで、現在、遺伝子レベルの確実な診断について、確率性だったものが確実性になり、そのことで新しい問題が出てきたという話だったのですが。筋ジストロフィーについては確かにそのとおりだと思うし、非常に深刻な問題が増えてきていると思います。一方で、そういうものが増えてきたことで、確実に疾患の発症が分かるという印象が一般の方々に広がって、実際には確率レベルでしかまだ分からないことも、もっとたくさん出ているのが現状だと思います。
遺伝カウンセリングの現場で、女子医大にいらっしゃる方々は知的レベルの高い方が多いからそういう誤解は少ないかもしれないですけど、やはりそれしか分からないのか、結局確率でしか分からないのかという反応もあるかと思います。そのときの対応の仕方とか、その反応には主にどのようなものがあるか、現状を教えていただければうれしいです。
斎藤加代子:遺伝子、ゲノムで全部分かるわけではなく、例えば、多因子性のものはまだ確率的なものです。いくつかのファクターが関わる事、薬の効きやすさなどの、薬理遺伝学(ファーマコジェノミクス)をわれわれのセンターも始めていますが、抗がん剤やリウマチの薬が効くか、副作用が出るか、それもまったく確率的なところです。
例えば、30%の人たちは副作用が出るとか、あなたの遺伝子多型だと10%ぐらいの人たちが副作用が出るということを話しますが、そのときの対応としては、30%や10%の残りもきちんと言うことです。例えば、30%の人が副作用を出して、70%の人は出さないこと。あるいは、10%の人が出して、90%の人は出さないという、裏表をきちんと説明することは、確率を話すときの一つの大事なところです。大体、30%異常が起こるというと随分異常が起こることが多いという印象を受けるところですが、70%異常が起らないと言うともっと多くの割合で異常が起こらないのだ、と感じると思います。そのような数のマジックがあるので、確率的なものを説明するときは、その裏表、両方をきちんと説明すること。
それと限界を説明します。なぜ限界なのかというところまで、なるべく説明するようにしています。例えば、薬理遺伝学のときによくあるのが、なぜ30%、70%なのかを聞かれます。それはなぜかというと、薬の代謝酵素が複数あるからです。1つの薬を飲んでも、例えば吸収するときの酵素、肝臓において代謝に関わる酵素、腸に行ったときの吸収の酵素、尿から出るときのトランスポーターなどが全部関わり、その組み合わせで確率が出てきます。研究が進めば、将来的には副作用が出る確率や効果が出る確率が、0%か100%かになると思います。
肥満も、単一のファクターによって決まるのではなく、そこに複数の肥満に関する遺伝子のファクターや環境のファクターが関与します。高血圧でも何でもそうで、1つの問題ではない多因子性のものは複数のファクターがあり、それが相乗的になると100%か0%か分からない。1つのファクターだけで判断はできないことを考慮することも大事だと思います。まだ確率的なところで分からないことがたくさんあるという話は、やはりせざるを得ない場合が多いです。
齋藤有紀子:私が質問してもいいですか? 貴重なお話というか、レクチャーしていただいて、頭にスッと入りました。ありがとうございました。例えば、PGSのようなスクリーニングのかたちで着床前診断を使いたい現場のニーズが強くある気配を、慎重と言われている産科婦人科学会の中でも感じる。本当にいろいろな学会などと、もっといろいろな技術を学び、使いたい感じだとおっしゃいました。
さらに現実でよく聞くのは、染色体異常のスクリーニングは実際に不妊クリニックで結構されているのではないかと、データはないですけどよく聞きます。きょうだい姉妹間の卵子の提供なども、学会が慎重でも現場では、実際は友達を連れてきてもやっていたりする所もあるという話も見聞きします。そのアンダーグラウンドの現場のニーズや医師の裁量で進んでいってしまう現状については、どのようにお考えでしょうか。やはり、疑問を感じる人は、それを言い続けていくしかないのか、特に卵子のことでは、最後は仕方ないことなのか、先生のお考えをお願いします。
斎藤加代子:実際に堂々とやって、産科婦人科学会と裁判的なやり取りをしている方もいれば、本当にアンダーグラウンドでということは実際にはあるかもしれません。私も、実際にアンダーグラウンドでどのぐらいやっているのかは分からないですが、話は聞くことがあるので、そのような傾向はあるかもしれないと思っています。
産科婦人科学会の方たちは本当に考え方の幅が広くて、着床前診断を進めていく方向に対して、非常に慎重な意見を述べている産婦人科のドクターたちもいます。やはり、日本の文化としてどんどん進めていくことに対して、また代理懐胎に関する問題点などに対してです。要するに、先ほど先生がおっしゃったような、「第三者である他人の体を傷つけてまで」という考え方をしている方もいます。私も産婦人科の医師たちの中に深く入っているわけではないですが、公開討論会などの現場に行き、両側の討論を聞いていると、産科婦人科学会の方々も大変に高い見識を持って判断をしておられると思います。
一方で、やはりどんどん進めないといけないと思っている人もいます。様々な考え方がある、考え方のバリエーションというか多様性としてお互いを認めながらやっていかないといけないのかと思います。お互いに認めるなら何をしてもいいという意味ではなく、産科婦人科学会としてどうするかはきちんと筋を通し、いろいろな問題が起ってきたときに、外部委員を含めて議論をする、または第三者機関などで検討をするなど、広く意見を求めつつ、対処していくことが求められていると思います。
白井千晶(日本学術振興会特別研究員):貴重な話をありがとうございます、白井と申します。先生のお話の中でも、遺伝に対するイメージと遺伝子に対するイメージという話と、少しかかわると思いますが、一つ質問させていただきます。
実際に妊娠している方から聞く、漠然とした遺伝に対する不安があります。例えば、AIDに関する議論でよく出てくるのは、異母きょうだいで結婚してしまうかもしれない確率に対するバックグラウンドで、近親婚に対する漠然とした遺伝に関する不安があると思います。父親からの性虐待で妊娠した女性が、漠然とした近親婚に対する不安があって中絶をする。精神的なこととは別に、遺伝に対する漠然とした不安なのか。あるいは自分の息子との性関係において妊娠した女性が、遺伝に「何かあるのではないか」という漠然とした不安でいらっしゃった方には、現場としてどのようなカウンセリングなり、話をされているのかを、常々疑問に思っていたので、教えてください。
斎藤加代子:非常に近い近親での相談は、私は受けたことがなく、いとこ婚までの相談は結構多いです。いとこ婚に関しては、問題になるのは、稀な常染色体劣性遺伝をする遺伝性疾患です。多くは1万人から数万人に1人というまれな病気です。ですから可能性が可能性が高くなるといっても、せいぜい千分の1程度、つまり1000人に999人は病気になりません。一方で、日本人は、血族結婚がない人たちでも、ある遺伝性疾患の保因者である確率は50から500分の1くらいあります。自分の家系に誰も遺伝性疾患の患者がいなくても常染色体劣性遺伝の保因者である可能性があるのです。また、新生児においては、5%ぐらいの頻度で遺伝子の変化を、新生児期に起こす状態にあります。そのような確率を考えていくと、いとこ婚においては劣性遺伝性の疾患が近親にいない場合には問題としないという考え方です。
さらに近い近親になると、やはりそれはまたリスクがすごく高くなってきます。きょうだい同士、または親子だったりすると、遺伝子の変異を持った者同士の可能性はより高くなります。それは漠然とした不安より問題となります。しかし、その前に、DV的な問題を解決しないといけないと思います。遺伝子や遺伝という問題としては、やはりかなりリスクが高くなると考えます。いとこ婚までは、近親婚として計算上許されていますが、より近い関係であった場合、私たちとしては、やはりその背景を解決するほうを、私としてはDV的な問題、親子間の問題、そちらの解決のほうを、遺伝カウンセリングよりも先にやらないといけないと思います。
柳原良江(東京大学人文社会系研究科・グローバルCOEプログラム特任研究員):柳原です。先ほどのご発表の中で、自己決定で述べられない領域としてさい帯血を出されました。私の知っているトピックです。日本でも一時期ありましたが、アメリカで、さい帯血を提供しようというキャンペーンが行なわれ、その裏には、さい帯血を使ってビジネスをしている企業がありました。さい帯血を健康な母子から採ることは、そこで胎児に本来流れるはずの血液もなくなってしまうし、余計な処置もあることでリスクが高まるけど、そのような情報は伝えられずに、世の中のためになることだと。アメリカの場合は、さい帯血を採っておけば、赤ちゃんが将来何かあったときに役立つかもしれないということで採られていました。採ったものは、本人に使われるために保存するだけではなく、ほかの人にも使えるように売られていたことがありました。そこで女性の自己決定が、経済的な力、社会的な力に奪われた状態で、バイアスをかけた状態で行なわれていたことが問題になるトピックがあるので、思い出しました。
話を伺っていて思ったのは、法学の中で自己決定という言葉をどのような文脈で用いているのかという点です。私の不理解と、認識は違うのかもしれないですけど、私の思っている範囲では、日本で自己決定の議論が医療の現場へ出てきたときは、医師から患者に対して、医師の持つパターナリスティックな圧力に対する手段としての自己決定であり、何らかの権力に対して、弱い人が自分の意思を何とか伝えて行使していく意味でとらえていたものです。同じように女性の自己決定は、基本的に女性はいろいろな領域で圧力を受けている。だから弱者として、アサート(assert)していくという意味での自己決定だと思います。自己決定自体は、女性に限らず弱者はどの人でも言えるので、非常に相対的な概念で、もちろん男性でも障害者をはじめ様々な方に自己決定は使えます。
教科書的なことになり申し訳ないです。少し説明がしたくなったので、細かいことを話してしまいました。
女性の自己決定と言ったときに、わがままととらえられている視点があるとおっしゃったのは、多分女性の自己決定の言葉から組み入れられてしまっているのだろう、自己決定自体は弱者に対するものであるにもかかわらず、女性が自分の弱者性のないもの、男性と対等な場においても、女性としての抑圧を受けていない領域についても、「女性の」という冠を付けることで、ある意味エゴと呼ばれる、弱者救済以上の欲求を権利として主張しているように思います。以上です。
齋藤有紀子:さい帯血は、確かに日本でも、自分の赤ちゃんが将来病気になったときのために採っておけば、その子のために使えるとか、社会貢献で、再生医療で待っている人に役に立つとか、ボランティア精神に訴えるかたちのみで言われています。お産は何が起こるか分からない緊張感を持ってやらなければいけない状態の中で、胎盤やさい帯を清潔な環境で取り扱って、それだけきれいに別のノウ盆で処理してというと、医療者もそれに人手や神経を割かれる。その中で妊婦さんへの関心や注意力が、もし少しでも削がれてしまうことがあれば、確かに問題です。さい帯血をいただいた人といただかない人で、妊婦さんに払われる関心が変わる可能性があるとは、医療者は当然説明しないので、そのあたりの問題は確かにあると 思います。
自己決定は、弱者が自分の主体性を主張するためのものだというのは、もちろん、そういう面があります。自己決定とあえて言わなくても、自分の意思表示が受け入れられる人たちは言わなくても済むからです。「自己決定権」と言わなければいけない場面や、それが機能する必要がある場面は、社会的に弱い立場や、少数の声なき声、あるいはサイレントマジョリティの本音だったりすると思います。
今日申し上げたかったのは、そのことではなくて、では、平等な状態の中での自己決定というのは自己決定ではないのかというと、それも自己決定ではないかということです。他人からとやかく言われずに、自分の自由意思が尊重される。他人の生命を奪う、他人の財産を奪うことにかかわらない限りは、人は自由でいられるという、自由を根拠にした自己決定であれば、行き過ぎの自己決定は本来あまりないはずです。だけど他人から見れば、それを今この場で言うのは、あなたはいいかもしれないけど、ほかの人のことはどう考えるのかとか、あなたがそれをやったら、ほかの人への影響はどうするのか、これほど傷付く人が別にいるのに、などという、権利を奪われるわけではないけど、違和感や不快感を覚える人がいる。
そのようなかたちでの、弱者として主張しなければいけないときではない部分の自己決定も確かにあり、それがグラデーションのように生殖の自己決定でも起きている。弱者としての自己決定権と、自由を追求する自己決定権がつながっている。それは女性の体に多く起きていて、「女性の自己決定」というかたちでくくられているので、そのへんが誤解も含めて、女性の自己決定に対するいろいろなまなざしを呼び起こしているのかなと思います。
司会:では、時間も来ておりますので、これで講演会を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手)