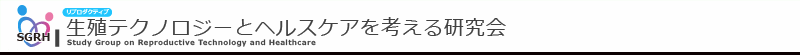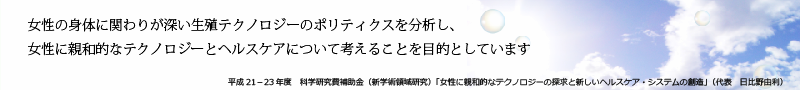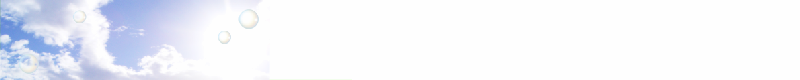出口顯(島根大学・法文学部/文化人類学)
「養父母になった国際養子たち:スカンジナビアの国際養子縁組におけるアイデンティティと親子関係」

ただいまご紹介にあずかりました、島根大学の出口と申します。よろしくお願いします。私の話は、国境を越えた後のお話になると思います。「養父母になった国際養子たち」について、特に北欧のスウェーデン、デンマークで、私自身が調査した事例をもとにお話ししたいと思います。
2001年から、毎年夏に北欧で、埼玉医科大学の石原先生と一緒に調査をしてきました。生殖医療の法的規制や社会的対応、さらには産婦人科医の見解について北欧の事例が我が国ではほとんど知られていなかったので調査をスタートさせました。
北欧では、不妊治療の代替策として国際養子縁組が行われています。実際に、病院やクリニックで、不妊治療の専門家から、患者さんたちに対して、子どもをもつためには、不妊治療だけではなく国際養子縁組という選択肢もあることを早くから提示されているわけです。そこから、私自身の研究は国際養子にスライドして行きました。単純に、英語で不妊治療のテクニカルタームがなかなか聞き取りにくかったこともあります。
まず、国際養子縁組についてお話ししておきます。外国から乳幼児を養子にもらうことです。日本のような婿養子をもらうということではありません。もらわれた養子は、法律上は出生国とのつながりが断ち切られてしまいます。つまり、この場合は二重国籍ということはありません。韓国からスウェーデンに養子にやってきたら、彼や彼女は完全にスウェーデン市民となり、韓国人国籍を一切持たないことになります。
北欧で、国際養子縁組というと、異人種間養子縁組である場合が圧倒的に多いのです。「人種」という言葉は、科学的根拠がある概念ではないのですが、取りあえず今この言葉を使っておくと、異人種間養子縁組である場合が圧倒的に多い。親が白人であるのに対して、アジア系、アフリカ系、ラテンアメリカ系の子どもとなります。
こういう国際養子縁組がスタートしたのは、スカンジナビアでは1960年代後半からです。この背景には、スウェーデン、デンマーク、ノルウェーで、国内養子に出される子どもの数が著しく減少した背景があります。スウェーデンの場合、1998年に国内で養子に出された子どもの数は年間47人でした。この47人は、最初に里子に出されていて養子縁組に移った事例も含めてなので、里子に出された経験も持たずに最初から養子という場合は、だいたい年間20人から30人以下という数字にとどまっています。
スウェーデン、デンマークで、国際養子縁組がスタートした1960年代後半は、ベトナム戦争が真っ盛りのころです。そういうベトナム戦争で孤児になった子ども、それより少し前は朝鮮半島で孤児になった子どもの窮状が、マスメディアを通じて、あるいは実際にそこへ人道支援に行ったスカンジナビアの医師や看護師たちから伝えられました。そういう戦災孤児を救おうという人道的な立場から国際養子縁組がスタートしたわけです。ですから、当初は、既に実子がいる人でも、外国から養子をもらうということが行われていました。現在は、先ほども言いましたように、圧倒的に不妊治療の代替策で行われています。これは、治療の早い段階から、医師から話をされるわけです。
コペンハーゲンのある病院の産婦人科で実際に不妊治療に携わっている医師の研究室には、韓国人女性の写真が飾ってありますが、彼は韓国から養女をもらっています。彼には、妻との間に実子がいました。その後に妻が病気で不妊になったために、韓国から養女をもらいました。
なぜ養女をもらったのか、日本的な感覚で私は聞いてしまいました。1人もう自分の子どもがいるからいいのではないかというニュアンスを込めて伝えたのでしょう。割と厳しい口調で、「私たちは、ほかに選択肢がなかった」と言われました。スカンジナビアの国では、子どもが複数いるのが望ましいという考え方が一般的です。1人というのはまず考えられない、子どもは2人もしくは3人いるべきだという考え方です。親が亡くなったときに支えあうのはきょうだいなのだということで、2人ないし3人以上もらうそうです。そういうことで、もう人道的観点からの国際養子は少なくなっていますが、実子がある人でも、その後妻が病気で不妊になったら国際養子をもらうことは、今でも割と行われています。
先ほどの柘植先生の、生殖ツーリズムの北と南の格差という問題とも関係しますが、ここで簡単に、国際養子主要受け入れ国とその実数をご紹介しておきたいと思います。国際養子に関してはご存じの方も多いと思いますが、1993年にハーグ協定というものが作られ、ハーグ条約が設けられています。国際養子をしようとする場合には、それに署名することの決まりができています。ちなみに日本は、協定に署名も、それに基づいた法律もないし、統計データも信頼すべきものをどこで見ればいいのか、まるで分からないということです。イギリスのピーター・セルマンという教授がずっとこういうデータを作っているのですが、日本は含まれていません。
国際養子縁組の数がもっとも多かった年が2004年です。数の上ではアメリカ合衆国が一番多くて2万2,884人、次いでスペイン、フランス、イタリア、カナダと続きます。スカンジナビア三国の場合は、1,109人、706人、528人と、絶対数は少ないですが、人口10万人に対する国際養子の割合では、ノルウェーが15.4%で一番高いわけです。1998年の段階ではパーセンテージは低かったスペインが、21世紀に入ってから世界第2位や3位になるが多くなってきている。第3位がスウェーデン、デンマークです。養子の割合で行くと、ノルウェー、スウェーデン、デンマークと、スカンジナビア三国が上位を占めるわけです。これはどういうことかと言うと、街を普通に歩いていると、白人の親がアジア・アフリカ系の子ども手を引いているという姿をよく見られるということです。
今日の話と直接関係しませんが、アイルランドが、やはり21世紀になってから割合の上では数が増えて、どちらかと言うと例外的な国になりました。1970年ぐらいまで、あるいはもう少し後まで、実は国際養子の拠出国でした。ところが、1990年頃から旧社会主義国の政権が倒れて、東欧で貧困から孤児になる子どもが増えていることが伝わると、そのころから経済的な発展が著しくなったアイルランドでは、国際養子の拠出国から受け入れ国に転換していきます。そのように、拠出国もしていたし、受け入れ国も高い割合でしている例外的な国がアイルランドになります。
話を戻します。次に、スウェーデンではどこから国際養子として子どもがもらわれてくるのかです。あくまでも上位に限ってのことですが、1990年代以降、国際養子の拠出国として世界第1位に台頭したのは中国です。人口が多いから捨てられるというか、そういう子どもが圧倒的に多いのです。韓国も高く、朝鮮戦争以降、外国に養子を出す国として、ずっと上位1位を占めてきていました。
1988年にソウルオリンピックが開かれるとき、韓国は自分たちで面倒をみ切れない子どもを外国に売っているということで西側諸国から非難が出て、国内養子の実践を言われるようになってきました。それ以降、国内養子の数を増やそうとしているのですが、韓国はなかなかうまくいきません。21世紀になり、もう一度そういう取り組みに乗り出し、功を奏していますが、それでも国内養子拠出国のトップ5からトップ10ぐらいには必ず顔を出しているのが韓国です。ほかにコロンビア、エチオピア、ロシアという国々が上位拠出国になっています。
簡単に言うと、経済格差の大きいインドや中国のような貧困層、エチオピアのように、やはり貧困であり、長らく内戦が続いていた国、コロンビアのように、カトリックで貧困層が子どもを中絶することが認められないような場合、社会主義政権崩壊後の経済困難があったロシアをはじめとする東欧などの国が、国際養子拠出国になっています。
韓国の場合、今では貧困国とは言えませんが、父系理念のとても強い国です。女性がシングルで産んだ子どもは族譜(一族の系譜)の中に入れられない、そういう子どもは社会的に存在しない、言ってみれば、文化的な理念から養子に出されるという背景があります。
1990年以降になると、養父母が子どもを引き取りに拠出国に行きます。そのときに、例えば韓国の土産物をいろいろ買ってきて、リビングに飾っておきます。これはヨテボリにすむ養母と養子の写真ですが、血のつながりは全然ないけれども、笑顔が本当にそっくりです。このとき、少年は15歳でしたが、もう母親の身長を追い越して180センチを超えるぐらいだと思います。この家庭にも、韓国のミニ国旗が飾られています。
このように、養父母が子どもの生まれた出生国へ子どもを引き取りに行き、いかにも韓国の何かを象徴するようなものを買ってきて飾っておき、子どもに触れさせるようにする背景には、「ダブルアイデンティティー」という考え方があります。1960年代から1970年代にかけては、養子は100%スウェーデン人であると考えられてきました。ところが1990年代から、養子が持っているパスポートはあくまでもスウェーデンだけのものだけど、生まれた国についての誇りも持たせたい、出生国の一員でもあるという考えを持たせたい、スウェーデン人であるけれども、同時に韓国人でもある自分のルーツに誇りを持つようにと、生まれた国の文化に触れさせます。国旗、本、美術品、音楽CDを買い与えて、あるいはその国のエスニック料理を作って食べさせるようなことをして、生まれた国の一員でもある誇りを持たせようというダブルアイデンティティーという考えが一般的になってきています。
しかし、このダブルアイデンティティーにこだわるのは誰かという問題が実はあります。先ほどの家族でも、この少年の上にお姉さんが韓国から、弟が1人韓国から、もちろん血のつながりはないけれども、彼女たち夫婦にもらわれてきています。親は、子どもを引き取りに行くとき、最初の長女、3番目の場合は長女と彼を連れて、韓国へ子どもを引き取りに行きます。常日頃、韓国の話題を持ち出します。例えば、夏休みに外国旅行をしようというとき、親は韓国へ行こうと言うわけですが、子どもはいい加減韓国の話ばかり聞かされてうんざりだから、行ったことのないアメリカのほうへ行きたいとなります。むしろ、親のほうが出生国とのつながりにこだわっているところがあります。
養子あっせん機関が組織する出生国ツアーというものがあります。「マザーランドツアー」と英語で言ったりもします。スウェーデン語での表現では「帰りの旅」です。チリから養子をもらった養父母が、子どもはそのマザーランドツアーに行かなかったけれど、チリのおかげで私たちは親になれたからと言って、そのツアーに参加したことがあります。
ダブルアイデンティティーということが言われますが、多くの子どもは、自分は100%スウェーデン人だと考えています。もちろん、外見は白人のスウェーデン人と違うけれど、その場合は「ダブル」と言うよりも、むしろ「エクストラ」なものであり、周りの友人が持っていない、何か特別なものを持っているという感覚に近いのです。
ダブルアイデンティティーは、ある意味でオリエンタリズム的なアイデンティティーとも言えるわけです。国旗や音楽、絵画をリビングに飾って触れさせることが、単純に2番目のアイデンティティーにつながるのかという問題は、あまり親たちにも養子あっせん機関にも考えられていないようです。言ってみれば、子どもが東京で捨てられたにもかかわらず、京都で買った土産物か何か、金閣寺の写真を家に置くようなものです。それで本当に日本人としてのアイデンティティーを、子どもに与えることになるのかというような問題がここには潜んでいます。
次の写真です。この家族は、先ほどの石原先生の『生殖医療と家族のかたち』(平凡社新書)の冒頭に紹介されていますが、ご夫婦はフィンランド出身で、スウェーデンで生活しています。子どもたち2人はコロンビアからもらわれてきて、スウェーデンの市民権を持っています。ご主人は、実はフィンランドで国内養子に出された人だったのです。夫はフィンランドでの国内養子、子どもたちは養子で、それを考えると、「生物学的な親の下で生まれ育ったのは、この家族の中では私だけだから、この家では私のほうがマイノリティーだ」ということを奥さんは言います。このように血のつながりがすべてではないと考える人たちも多々出てきています。
半世紀の歴史があるということは、1960年代の終わりから1970年代の初めに養子としてもらわれてきた人は、当然成人しています。そうなると、かつて国際養子だった人が、不妊などの理由で、今度は国際養子の養父母になる場合もあるのではないか。そういう場合、その人たちは自分と同じ出生国、自分と同じ外見の子どもを養子として迎えるのか、そういうことにまったくこだわらないのか、調査を進めていくうちに気になりました。その事例をこれからお話しします。2007年から調査を始めましたが、なかなかそういう人たちに出会えなくて、昨年までの段階で話を聞けたのは5組の方たちでした。
まず、1973年韓国生まれの男性の事例です。生後16カ月でスウェーデンに養子としてもらわれてきました。彼にはエクアドル出身の妹がいます。つまり、彼の養父母は2人の子どもをもらったわけです。この当時は、親は子どもを引き取りに出生国には出掛けなくて、エスコート役が子どもを連れてきて、親は空港で子どもを引き取ることが、この当時は一般的でした。
韓国生まれのこの男性は、2005年にスウェーデン人女性と結婚します。妻が不妊で体外受精を試みたのですが、奥さんが年上で38歳でした。体外受精の年齢制限が近づいていて、もう何回もすることができなくなったことから国際養子を選択しました。「自分が養子であったから、養子をもらうことは極めて自然な考えだった」と、彼は話していました。
国際養子をしようと思っても、ソーシャルワーカーのホームスタディと称されるものがあったり、あっせん機関を通じて書類を送ったりして、結構手続きに時間がかかります。この人の場合は、養子をもらおうと決めてから実際に養子が来るまで2年弱かかったのですが、2007年に中国から養女をもらいました。アジア系という、自分と外見が同じことが中国から養女をもらう決め手ではなく、コストがほかの国と比べて安かった、その当時は待機時間が割と短かったという、実際的な理由で中国を選択したのだそうです。
彼は、自分が韓国から来たのに、なぜ韓国から養子をもらわないのかという質問を、周りからしばしばされたそうです。この人は、韓国に一度も行ったことがなく、出生国を訪ねたことがありません。高校生のときにアメリカに留学したことはあると言っていましたが、韓国に行ったことはありません。なぜ韓国から養子をもらわないのかは、なぜ生まれた国の韓国に行きたいと思わないのかという質問と同じようなことに感じられる。自分は特別に韓国に行きたいと思っているわけでもないし、たまたま生まれて、でもすぐに警察の前に捨てられていて、生後16カ月でもらわれてきたから韓国のことなど何も覚えていないのに、なぜことさら韓国とのつながりを周りが持たそうとするのか、すごく違和感がある。韓国から来たから韓国から養子をもらいたいとか、韓国と同じ東アジアの中国からもらいたいと思ったわけではないと話していました。
2番目の例は女性です。彼女も韓国からデンマークに養子にもらわれて、彼女自身も韓国から養子をもらいました。彼女は1966年に韓国で生まれて、1967年にデンマークへ養女にやってきました。デンマークの最初の国際養子の一人でした。今、北欧に数多くあるホテルのマネージャーをしていますが、2000年にノルウェー人の夫と出会い、2004年に結婚します。この場合の結婚は正式に結婚することで、それまでは事実婚が続いていました。彼女自身が糖尿病を患っていることがあり、実子を持つことをあきらめて、2007年に韓国から男の子を養子にもらいました。
彼女は、生まれたときから割と韓国とのつながりがあり、それで韓国との養子縁組を選択しました。彼女の両親の雇い主が、実は実業家で韓国とのパイプが強く、その雇い主が韓国に行ったときに、子どもがいない彼女の両親のために、韓国で彼女を見つけてくれて養子縁組の手続きをして、両親のための養子として連れてきてくれました。その両親の雇い主の娘さんも、子どもができなかったので韓国人養子をもらっています。合計4回、学生のころや働くようになってから韓国旅行をしていて、韓国に里親制度を知るようになります。これは大変良い仕組みだと思うようになり、韓国から養子をもらおうと決めたわけです。
彼女自身が養女になったとき、親は彼女を引き取りに韓国に行ったわけではなく、コペンハーゲンの空港で彼女を出迎えているわけです。そこで彼女の親は、彼女の推定の誕生日のほかに、彼女がデンマークにやってきたその日を「ホームカミングディ」と称して、誕生日と同じようにお祝いをしました。彼女もこれを踏襲して、息子がやってきたとき、息子と最初に会った日をホームカミングディとして祝うようになったそうです。だから、生まれ以上に、親子が出会った日を家族の記念日として祝うようになっています。今、アメリカの養父母たちも同じようなことをやっていて、「ファミリーディ」と言っています。
彼女自身は、周りと外見が違うことを悩んだことはなく、ずっと自分をデンマーク人として自己規定してきました。韓国へ4回旅行したわけですが、特に生物学的な母親を探そうと思ったことはなかったそうです。韓国を選んだのも、最初に言ったように、韓国へ行き、韓国の里親制度のことも知っていたし、韓国から養子をもらった人が身近にいて、韓国文化が自分の周りにあふれていたから、養子をもらうとしたら韓国からということが極めて自然だと思えたそうです。自分が韓国生まれだから、韓国の出自というか、生物学的な特徴を大事にしたいから、養子も自分と外見が同じ韓国の子どもをもらおうという考えではないと話してくれました。
この女性に、去年の12月にもう一度会ったのですが、国際養子であることについて、自分の体験と息子の行動を比較して、あれこれ考えてきたことを話してくださいました。養子には、捨てられたという思い、それから捨てられるかもしれない恐れが、言ってみれば養子の一部として絶えず傍らにあります。例えば、養父母が少し自分から離れようものなら、母親のスカートのすそを引っ張る、養父母がどこかに旅行に出掛けようとするときには、スーツケースの上に乗って行かせないようにするような行動があります。その一方で、無意識に生き残るためにポジティブになるから、例えば、積極的にデンマークを覚えようとする、そういうところがあるのではないかと話してくださいました。
次は1975年アフリカのリベリア生まれの女性です。1976年にスウェーデンに養子にもらわれてきました。2歳下の妹はインドから養子にきました。彼女が、先ほど紹介した人たちとこれから紹介する人たちと大きく違うのは、生物学的な両親と成人してから会っていることです。1977年の22歳のとき、アフリカからアメリカに移った生みの母親から手紙をもらいました。それは、彼女にとってはとてもショックで、気持ちの整理がつかなくて、会うのに3年ぐらいの時間がかかりました。会っても、本当の母親と娘にはなれないと思ったのだそうです。
生みの母親とスウェーデンにいる母親、2人の母親と父親がいるとは思わないかと聞いてみましたが、「自分には母親は1人しかいない、スウェーデンで私を育ててくれた人だ」と言いました。先ほどの、柘植さんの卵子提供者の意見にあったようなことと極めて同じような考え方が、生まれてきた側、育てられた側でもそういう考えを持っています。
日本語で言う「おかあちゃん」という感覚なのでしょうが、スウェーデン語で「マンマ」と言います。アメリカにいて、たまにスウェーデンに来る生母に対しては「ママ」とは言うけれども、決してスウェーデン語の「マンマ」を使うことはなく、「マンマ」という呼称を使うのは、スウェーデン人の養母に対してだけだと言います。
彼女は体外受精を4回試みますが、その都度妊娠・流産を繰り返し、それで国際養子をもらおうと決心しました。リベリアではなくて南アフリカから2人の子どもをもらいました。そのあとで彼女と夫との間に実子が生まれます。実子が生まれてよかったと思うかを聞いてみたら、「養子も実子も、どちらも自分にとっては本当の子どもだ。自分の生物学的な子どもができて幸せだろうと周りから言われるけど、なぜそういう質問をされるのか分からない」そうです。あえて特別な子どもを選べと言われたら、むしろ最初の子であり、この子が来たから、自分たちは親になれたからということです。ずっと子どもが欲しいと思っていたから、彼が来てから親になれたから、強いて言えばその子が特別だということになります。なぜ彼女夫婦が南アフリカから養子をもらったかと言うと、子どものいろいろなDNAの診断やケアが割としっかりしているからということが第一理由だったと言っています。
次は極めて珍しい例ですが、ご主人が韓国からの国際養子、奥さんがエクアドルからの国際養女で夫婦になり、子どもがベトナムからもらわれてきた例です。夫は1977年に韓国で生まれて、生後6か月でスウェーデンに来ました。ロンドン留学中に韓国人のガールフレンドができたので、その彼女を訪ねに韓国に旅行に行ったのですが、外見は自分と同じでも仕草がまったく違うことで、韓国人と違うということ、自分はスウェーデン人だということを実感してきました。その旅行の体験をブログにつづったときに、そのブログを読んだエクアドル出身の奥さんがコンタクトしてきて、奥さんと実際に会うようになり結婚しました。
奥さんは1975年にエクアドルで生まれ、生後2か月半でスウェーデンに来ています。チリ出身の弟がいます。赤ん坊はどこから来るのかを言われたとき、あるいは幼稚園や小学校で話しているとき、「コウノトリが来た」や「おなかから生まれた」ではなく、「飛行機で来た」ということを、周りに強く言っていたそうです。彼女は養父母への愛着が強く、親のほうが、生まれた国のエクアドルに行ってみようかと言うのですが、「絶対に行きたくない」と、ずっと拒み続けてきたのだそうです。つまり、エクアドルに連れていかれたら、そこで実の親戚たちが、養父母のもとから私を引き離してさらってしまうのではないか、それが怖くて一度もエクアドルには行っていないと言っていました。
養父母との結び付きが強かったので、ずっと子どもができないときも、不妊治療を受けずに養子縁組を選択しました。つまり、養父母が養子縁組によって子どもを持ったから、その養父母と同じ体験をしたかったというわけです。
どこの国からもらうかということで、妻が南米、夫がアジア、住んでいるところがスウェーデンです。アフリカから子どもをもらってもいいけど、それでは国連みたいで、それはどうかということでエクアドルに落ち着いたのだそうです。しかし、なかなかエクアドルから返事が来なかったので、国際養子縁組について、2007年までスウェーデンと良好な関係を保っていたベトナムに変更して手続きをしようとしていたところ、障害を抱えた子どもをもらってくれるかとベトナムから先に連絡が来て、すぐに応じました。別に病気を抱えていても関係ないと言っていました。2007年10月にベトナムに引き取りに行きました。それがこの子で、障害を持っていても、単に弱視であっただけです。
これは2009年の写真ですが、奥さんは太っているのではなくて、このとき妊娠していました。2009年12月に女の子が生まれています。生まれても、別に養子も実子も違いはないということです。クリスマスカードがメールで送られて、写真を見てみると父親にそっくりです。
最後の例です。エチオピア生まれの男性で、エチオピアから養子をもらった人です。今まで話してきた中で、彼だけが外見が重要だと言いました。この男性は、生後14か月でスウェーデンにもらわれてきています。この当時の例として、養父母には既に実子がいました。彼の後にも息子が生まれています。家族の中で自分一人だけ色が黒い、周りと違うという感覚があったけれども、家族の中で阻害されたり孤立を味わうことはなく、きょうだいも養父母も大切にしてくれました。やはり父親と自分の色が違うことは気にはなっていたけれど、「両親は、私が欲しかったからもらった」とポジティブに考えるようにしたそうです。
22歳のとき、大学のソーシャルワークのフィールドワークでエチオピアに訪問して、エチオピアを気に入るようになります。その後、エチオピア・エリトリア協会という、2つの国からスウェーデンに養子にもらわれてきた子どもたちの協会の会長になり、実の親を探したいという人たちの手助けをする活動をしています。
2005年にスウェーデン人の妻と結婚しますが、彼女のほうがずっと年上で、もう既に成人した子どもがいました。彼女は新たに妊娠して実子を欲しいとは思わないので、では養子をもらうと、エチオピアから養子をもらうことにしました。この男性は、自分は85%スウェーデン人だけど、15%はエチオピア人であり、やはり容貌はアイデンティティーのどうしても欠かせない一部だと言います。養子をもらうことにしたとき、エチオピアから養子をもらえば、その子が父親と外見が違うことを悩まずに済むだろう、自分が父親と外見が違うことを気にしていた思いを子どもにさせないために、エチオピアから子どもをもらうことにしたと話していました。
最後のまとめです。このように養子ごとに考え方が違うわけです。多くは自分と外見が同じ子どもが欲しい、自分と同じ国から欲しいとは思っていないけれども、すべてがそうだとは言い切れないのです。「血は水よりも濃い」とは言えないけれど、どこかでいつも血というものあるいは遺伝子といったものがいつも傍らにあります。5番の男性の場合は、血というか外見というか、自分の生物学的な特徴がまったく問題にならないと考えているわけではありません。
4番の女性の場合は、息子の行動と自分の行動の類似点を見つけます。捨てられた思いがする、親がどこか行こうとすると絶えず付いていくなど、そういう息子の行動と自分の行動の類似点を、国際養子だからということに根拠を求めようとします。普通の親子であれば、それは血のつながりに求めるところですが、国際養子の親子の場合は血のつながりに根拠を求めることができないから、国際養子であることに根拠を求めます。
普通だったら血のつながりで説明するようなところを、それが使えないから国際養子を代わりに持ってきます。血のつながりで親子の行動の類似を説明するものがまずあり、それを基に行動の類似点を国際養子で説明しようとするところがあります。「血は水よりも濃い」とは言えないけれど、さりとて血を無視できないということが、国際養子の在り方の特徴かなと思います。
2001年から、毎年夏に北欧で、埼玉医科大学の石原先生と一緒に調査をしてきました。生殖医療の法的規制や社会的対応、さらには産婦人科医の見解について北欧の事例が我が国ではほとんど知られていなかったので調査をスタートさせました。
北欧では、不妊治療の代替策として国際養子縁組が行われています。実際に、病院やクリニックで、不妊治療の専門家から、患者さんたちに対して、子どもをもつためには、不妊治療だけではなく国際養子縁組という選択肢もあることを早くから提示されているわけです。そこから、私自身の研究は国際養子にスライドして行きました。単純に、英語で不妊治療のテクニカルタームがなかなか聞き取りにくかったこともあります。
まず、国際養子縁組についてお話ししておきます。外国から乳幼児を養子にもらうことです。日本のような婿養子をもらうということではありません。もらわれた養子は、法律上は出生国とのつながりが断ち切られてしまいます。つまり、この場合は二重国籍ということはありません。韓国からスウェーデンに養子にやってきたら、彼や彼女は完全にスウェーデン市民となり、韓国人国籍を一切持たないことになります。
北欧で、国際養子縁組というと、異人種間養子縁組である場合が圧倒的に多いのです。「人種」という言葉は、科学的根拠がある概念ではないのですが、取りあえず今この言葉を使っておくと、異人種間養子縁組である場合が圧倒的に多い。親が白人であるのに対して、アジア系、アフリカ系、ラテンアメリカ系の子どもとなります。
こういう国際養子縁組がスタートしたのは、スカンジナビアでは1960年代後半からです。この背景には、スウェーデン、デンマーク、ノルウェーで、国内養子に出される子どもの数が著しく減少した背景があります。スウェーデンの場合、1998年に国内で養子に出された子どもの数は年間47人でした。この47人は、最初に里子に出されていて養子縁組に移った事例も含めてなので、里子に出された経験も持たずに最初から養子という場合は、だいたい年間20人から30人以下という数字にとどまっています。
スウェーデン、デンマークで、国際養子縁組がスタートした1960年代後半は、ベトナム戦争が真っ盛りのころです。そういうベトナム戦争で孤児になった子ども、それより少し前は朝鮮半島で孤児になった子どもの窮状が、マスメディアを通じて、あるいは実際にそこへ人道支援に行ったスカンジナビアの医師や看護師たちから伝えられました。そういう戦災孤児を救おうという人道的な立場から国際養子縁組がスタートしたわけです。ですから、当初は、既に実子がいる人でも、外国から養子をもらうということが行われていました。現在は、先ほども言いましたように、圧倒的に不妊治療の代替策で行われています。これは、治療の早い段階から、医師から話をされるわけです。
コペンハーゲンのある病院の産婦人科で実際に不妊治療に携わっている医師の研究室には、韓国人女性の写真が飾ってありますが、彼は韓国から養女をもらっています。彼には、妻との間に実子がいました。その後に妻が病気で不妊になったために、韓国から養女をもらいました。
なぜ養女をもらったのか、日本的な感覚で私は聞いてしまいました。1人もう自分の子どもがいるからいいのではないかというニュアンスを込めて伝えたのでしょう。割と厳しい口調で、「私たちは、ほかに選択肢がなかった」と言われました。スカンジナビアの国では、子どもが複数いるのが望ましいという考え方が一般的です。1人というのはまず考えられない、子どもは2人もしくは3人いるべきだという考え方です。親が亡くなったときに支えあうのはきょうだいなのだということで、2人ないし3人以上もらうそうです。そういうことで、もう人道的観点からの国際養子は少なくなっていますが、実子がある人でも、その後妻が病気で不妊になったら国際養子をもらうことは、今でも割と行われています。
先ほどの柘植先生の、生殖ツーリズムの北と南の格差という問題とも関係しますが、ここで簡単に、国際養子主要受け入れ国とその実数をご紹介しておきたいと思います。国際養子に関してはご存じの方も多いと思いますが、1993年にハーグ協定というものが作られ、ハーグ条約が設けられています。国際養子をしようとする場合には、それに署名することの決まりができています。ちなみに日本は、協定に署名も、それに基づいた法律もないし、統計データも信頼すべきものをどこで見ればいいのか、まるで分からないということです。イギリスのピーター・セルマンという教授がずっとこういうデータを作っているのですが、日本は含まれていません。
国際養子縁組の数がもっとも多かった年が2004年です。数の上ではアメリカ合衆国が一番多くて2万2,884人、次いでスペイン、フランス、イタリア、カナダと続きます。スカンジナビア三国の場合は、1,109人、706人、528人と、絶対数は少ないですが、人口10万人に対する国際養子の割合では、ノルウェーが15.4%で一番高いわけです。1998年の段階ではパーセンテージは低かったスペインが、21世紀に入ってから世界第2位や3位になるが多くなってきている。第3位がスウェーデン、デンマークです。養子の割合で行くと、ノルウェー、スウェーデン、デンマークと、スカンジナビア三国が上位を占めるわけです。これはどういうことかと言うと、街を普通に歩いていると、白人の親がアジア・アフリカ系の子ども手を引いているという姿をよく見られるということです。
今日の話と直接関係しませんが、アイルランドが、やはり21世紀になってから割合の上では数が増えて、どちらかと言うと例外的な国になりました。1970年ぐらいまで、あるいはもう少し後まで、実は国際養子の拠出国でした。ところが、1990年頃から旧社会主義国の政権が倒れて、東欧で貧困から孤児になる子どもが増えていることが伝わると、そのころから経済的な発展が著しくなったアイルランドでは、国際養子の拠出国から受け入れ国に転換していきます。そのように、拠出国もしていたし、受け入れ国も高い割合でしている例外的な国がアイルランドになります。
話を戻します。次に、スウェーデンではどこから国際養子として子どもがもらわれてくるのかです。あくまでも上位に限ってのことですが、1990年代以降、国際養子の拠出国として世界第1位に台頭したのは中国です。人口が多いから捨てられるというか、そういう子どもが圧倒的に多いのです。韓国も高く、朝鮮戦争以降、外国に養子を出す国として、ずっと上位1位を占めてきていました。
1988年にソウルオリンピックが開かれるとき、韓国は自分たちで面倒をみ切れない子どもを外国に売っているということで西側諸国から非難が出て、国内養子の実践を言われるようになってきました。それ以降、国内養子の数を増やそうとしているのですが、韓国はなかなかうまくいきません。21世紀になり、もう一度そういう取り組みに乗り出し、功を奏していますが、それでも国内養子拠出国のトップ5からトップ10ぐらいには必ず顔を出しているのが韓国です。ほかにコロンビア、エチオピア、ロシアという国々が上位拠出国になっています。
簡単に言うと、経済格差の大きいインドや中国のような貧困層、エチオピアのように、やはり貧困であり、長らく内戦が続いていた国、コロンビアのように、カトリックで貧困層が子どもを中絶することが認められないような場合、社会主義政権崩壊後の経済困難があったロシアをはじめとする東欧などの国が、国際養子拠出国になっています。
韓国の場合、今では貧困国とは言えませんが、父系理念のとても強い国です。女性がシングルで産んだ子どもは族譜(一族の系譜)の中に入れられない、そういう子どもは社会的に存在しない、言ってみれば、文化的な理念から養子に出されるという背景があります。
1990年以降になると、養父母が子どもを引き取りに拠出国に行きます。そのときに、例えば韓国の土産物をいろいろ買ってきて、リビングに飾っておきます。これはヨテボリにすむ養母と養子の写真ですが、血のつながりは全然ないけれども、笑顔が本当にそっくりです。このとき、少年は15歳でしたが、もう母親の身長を追い越して180センチを超えるぐらいだと思います。この家庭にも、韓国のミニ国旗が飾られています。
このように、養父母が子どもの生まれた出生国へ子どもを引き取りに行き、いかにも韓国の何かを象徴するようなものを買ってきて飾っておき、子どもに触れさせるようにする背景には、「ダブルアイデンティティー」という考え方があります。1960年代から1970年代にかけては、養子は100%スウェーデン人であると考えられてきました。ところが1990年代から、養子が持っているパスポートはあくまでもスウェーデンだけのものだけど、生まれた国についての誇りも持たせたい、出生国の一員でもあるという考えを持たせたい、スウェーデン人であるけれども、同時に韓国人でもある自分のルーツに誇りを持つようにと、生まれた国の文化に触れさせます。国旗、本、美術品、音楽CDを買い与えて、あるいはその国のエスニック料理を作って食べさせるようなことをして、生まれた国の一員でもある誇りを持たせようというダブルアイデンティティーという考えが一般的になってきています。
しかし、このダブルアイデンティティーにこだわるのは誰かという問題が実はあります。先ほどの家族でも、この少年の上にお姉さんが韓国から、弟が1人韓国から、もちろん血のつながりはないけれども、彼女たち夫婦にもらわれてきています。親は、子どもを引き取りに行くとき、最初の長女、3番目の場合は長女と彼を連れて、韓国へ子どもを引き取りに行きます。常日頃、韓国の話題を持ち出します。例えば、夏休みに外国旅行をしようというとき、親は韓国へ行こうと言うわけですが、子どもはいい加減韓国の話ばかり聞かされてうんざりだから、行ったことのないアメリカのほうへ行きたいとなります。むしろ、親のほうが出生国とのつながりにこだわっているところがあります。
養子あっせん機関が組織する出生国ツアーというものがあります。「マザーランドツアー」と英語で言ったりもします。スウェーデン語での表現では「帰りの旅」です。チリから養子をもらった養父母が、子どもはそのマザーランドツアーに行かなかったけれど、チリのおかげで私たちは親になれたからと言って、そのツアーに参加したことがあります。
ダブルアイデンティティーということが言われますが、多くの子どもは、自分は100%スウェーデン人だと考えています。もちろん、外見は白人のスウェーデン人と違うけれど、その場合は「ダブル」と言うよりも、むしろ「エクストラ」なものであり、周りの友人が持っていない、何か特別なものを持っているという感覚に近いのです。
ダブルアイデンティティーは、ある意味でオリエンタリズム的なアイデンティティーとも言えるわけです。国旗や音楽、絵画をリビングに飾って触れさせることが、単純に2番目のアイデンティティーにつながるのかという問題は、あまり親たちにも養子あっせん機関にも考えられていないようです。言ってみれば、子どもが東京で捨てられたにもかかわらず、京都で買った土産物か何か、金閣寺の写真を家に置くようなものです。それで本当に日本人としてのアイデンティティーを、子どもに与えることになるのかというような問題がここには潜んでいます。
次の写真です。この家族は、先ほどの石原先生の『生殖医療と家族のかたち』(平凡社新書)の冒頭に紹介されていますが、ご夫婦はフィンランド出身で、スウェーデンで生活しています。子どもたち2人はコロンビアからもらわれてきて、スウェーデンの市民権を持っています。ご主人は、実はフィンランドで国内養子に出された人だったのです。夫はフィンランドでの国内養子、子どもたちは養子で、それを考えると、「生物学的な親の下で生まれ育ったのは、この家族の中では私だけだから、この家では私のほうがマイノリティーだ」ということを奥さんは言います。このように血のつながりがすべてではないと考える人たちも多々出てきています。
半世紀の歴史があるということは、1960年代の終わりから1970年代の初めに養子としてもらわれてきた人は、当然成人しています。そうなると、かつて国際養子だった人が、不妊などの理由で、今度は国際養子の養父母になる場合もあるのではないか。そういう場合、その人たちは自分と同じ出生国、自分と同じ外見の子どもを養子として迎えるのか、そういうことにまったくこだわらないのか、調査を進めていくうちに気になりました。その事例をこれからお話しします。2007年から調査を始めましたが、なかなかそういう人たちに出会えなくて、昨年までの段階で話を聞けたのは5組の方たちでした。
まず、1973年韓国生まれの男性の事例です。生後16カ月でスウェーデンに養子としてもらわれてきました。彼にはエクアドル出身の妹がいます。つまり、彼の養父母は2人の子どもをもらったわけです。この当時は、親は子どもを引き取りに出生国には出掛けなくて、エスコート役が子どもを連れてきて、親は空港で子どもを引き取ることが、この当時は一般的でした。
韓国生まれのこの男性は、2005年にスウェーデン人女性と結婚します。妻が不妊で体外受精を試みたのですが、奥さんが年上で38歳でした。体外受精の年齢制限が近づいていて、もう何回もすることができなくなったことから国際養子を選択しました。「自分が養子であったから、養子をもらうことは極めて自然な考えだった」と、彼は話していました。
国際養子をしようと思っても、ソーシャルワーカーのホームスタディと称されるものがあったり、あっせん機関を通じて書類を送ったりして、結構手続きに時間がかかります。この人の場合は、養子をもらおうと決めてから実際に養子が来るまで2年弱かかったのですが、2007年に中国から養女をもらいました。アジア系という、自分と外見が同じことが中国から養女をもらう決め手ではなく、コストがほかの国と比べて安かった、その当時は待機時間が割と短かったという、実際的な理由で中国を選択したのだそうです。
彼は、自分が韓国から来たのに、なぜ韓国から養子をもらわないのかという質問を、周りからしばしばされたそうです。この人は、韓国に一度も行ったことがなく、出生国を訪ねたことがありません。高校生のときにアメリカに留学したことはあると言っていましたが、韓国に行ったことはありません。なぜ韓国から養子をもらわないのかは、なぜ生まれた国の韓国に行きたいと思わないのかという質問と同じようなことに感じられる。自分は特別に韓国に行きたいと思っているわけでもないし、たまたま生まれて、でもすぐに警察の前に捨てられていて、生後16カ月でもらわれてきたから韓国のことなど何も覚えていないのに、なぜことさら韓国とのつながりを周りが持たそうとするのか、すごく違和感がある。韓国から来たから韓国から養子をもらいたいとか、韓国と同じ東アジアの中国からもらいたいと思ったわけではないと話していました。
2番目の例は女性です。彼女も韓国からデンマークに養子にもらわれて、彼女自身も韓国から養子をもらいました。彼女は1966年に韓国で生まれて、1967年にデンマークへ養女にやってきました。デンマークの最初の国際養子の一人でした。今、北欧に数多くあるホテルのマネージャーをしていますが、2000年にノルウェー人の夫と出会い、2004年に結婚します。この場合の結婚は正式に結婚することで、それまでは事実婚が続いていました。彼女自身が糖尿病を患っていることがあり、実子を持つことをあきらめて、2007年に韓国から男の子を養子にもらいました。
彼女は、生まれたときから割と韓国とのつながりがあり、それで韓国との養子縁組を選択しました。彼女の両親の雇い主が、実は実業家で韓国とのパイプが強く、その雇い主が韓国に行ったときに、子どもがいない彼女の両親のために、韓国で彼女を見つけてくれて養子縁組の手続きをして、両親のための養子として連れてきてくれました。その両親の雇い主の娘さんも、子どもができなかったので韓国人養子をもらっています。合計4回、学生のころや働くようになってから韓国旅行をしていて、韓国に里親制度を知るようになります。これは大変良い仕組みだと思うようになり、韓国から養子をもらおうと決めたわけです。
彼女自身が養女になったとき、親は彼女を引き取りに韓国に行ったわけではなく、コペンハーゲンの空港で彼女を出迎えているわけです。そこで彼女の親は、彼女の推定の誕生日のほかに、彼女がデンマークにやってきたその日を「ホームカミングディ」と称して、誕生日と同じようにお祝いをしました。彼女もこれを踏襲して、息子がやってきたとき、息子と最初に会った日をホームカミングディとして祝うようになったそうです。だから、生まれ以上に、親子が出会った日を家族の記念日として祝うようになっています。今、アメリカの養父母たちも同じようなことをやっていて、「ファミリーディ」と言っています。
彼女自身は、周りと外見が違うことを悩んだことはなく、ずっと自分をデンマーク人として自己規定してきました。韓国へ4回旅行したわけですが、特に生物学的な母親を探そうと思ったことはなかったそうです。韓国を選んだのも、最初に言ったように、韓国へ行き、韓国の里親制度のことも知っていたし、韓国から養子をもらった人が身近にいて、韓国文化が自分の周りにあふれていたから、養子をもらうとしたら韓国からということが極めて自然だと思えたそうです。自分が韓国生まれだから、韓国の出自というか、生物学的な特徴を大事にしたいから、養子も自分と外見が同じ韓国の子どもをもらおうという考えではないと話してくれました。
この女性に、去年の12月にもう一度会ったのですが、国際養子であることについて、自分の体験と息子の行動を比較して、あれこれ考えてきたことを話してくださいました。養子には、捨てられたという思い、それから捨てられるかもしれない恐れが、言ってみれば養子の一部として絶えず傍らにあります。例えば、養父母が少し自分から離れようものなら、母親のスカートのすそを引っ張る、養父母がどこかに旅行に出掛けようとするときには、スーツケースの上に乗って行かせないようにするような行動があります。その一方で、無意識に生き残るためにポジティブになるから、例えば、積極的にデンマークを覚えようとする、そういうところがあるのではないかと話してくださいました。
次は1975年アフリカのリベリア生まれの女性です。1976年にスウェーデンに養子にもらわれてきました。2歳下の妹はインドから養子にきました。彼女が、先ほど紹介した人たちとこれから紹介する人たちと大きく違うのは、生物学的な両親と成人してから会っていることです。1977年の22歳のとき、アフリカからアメリカに移った生みの母親から手紙をもらいました。それは、彼女にとってはとてもショックで、気持ちの整理がつかなくて、会うのに3年ぐらいの時間がかかりました。会っても、本当の母親と娘にはなれないと思ったのだそうです。
生みの母親とスウェーデンにいる母親、2人の母親と父親がいるとは思わないかと聞いてみましたが、「自分には母親は1人しかいない、スウェーデンで私を育ててくれた人だ」と言いました。先ほどの、柘植さんの卵子提供者の意見にあったようなことと極めて同じような考え方が、生まれてきた側、育てられた側でもそういう考えを持っています。
日本語で言う「おかあちゃん」という感覚なのでしょうが、スウェーデン語で「マンマ」と言います。アメリカにいて、たまにスウェーデンに来る生母に対しては「ママ」とは言うけれども、決してスウェーデン語の「マンマ」を使うことはなく、「マンマ」という呼称を使うのは、スウェーデン人の養母に対してだけだと言います。
彼女は体外受精を4回試みますが、その都度妊娠・流産を繰り返し、それで国際養子をもらおうと決心しました。リベリアではなくて南アフリカから2人の子どもをもらいました。そのあとで彼女と夫との間に実子が生まれます。実子が生まれてよかったと思うかを聞いてみたら、「養子も実子も、どちらも自分にとっては本当の子どもだ。自分の生物学的な子どもができて幸せだろうと周りから言われるけど、なぜそういう質問をされるのか分からない」そうです。あえて特別な子どもを選べと言われたら、むしろ最初の子であり、この子が来たから、自分たちは親になれたからということです。ずっと子どもが欲しいと思っていたから、彼が来てから親になれたから、強いて言えばその子が特別だということになります。なぜ彼女夫婦が南アフリカから養子をもらったかと言うと、子どものいろいろなDNAの診断やケアが割としっかりしているからということが第一理由だったと言っています。
次は極めて珍しい例ですが、ご主人が韓国からの国際養子、奥さんがエクアドルからの国際養女で夫婦になり、子どもがベトナムからもらわれてきた例です。夫は1977年に韓国で生まれて、生後6か月でスウェーデンに来ました。ロンドン留学中に韓国人のガールフレンドができたので、その彼女を訪ねに韓国に旅行に行ったのですが、外見は自分と同じでも仕草がまったく違うことで、韓国人と違うということ、自分はスウェーデン人だということを実感してきました。その旅行の体験をブログにつづったときに、そのブログを読んだエクアドル出身の奥さんがコンタクトしてきて、奥さんと実際に会うようになり結婚しました。
奥さんは1975年にエクアドルで生まれ、生後2か月半でスウェーデンに来ています。チリ出身の弟がいます。赤ん坊はどこから来るのかを言われたとき、あるいは幼稚園や小学校で話しているとき、「コウノトリが来た」や「おなかから生まれた」ではなく、「飛行機で来た」ということを、周りに強く言っていたそうです。彼女は養父母への愛着が強く、親のほうが、生まれた国のエクアドルに行ってみようかと言うのですが、「絶対に行きたくない」と、ずっと拒み続けてきたのだそうです。つまり、エクアドルに連れていかれたら、そこで実の親戚たちが、養父母のもとから私を引き離してさらってしまうのではないか、それが怖くて一度もエクアドルには行っていないと言っていました。
養父母との結び付きが強かったので、ずっと子どもができないときも、不妊治療を受けずに養子縁組を選択しました。つまり、養父母が養子縁組によって子どもを持ったから、その養父母と同じ体験をしたかったというわけです。
どこの国からもらうかということで、妻が南米、夫がアジア、住んでいるところがスウェーデンです。アフリカから子どもをもらってもいいけど、それでは国連みたいで、それはどうかということでエクアドルに落ち着いたのだそうです。しかし、なかなかエクアドルから返事が来なかったので、国際養子縁組について、2007年までスウェーデンと良好な関係を保っていたベトナムに変更して手続きをしようとしていたところ、障害を抱えた子どもをもらってくれるかとベトナムから先に連絡が来て、すぐに応じました。別に病気を抱えていても関係ないと言っていました。2007年10月にベトナムに引き取りに行きました。それがこの子で、障害を持っていても、単に弱視であっただけです。
これは2009年の写真ですが、奥さんは太っているのではなくて、このとき妊娠していました。2009年12月に女の子が生まれています。生まれても、別に養子も実子も違いはないということです。クリスマスカードがメールで送られて、写真を見てみると父親にそっくりです。
最後の例です。エチオピア生まれの男性で、エチオピアから養子をもらった人です。今まで話してきた中で、彼だけが外見が重要だと言いました。この男性は、生後14か月でスウェーデンにもらわれてきています。この当時の例として、養父母には既に実子がいました。彼の後にも息子が生まれています。家族の中で自分一人だけ色が黒い、周りと違うという感覚があったけれども、家族の中で阻害されたり孤立を味わうことはなく、きょうだいも養父母も大切にしてくれました。やはり父親と自分の色が違うことは気にはなっていたけれど、「両親は、私が欲しかったからもらった」とポジティブに考えるようにしたそうです。
22歳のとき、大学のソーシャルワークのフィールドワークでエチオピアに訪問して、エチオピアを気に入るようになります。その後、エチオピア・エリトリア協会という、2つの国からスウェーデンに養子にもらわれてきた子どもたちの協会の会長になり、実の親を探したいという人たちの手助けをする活動をしています。
2005年にスウェーデン人の妻と結婚しますが、彼女のほうがずっと年上で、もう既に成人した子どもがいました。彼女は新たに妊娠して実子を欲しいとは思わないので、では養子をもらうと、エチオピアから養子をもらうことにしました。この男性は、自分は85%スウェーデン人だけど、15%はエチオピア人であり、やはり容貌はアイデンティティーのどうしても欠かせない一部だと言います。養子をもらうことにしたとき、エチオピアから養子をもらえば、その子が父親と外見が違うことを悩まずに済むだろう、自分が父親と外見が違うことを気にしていた思いを子どもにさせないために、エチオピアから子どもをもらうことにしたと話していました。
最後のまとめです。このように養子ごとに考え方が違うわけです。多くは自分と外見が同じ子どもが欲しい、自分と同じ国から欲しいとは思っていないけれども、すべてがそうだとは言い切れないのです。「血は水よりも濃い」とは言えないけれど、どこかでいつも血というものあるいは遺伝子といったものがいつも傍らにあります。5番の男性の場合は、血というか外見というか、自分の生物学的な特徴がまったく問題にならないと考えているわけではありません。
4番の女性の場合は、息子の行動と自分の行動の類似点を見つけます。捨てられた思いがする、親がどこか行こうとすると絶えず付いていくなど、そういう息子の行動と自分の行動の類似点を、国際養子だからということに根拠を求めようとします。普通の親子であれば、それは血のつながりに求めるところですが、国際養子の親子の場合は血のつながりに根拠を求めることができないから、国際養子であることに根拠を求めます。
普通だったら血のつながりで説明するようなところを、それが使えないから国際養子を代わりに持ってきます。血のつながりで親子の行動の類似を説明するものがまずあり、それを基に行動の類似点を国際養子で説明しようとするところがあります。「血は水よりも濃い」とは言えないけれど、さりとて血を無視できないということが、国際養子の在り方の特徴かなと思います。