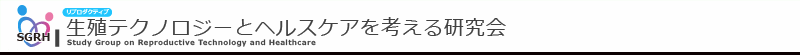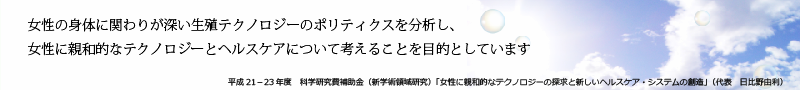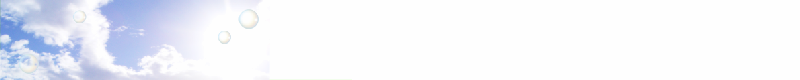秋葉悦子(富山大学経済学部経営法学科教授)
「イタリアとカトリックの生殖補助医療をめぐる倫理問題」
秋葉悦子:
今、自己紹介をしておりまして、お名前だけ存じ上げていて文献をたくさん読ませていただいている先生方がいらっしゃっているので、緊張してうまくお話できるか上がっておりますが、よろしくお願いします。
水野先生がおっしゃっていた自由主義が日本では著しいのですが、私はその自由主義生命倫理とは反対の立場、人格主義生命倫理についてお話させていただきます。
今、皆さんの自己紹介をお聞きしていて、法哲学の方もいらっしゃいますし、法律学の方、社会学の方もいらっしゃいますので、先ほどきちんとお話しなかったのですが、なぜ刑法を専攻していて、生命倫理を研究することになったかを簡単にお話させていただきます。特に、なぜカトリックの生命倫理を研究することになったのかを――もう少し今日の話をご理解いただけるのではないかと思いますので――お話させていただきます。
大学院では刑法を専攻しておりまして、安楽死の問題を修士論文で扱いました。このとき、当時の日本の刑法学は自己決定権と自由主義の立場を最初から土台にしていました。その土台を問うのは法哲学ですが、私は法哲学を勉強せずに刑事法を専攻しましたので、自己決定権の立場からの結論しか出てこないのです。つまり1つの世界観が最初から前提にあって、その上に組み立てていく議論しかできなかったのです。
富山大学に赴任しましてから、かなり自由な研究環境に恵まれましたので、そのとき出した自由主義の結論、つまり、自殺の権利を認めるという結論で本当にいいのかどうかを、法哲学にさかのぼって少し考えてみようと思い、独学で法哲学を勉強し始めました。
出身が上智大学でしたので、キリスト教倫理の専門家が周囲に大勢いました。修士論文の審査のときに教会法担当の神父がおり、専門の立場から自殺についてのレクチャーをしてくれたのです。当時はドイツの法律を調べておりましたが、判例の文言の中に、キリスト教の伝統的な倫理ではこういう考え方をする、ということが普通に書かれています。ドイツの刑法の背景にキリスト教の倫理があること、その意義深さをこのとき実感しました。
日本で今、問題になっている安楽死や、受精卵の実験、生殖補助医療の問題もそうですが、これは倫理の問題です。それについてドイツやフランスやイタリアでは一応倫理学の議論を見て、その後でそれを踏まえて法律学者が議論するという仕組みになっていると思うのですが、日本では、法律の人がいきなりそれを議論しています。では日本の倫理学者はどうしているかと言うと、どうもあまり法律学とは連動していない。
それで、富山に参りまして間もなく半年間の在外研究の機会を与えられましたので、ヨーロッパの法律の土台にあるキリスト教の倫理をしっかりやってみたいと思ったのです。しかし在外研究先に選んだのはアメリカのジョージタウン大学でした。ジョージタウン大学は、ご存知のとおり、自由主義生命倫理学を始めた本拠地です。しかしその研究所に半年間勉強に行くプログラムを組んでくれたのは上智の生命倫理の先生でした。アメリカに行く前にスペインとイタリアにも立ち寄りました。イタリアはちょうど生命倫理の国際会議があったのでその様子を見るだけの予定だったのですが、たまたま訪れたローマの大学、教皇庁立のグレゴリアン大学ということころだったのですが、世界中から生命倫理の研究者が来ており、「カトリックの生命倫理をやりたいならなぜアメリカに行くのか。アメリカの生命倫理は自由主義で、カトリックとは反対の立場だ。私は伝統的な生命倫理を学ぶためにイタリアに来た」というようなことをアメリカの学者に言われて、はじめて事態に気づいたのですが、それを全然知らずに行ったわけです。結局、行き先を変更して、イタリア語もできないのに半年そこにおりました。
要するに、生命倫理という言葉が使われたのはアメリカが最初ですが、生命倫理の実体はヒポクラテスの時代からあり、それを実質的に発展させてきたのがカトリックの倫理神学という分野だということに、そこで気付きました。その後、やり始めてしまったことでもあるし、特にカトリックの立場としてそれをやるとか、そういうことではなくて、日本では全然知られていない――私自身もそうでしたが――欧米には個人主義の生命倫理しかないと思っていたのですが、そのリベラルな生命倫理のカウンターパートが実はヨーロッパにちゃんとあって、――それが今、保守的と言われているカトリックの生命倫理です――それを紹介しようと思ったのです。ところがそれは、実際にはかなり大変な作業でした。まず、自由主義の強い日本で紹介しても、保守的な倫理の話は誰も聞きたくないわけですし、刑法は脱道徳化が戦後のうたい文句になっています。刑法と道徳が日本では分離されておりますので、倫理学をやっても法律に反映するまでに非常な距離があります。
もっとも最近は少し風向きが変わってまいりまして、カトリックの考え方を随分いろいろなところで紹介させていただけるようになりました。聞いてくださるのは、特にほかの宗教の方、それから主に実務に就いている臨床医です。2006年に富山で人工呼吸器の取り外しの事件(射水市民病院事件)が発覚し、自己決定権に基づいた決定がなされようとしましたが、事態は急展開して、そうではない、人格主義的な解決がなされました。それは、自由主義とは別の考え方、倫理主導の伝統的な考え方に基づくものです。先ほど水野先生が医者の本能とおっしゃいましたが、本能というよりも、職業倫理上の使命感かもしれません。
ヒポクラテスの「医の倫理」というものがあります。患者のために自分の技能を使って奉仕するという徳の倫理なのですが、これが個人主義、自由主義、自己決定のカウンターパートです。私はこのカウンターパートの方を調べて紹介してきたのですが、カトリック倫理そのものを提示するといろいろと反発が強いので、イタリアの例を紹介することもしてきました。イタリアはヴァチカンのおひざ元にあり、かなりカトリックの影響が強い。そして、医者の組織が非常に強いところでもあります。イタリアで生命倫理を担っているのは、倫理神学の養成を受けた医者です。私がローマで教えを請うているのは、大体が医学者です。受精卵の問題については、ヒト遺伝学の世界的権威の医学部教授が神父でもあります。ですから、倫理神学の養成があり、医療倫理が実践でできてという人が大体担い手になっているので、非常に科学的であり、しかも伝統倫理にのっとった――カトリック倫理という言い方をしないで、普遍的な自然道徳法などいろいろな言葉が使われていますが――カトリックだけではなくて、普遍的に使えるものにする取り組みを、カトリックでは非常に熱心に追求しています。法哲学の方は、自然法の立場をお取りになると大体接点があるというか、同じ立場に行きつくのだろうと思います。前置きが長くなりました。
人格主義生命倫理というのは、カトリックで使っている名称で、リベラルな自由主義生命倫理の対概念としてつけられたものです。英語ではパーソナリスティック・バイオエシックスです。西洋の生命倫理には2つあって、個人主義と人格主義、これは単純な図式化といってよくお叱りを受けるのですが、こうでもしないと日本で生命倫理と言うと、左側の個人主義がすべてだと思われてしまいます。上智大学はカトリックの大学ですが、そこでも生命倫理の研究をしたいと言ったらアメリカに行くように言われたということが、すべてを如実に物語っています。何年か前の日本生命倫理学会でフランス人の教授がヨーロッパの伝統的な生命倫理について講演したのですが、そのとき著名な日本の倫理学者が、「西洋に別の考え方があるのを知らなかった」ということを公の場で発言されたのは非常に印象的でした。
生命倫理は1960年代にアメリカで始まったとされています。それ以前は生命倫理という言葉自体はありませんでした。しかし、この個人主義生命倫理というのは、実は右側の人格主義生命倫理を否定して、そのアンチテーゼとして生まれてきたものです。つまりゼロからのスタートではなくて、既存の考え方とは反対の立場を取って、伝統を切り捨てる立場を取っているのが個人主義だということです。最高原理は個人の自己決定権ですが、この反対が人間の尊厳です。人格主義は人間の尊厳が最高原理です。
本日はわざわざご説明するまでもないかもしれませんが、バイオエシックスの誕生は、アメリカでちょうど公民権運動が盛んだった時代です。ビートルズの時代、ウーマンリブの時代です。先ほどどなたかリプロダクティブ・ライツの話をなさいましたが、社会的弱者が社会的強者に対して反抗するという、そういう社会革命が公民権運動です。男性に対して女性、黒人に対して白人、学生に対して教師――学生運動です――、そして患者さんが医者に対して、反抗します。
アメリカは人種のるつぼですので、共通の倫理がないと言っては語弊があるかもしれませんが、ピューリタンの倫理もあれば、様々な国からの入植民の倫理もあって、人種も社会的身分もまちまちですので、合衆国としてみんなで一緒にやっていくためには、憲法が最低限のルールになります。合衆国憲法がすべてで、そこを起点にします。
ですから、弱者が強者に対して戦うときに何を目標にするかと言うと、合衆国憲法に勝ち取った権利を書き込むことです。どんな権利を勝ち取るか。女性の中絶権、自分で決める権利、個人情報をコントロールする権利、――加藤尚武先生は「愚行権」という言葉を造られましたが――愚かなことをする権利。いろいろな権利が新しく考え出されました。リプロダクティブ・ライツ、子どもを持つ権利もそうです。男同士であっても、女同士であっても、技術でそれができるのであれば、そういう権利もあっていいわけなので、どんどんそういう権利を主張し、勝ち取っていきます。このようなムーブメントの中で患者の自己決定権というものも出てきました。
ここには合衆国の建国の理念が反映されていて、個人を大事にします。もともとイギリスで国教会の迫害を受けたピューリタンが、新天地を求めてアメリカに脱出してきたわけですので、権威に対して非常に反抗するし、自分たちで新しい国を造るとき、自分たちを迫害したような公権力に頼らない。アメリカでは「小さい政府」ということを言いますけれども、個人が自分のイニシアチブを発揮できることが一番大事ですので、自由の権利が強調されます。同時に、アメリカで一番大事にされるのはプライバシーの権利だと言われます。このプライバシーの権利というのは、個人が公権力から干渉されない権利です。公権力の干渉をできるだけ排除します。アメリカではプライバシー権が憲法上の最高の権利と言われますが、これはヨーロッパの憲法には出てきません。公権力と個人とをこのように対立関係でとらえるのは、アメリカ独特の考え方です。
何が言いたいかと言いますと、ここでわざわざ申し上げるまでもないのですが、アメリカは独特な政治状況の中で、独特の人格概念を醸成してきたということです。ハーバード大学ロースクールの法律学の教授、グレンドンがこのことを指摘しています。ドイツの憲法に描かれている人格は、人と人との関係を大事にする。それは孤立した個人を対象にしていない。それに対してアメリカの人格は、個人のイニシアチブを大事にする。1人にされる権利、1人でいることを許してもらう権利、人から干渉されない権利を求める孤立的な自己、それを対象にしていて、その人格概念に大きな違いがある。これは合衆国憲法の話です。ジョン・ロックの政治思想にそれが描かれているのですが、これをそのまま生命倫理の問題に適用してもいいか、そこには無理があるのではないか、とグレンドンは指摘するのです。
このようなアメリカの独特な人格概念、アメリカの「人格」は、しばしば法的権利主体と同視されます。ですから生まれた後の人を指します。人格という言葉は、もともと法的権利主体を指すだけのことばではないのですが、アメリカの新しい個人主義生命倫理は、人格を最初から法的な権利主体を表す語としてのみとらえ、この法律上の概念である「人格」を倫理でも採用する。個人主義生命倫理の大きな特徴です。
個人主義生命倫理の想定する自己像として、「孤立的自己」と書きましたが、これについて、最近面白い文献を見つけました。東大医学部の名誉教授、大井玄先生が書かれた本の中に「文化心理学」という割合新しい学門分野の紹介があって、その文化心理学によると、世界には2つの自己観、「孤立的自己観」と「関係的自己観」がある。この「関係的自己観」は割合普遍的な考え方で、「孤立的自己観」は、アメリカに特異な考え方なのだそうです。もちろんアメリカ以外でも、移民やニューフロンティアの状況を想起していただきたいのですが、非常に広大な土地に人間がいて、――隣の家まで何キロもあるような――、自分の力で土地を切り開いていくような環境があって、このような自己観の形成が初めて可能になる。日本では北海道の人にこのような自己観の持ち主が多いという調査結果もあるのだそうです。ところが、1人ひとりにこのような広大な空間が与えられていないところでは、長屋やマンションなどに住み、お隣と密接にかかわっていて、親戚も知り合いも身近に大勢いる、そういう閉鎖的な社会では関係的自己観が形成されます。ここでは「孤立した個人」というものはイメージしづらくて、大体、何かを自己決定すると言われても、実際には自分だけで決めていない。周りのことを考えて決める。安楽死の問題についてもそうです。もし自分が何か人に迷惑を掛ける状態になったら死にたい。それは人に迷惑を掛けるから死にたいのであって、アメリカ人は、自分がもう、1人で自立できない、自分1人で決められない、イニシアチブを発揮できない。そのことがつらいから、だから死にたいのだという答えが返ってくるのだそうです。しかし日本人はいつも他者とのかかわりの中で決定をします。そして世界的に見ると、インドもそうだし、アフリカもそうだし、日本人のような反応がむしろ標準的であって、孤立的自己観はごく特殊な地域で見られるにすぎないのだということです。
戦後の日本は、刑法学もそうですが、個人主義が急に入ってきて、今までの関係的自己の持ち主が、孤立的自己――大井先生の言葉では「アトム的な自己」――を確立できないで、いろいろな葛藤があるところから、鬱状態になったり、自殺が増えたり、ひきこもりになったりするのではないかというような感じがするのですが、いずれにしても、個人主義生命倫理も、この孤立的自己像をモデルにして、個人の自己決定権を最重視します。
それに対して人格主義のほうは、存在論に立脚します。存在論においては、個人にとって大事な価値、自己決定、自意識、理性の働きなどではなくて、存在そのものの価値を重視します。自己決定しなくても、自意識がなくても、人間の尊さというものをそれとは違うレベルで見ていくわけです。例えば、自意識の働きがない人に対しても、なんらかのつながりを持てればその人を大事に思うかもしれないし、その人の存在そのものの価値を認めます。つまり、自意識によって、理性によって自分の能力を発揮するなど、そういう考え方でいきますと、何が人間にとってよいことかということを考えますので、功利主義につながりますが、そうではなくて、存在そのものの価値、人間の内在的な価値というものを認めていくと、それが人間にとって利益になるかどうかではなくて、ともかく人間なので大事にしようと、そういう考え方になるわけです。
考え方の基礎を築いたのは、ジョセフ・フレッチャーというプロテスタントの神学者で、大谷いづみ先生が彼を取り扱った本を最近出されています。フレッチャーが1954年に出した『倫理学と医学』という本は、「カトリック以外で医療における倫理問題を取り上げた最初の書籍」といううたい文句になっています。彼はこの中で初めて安楽死を合法化し、正当化します。これが日本にも入ってきて、私が大学院時代に悩んだ、自己決定権による自殺の合法化につながります。日本でも宮野彬という刑法学者が積極的安楽死の合法化を唱えますが、彼もフレッチャーに影響を受けておりましたし、それから「日本安楽死協会」を作った太田典礼もこのフレッチャーの書物からヒントを得ていたのだそうです。
個人主義生命倫理について、スライドに「反宗教的」と書きました。この点については、あとでまた詳しくご説明致しますが、個人主義生命倫理は、要するに伝統的なカトリック倫理ではなく、世俗的な哲学に立脚しているということで、日本の哲学者がこれを組織的に輸入したのです。そして、教育現場にもこれをそのまま持ち込みます。アメリカの大学では大規模な教育プログラムを組んで在外研究者や留学生を受け入れました――私がジョージタウン大学に行こうと思ったのも、この教育プログラムを受講するためでした。そして個人主義生命倫理は日本にもすごい勢いで広がりました。
右側の人格主義のほうはどうかと言うと、先ほども申し上げましたとおり、生命倫理という言葉自体はありませんでしたが、その元になっているのは、伝統的なヒポクラテスの「医の倫理」です。これは紀元前のもので、非常に簡単です。要約すれば2つのことしか書かれていません。ヒポクラテスは、科学的医学を始めた人です。「科学」というのが1つめのキーワードです。もう1つは、「目の前の患者の善」です。科学を大事にします。科学的知識の行使は特殊技能ですので、これを守り、弟子に伝えて発展させます。医者はそういう任務も担うし、もう1つの任務も担うのです。目の前の患者を助けることです。では、科学を発展させるために目の前の患者を犠牲にしていいかと言うと、答えははっきりしていて、常に目の前の患者を助けることが優先されるのです。ですから、「科学」というのがキーワード。もう1つは「目の前の患者の善」。そして「目の前の患者の善」が常に優先します。
あとはこの応用問題というか、この原則を当てはめればよいのです。この「科学」プラス「倫理」、それを個別の問題に当てはめて応用問題を解いていきます。方程式はずっと同じです。イタリアではこのヒポクラテスの「医の倫理」を現代化する取り組みが続けられてきました。イタリアの話が日本の医者になぜ受けるのか。イタリアでの議論は、ヒポクラテスの「医の倫理」を共有している医者には理解しやすいからです。ヒポクラテスの「医の倫理」を継受したのはカトリックだけではありません。ヒンズー教とイスラム教、ユダヤ教にも継受されました。東洋とのつながりも指摘されています。「医は仁術」と言います。仁慈は儒教の最高倫理です。ヒポクラテスの「医の倫理」は東洋の徳の思想ともつながっています。
このように、ヒポクラテスの「医の倫理」自体は宗教とは無関係の世俗的なものだったのですが、ただ、多くの宗教はこれをこぞって継受して発展させました。それを最も組織的に学問体系に構築してきたのが、最近500年くらいの間のカトリック倫理学でした。私が個人主義生命倫理の反対の立場を研究しようと思って、カトリック倫理学を見なければならなかった理由は、ここにあります。ただ、カトリック倫理学は、ヴァチカンがほとんど世俗的な権力を失った現在、その実定法としての展開を見るためには、その影響を受けている国の法律を見ることが必要になります。イタリアの法律は、私の見る限り、生殖補助医療法もそうですが、カトリック倫理に一番忠実な形で展開されているので、イタリアの医療倫理や法律の文献も読まなければならなくなったわけです。
今の話を、時系列というほどではありませんが、一応上から順番に並べると、まずヒポクラテスの「医の倫理」があって、ここから積極的安楽死の禁止、またここには書きませんでしたが、人工妊娠中絶の禁止が導かれます。なぜかと言うと、人を殺すからです。「殺すなかれ」というのが第一の原則ですので、殺さないのです。イスラム、ユダヤ、カトリック、儒教がこれを採用して、16世紀ごろからカトリック医療倫理が体系的な学問として発展します。これを今、個人主義に対抗して人格主義と名付けて、カトリックが熱心に普及活動をしています。1954年にプロテスタント神学者のフレッチャーが――プロテスタントというところが肝心かもしれません、カトリックに反抗する立場です。フレッチャーはアメリカで一番政治的に力のある長老派の牧師です――カトリックでない医療倫理の書を初めて刊行します。積極的安楽死の合法化です。
84年に生命倫理学の体系的な教育機関が2つ創られます。ジョージタウン大学のケネディ研究所と、もう1つはヘイスティングス・センターです。そこで教育を受けた最初の卒業生は、ロバート・ヴィーチですが、彼が84年に書いた論文のタイトルは非常にわかりやすい。「ヒポクラテスの倫理は死んだ」。これが個人主義生命倫理学ですので、両方の立場は相いれない立場です。もっとも、有力な人格主義生命倫理学者はアメリカにもいます。かつてケネディ研究所の所長も務めたペレグリーノは、有名な生命倫理学者であり、医者でもあるのですが、保守的なブッシュ政権の下で大統領生命倫理諮問委員会の委員長を務めました。彼が最近書いたものをこの間翻訳したのですが、その中に、最近の個人主義生命倫理学は「脱宗教的」、つまり単に世俗的であるばかりでなく、「反宗教的」、「宗教敵対的」でさえあるということが書かれています。
以上から申し上げたいことは、この2つの真反対の立場が今、世界にあって、――単純化し過ぎかもしませんが――、この2つの構図を見ながらいろいろな問題を読み解いていくと、対立の根本にあるものが何か、割合わかりやすいのではないかと思って、私は大体この図式に当てはめて、普段ものを考えています。
今日は、代理出産の話ということでご依頼をいただいたのですが、代理出産については、お手元にレジメがあると思いますが、最後のところで生殖補助医療についてお話する中で触れさせていただきます。先に終わりのほうを見ていただいたほうがいいかもしれません。
スライドの31番にイタリアの生殖補助医療法について記しましたが、今日は本当にごく簡単に総論だけしかできないと思います。総論の基本コンセプトを読みます。
「生殖補助医療にかかわるすべての主体の権利を保障する」。先ほどから両親のことは話題に出ておりますが、「すべての主体」は、生まれてくる子どもの権利を含みます。では生まれてくる子どもの権利はいつから保障されるかと言うと、一番初めの受精のときからです。そうすると、体外受精も難しくなるし、今、日本では、iPS細胞から生殖細胞を作って、子どもを作っていいかどうかということが先ごろから議論されているようですが、ここでは、先ほど問題になっていた、卵子を摘出するときの女性のリスクなどは全く生じません。将来、人工孵卵器ができたら問題のありかがいっそう明確になるかもしれませんが、受精のときから子どもの人権を認めるとすると、人はどのように受精されるべきか、どのように生み出されるべきかという問題まで入ってきます。イタリアの生殖補助医療法は、「子どもの権利を一番最初から認める」ことをうたい、「その生命の開始、すなわち受精時から法的主体として保護する」という、これはかなり大胆というか、ある意味で論理必然なのですが、そういう立場を取ります。これは、生命科学技術の進展に対して、生まれてくる子どもの善を優先するという、伝統的な医療倫理に基づいた一つの明確な態度決定を示したものと言うことが出来ます。
32番を見ていただきたいのですが、2009年6月、受精時から人を法的主体とする民法改正案が提出されました。これは、「倫理を法に格上げする」という言い方をイタリアではよくするのですが、アメリカで倫理の議論が法律の議論に還元されてしまったのとは対照的に、イタリアはその逆方向が目指されます。倫理を明確にして、それを法に格上げするということをやっているのです。
このコンセプトにのっとるとどういう結論が導かれるかというと、大体のものは刑事罰で禁止です。胚の商品化、代理出産もそうです。人のクローニング、研究目的のヒト胚の作成と利用です。
フランスではなぜリベラルなのかということを先ほどご質問致しましたが、受精卵がまだ「人」でなければ、人間の尊厳原則に抵触せずに実験に使えるわけなので、そこが一番大事なポイントになります。あとでご説明するとおり、カトリックは科学的事実を重視して、生物学の議論を徹底的に尽くした上で、人の生物学的な始まりは受精時だということを認めます。
子どもが人として生まれてくることのためには、恣意的に作られてはいけないというような論理もそこから出てきます。優生目的の胚の選別と操作、それからハイブリット、キメラの作成、多胎妊娠における減数も駄目です。胚の凍結、破壊も駄目です。余剰胚の作成も駄目、ほとんどのことが禁じられることになります。行政罰で禁止されているのは、第三者の配偶子の使用、インフォームドコンセントをとらなかった場合、不認可の手術を適用した場合等などですが、イタリア生殖補助医療法が一番重視しているのは、子どもの権利です。それも、生きる権利だけではなくて、人格権も保護する。両親から生まれる権利等を保護する。そのような話になっています。
今日お話する内容のポイントは以上のとおりです。代理出産がなぜ駄目かというと、生まれてくる子どもの権利を侵害するからだ、ということなのですが、それをもう少し詳しく見るとどうなのか、前のスライドに戻りたいと思います。
人格主義生命倫理学の基本構造、6番です。科学的事実の承認。ヒポクラテス以来の科学的医学に立脚する立場を貫きますので、まず科学的事実をしっかり確認することです。ヒトの生命は受精時に始まります。「ヒト」とカタカナで書いたのは、生物学上の表記が「ヒト」だからです。まず生物学の議論を尽くします。その次に倫理の議論が来ます。その実質的な内容は「人間の尊厳」原則の確認です。
この「人間の尊厳」原則が何かということについては、もうさまざまな議論があるのですが、できるだけ立ち入らずにすませたいと思います。一言で言えば、それは、「誰でも例外なく人間の尊厳と基本的人権を認められるべきだ」という原則です。なぜ人間に人権があるかというと、尊厳があるからです。人権の前提が尊厳なのですが、先ほど申し上げたヒポクラテスの医の倫理、目の前の患者さん、目の前の人――その始まりの時から――を最大限に尊重する原則、と考えていただいて構わないと思います。両方を合わせると、「受精時から人間の尊厳と人権を例外なく保護しましょう」。これが人格主義生命倫理の基本構造です。
「科学的事実の承認」のあとに記したscienzaは、イタリア語で「科学」の意味です。そして「人間の尊厳原則の確認」のあとに記したcosciencaは、良心という意味です。良心と科学は日本語ではまったく別の言葉なのですが、語源が一緒なのです。つまり、科学はそれだけであるのではなくて、coという接頭詞は、それに伴うという意味ですので、コシエンツァは、シエンツァがあるところに、それに伴ってあるものです。後でまたご説明しますが、人間は肉と霊から出来ています。肉だけではない、目で見えるものの背後に必ずスピリチュアルなものがあります。その目に見えるものと見えないものが一緒になったのが人格です。同じように、科学は目に見えるシエンツァ(scienza)ですが、それが人間の技であるとき、そこには必ず目に見えない次元が入ってきます。スピリチュアルな次元、良心の次元、倫理の次元です。これは自然科学ではありませんので、良心や倫理の問題は自然科学の問題には還元できません。ですから、科学ではできるけれども、それを使ってよいか、どう使うかというのはコシエンツァの問題で、人間が科学をやるときに必ずそれに伴って良心の問題が出てくるという意味です。この良心の中身、ヒポクラテスの目の前の患者優先の態度を言いかえたのが「人間の尊厳」原則だと思っていただければ、大体よろしいのではないかと思います。
カトリックの最近の文献に『いのちの福音』というヨハネ・パウロ2世――前の教皇ですが――の回勅というものがあって、信者あての手紙なのですが、これは信者だけではなくて、全世界の善意の人に向けて書かれたものです。この中に「卵子が受精したときから新たな人の生命が始まる。現代遺伝学はこの不変の事実に貴重な確証を与えた」と書かれています。この箇所は、先ほどのシエンツァ、科学的な事実を記しているだけです。これはただ科学の事実を承認しているだけですが、このことのためにヴァチカンでは多大な精力をつぎ込んでいます。科学アカデミーという1603年にできた組織があるのですが、世界中から招いたノーベル賞受賞者が40人ぐらい含まれています。そういうアカデミーを持っていて、そこで現代科学の最新の事実を厳密に調べるということをヴァチカンはしているのです。こうして現代遺伝学の詳細な議論を踏まえた上で「卵子が受精したときから新たな人の生命が始まる」ということを言っているわけです。
コシエンツァのほうはどうかというと、「人は身体と精神の全体であり統合であるから、身体的に新たに存在し始めた初期胚には、既に精神的霊魂が宿っていると考えられる」と記されています。これは科学ではありません。これはカトリックの信仰なのか、良心の問題なのか、あるいはカトリックもゼロから始まったわけではなくて、その前にプラトンがありますので、プラトンの考え方もこれと同じだと言われていますが、それ以前からある宗教に基づくものなのかもしれません。いずれにしても科学的に解明できない部分ですが、このような人間観に立ちます。要するに、人というのは、身体と精神の全体であり統合である。両方は一緒になっていて、分離できない。でも、両方の次元がある。この人間観が出発点になっています。これを認めないと次に書かれているようなヴィジョンは出てきません。「したがって、人は受精時から人格として扱われるべきであり、また不可侵の生きる権利が認められなければならない」。
この中に日本語に訳すと、「人」という言葉と、それから「人格」という言葉と、「人間」の尊厳という言葉と、「個人」という言い方もあります。日本語では普通、ヒューマン・ビーイング(human being)という語を「人」に、パーソン(person)という語を「人格」に置き換えますが、人間という語は外国語にありませんので、人格と同じでいいのかどうか、いつも翻訳するときとても迷うところです。しかし「人間」というときは大体、その身体と精神の全体であり統合である人格のことを指していると考えられるように思います。一方、「人」という語は、法律用語でもあり、法的な権利主体のことを刑法でも「人」と言いますので、日本でもよく見られる、どこから「人」かという議論は、生物学のシエンツァの議論なのか、それとも倫理のコシエンツァの議論なのか、両者の区別はとても大事な問題です。
ヴァチカンの立場は、まず生物学的な事実を認めます。そして、自然科学ではないところで、人間にはスピリットもあると考えますので、人が物理的に存在すればそこにはスピリットが宿っていると考えて、そのスピリットの部分において人間は尊いと考えます。この考え方はいろいろなところで誤解されていますが、後で「パーソン論」が出てきますので、そこでまたご説明します。
2005年に現在の教皇ベネディクト16世に変わり、カトリックの教えを要約する文書が公表されました。現在の教皇は、前の教皇の時代に教理省という省庁でカトリックの教義を形成する仕事に従事してきた有名な神学者ですが、彼自身が用意したこの文書の中に、「個々人の譲ることのできない生存権は、その受精のときから、市民社会と法律を成り立たせる一つの要素です。国家がすべての人の権利、特に弱者、中でも出生以前の受精卵・胎児の権利の保護のためにその力を行使しないなら、法治国家の基礎そのものが脅かされることになります」(「カトリック教会のカテキズム要約(コンペンディウム)」カトリック中央協議会訳)という文言があります。
ここで主張されていることは、ヨハネ・パウロ2世もそうだったのですが、命の問題や性の問題などについて、よく誤解されるように、カトリック教会は、何か神の領域に人間が手を出してはいけないと命じているなど、よくそのようなことを言われるのですが、そういうことではまったくなくて、「受精卵のときから人権を守らなかったら、平和が守れない」と言っているのです。
ですから、生命倫理を社会倫理の問題と結びつけたところにヨハネ・パウロ2世の功績があった、独自性があったというように、今日では評価されているのですが、その路線を現在の教皇も推し進めているということです。ヴァチカンは今、領土を持っていませんので、国益を追求する必要からも解放され、純粋に世界の平和を追求する立場から、道徳的な指導者として、いろいろなところで政治の問題にも口をはさんでいます。今日のカトリック生命倫理は、単に信者さんに対して正しい性のあり方を説くというようなものではなくて、「弱い人の人権をどう守るかということが世界平和にとって大事なのだ」という、社会正義と結びつけた議論をしているということです。
ヴァチカンの公式見解と書きながら〔スライドに〕欧州議会やドイツの話を書いてすみません。一応色を変えたのですが、お配りしたレジメは白黒ですので全部一律に並んでいます。一緒にすべきではないかもしれませんが、歴史的に並べるとわかりやすいのではないかと思って、今回作ってみました。
1968年にパウロ6世の当時の教皇の回勅、信者あての手紙、これは全世界の人々に向けたものではなく、カトリック教徒のみに向けたものですが、『人間の生命-適正な産児の調整について-』という文書が公表されます。一般に普及した避妊方法を禁止するなど、非常に保守的な内容を含んでいるため、アメリカで新しい生命倫理を構築する運動が起きたきっかけの1つがこの回勅であると言われています。しかしこれ以前にも、哺乳(ほにゅう)類の卵子が発見されるのが1827年なのですが、1864年にピオ9世が受精のときから人であるということを最初に公式に認めた文書を出しているようです。島薗先生が文献の中で引用されているのですが、原典を確認しておりませんので、ここには書きませんでした。その後もピオ12世が、体外受精をしてはいけないということを再三注意している、そういう文献も見られるのですが、この問題についてまとまった文書が公表されたのが、68年のパウロ6世の回勅ということです。
74年に教理省から「中絶に関する宣言」が出されます。この中にも「受精のときから人だ」ということが記されています。そして「中絶は人を殺すことなのでしてはいけない」ということが記されています。87年にやはり同じ教理省から「初期の人間の生命の尊重と生殖の尊厳」という文書が出されます。「生殖の尊厳」というのは聞き慣れない言葉かもしれませんが、カトリック倫理は人間の行為について「尊厳」という言葉をよく使います。後で「労働の尊厳」が出てきます。人間も馬も労働するし、生殖行為もするのですが、人間の行為についてはスピリットの部分が関与しますので、動物の行為とは違う意味合いがあるのです。物理的には同じ行為であっても、そこには別の次元が伴います。
人間の生殖にリプロデュース(reproduce)ではない、プロクリエイト(procreate)という言葉を使うのもこのためです。「生殖の尊厳」を含意する言葉です。教理省が1987年にこの文書を出した理由は、1978年に世界初の体外受精児ルイーズ・ブラウンが誕生したためです。不妊に悩んでいた人々にとっては福音でしたが、ヴァチカンは、体外で生産されるヒト胚にとっては、その後のさまざまな干渉を予測させる脅威的な出来事である、ととらえます。つまり、この時点で、この後、ヒト胚にもたらされる大規模な侵害を懸念していたのです。実際にこの懸念は現在、現実のものとなっています。余剰胚を使った実験は日本ではゴーサインですし、体外の受精卵に対しては誰でも容易にアプローチが可能です。研究用に体外受精卵を作成することさえ許されています。
ですから、教理省のこの文書、あるいはパウロ6世の回勅もそうですが、ここで考えられていることは、人間の受精卵は、通常であれば、お母さんのおなかの中で、お母さんに守られた状態で生を受けます――もちろんお母さんが中絶するということもありうるのですが、これはまた別な事態です。しかし母体外で作成された受精卵は、外からアプローチできる状態で生を受けます。外部の攻撃から身を守るものは何もありません。「容易に危害にさらさる環境で、最も弱い状態の人間を存在させてもいいのか」、そういう問い掛けをするのです。実際に今、一番弱い立場、無防備な立場の者が搾取の道具になっています。それを予見したのが87年の教理省の文書でした。
あとはこの路線が一貫して推し進められるのですが、この考え方に基づいて1989年にヨーロッパ議会で「体内および体外の人工生殖に関する決議」、それから「遺伝子操作の倫理的・法的問題に関する決議」が出されます。体外で受精卵を作ることができれば、これを操作する話はすぐに出てきますので、ヨーロッパ議会でこれへの警戒が示されます。1990年にはドイツで胚保護法が成立します。ドイツの対応が早いのは、人間の尊厳についての歴史的反省があるからです。ドイツはナチスの時代に優生学を推し進めました。これについては後に触れます。
95年にヨハネ・パウロ2世の『いのちの福音』が公表されます。ヨハネ・パウロ2世はこの『いのちの福音』の中で、生命倫理に関する諸問題を網羅的に扱っていますが、特に気にかけていたのが受精卵の問題でした。私が在外研究でイタリアを訪れたのは1995年の秋でした。『いのちの福音』が出されたのは3月でしたが、当時イタリアでは、人の始まりがいつかという議論で持ちきりで、安楽死の研究に来たと言ったら、それはもう解決済みで、今しなければならないのは体外受精卵の問題だ、と言われて、いろいろな研究者からヒト胚に関する文献を紹介されて面食らったことをよく覚えています。
ヨハネ・バウロ2世が生命アカデミーという新しい機関を、1603年に創設された科学アカデミーとは別に新設したのは、将来、現在のような事態、生命科学技術の進展に伴って、着床前診断や代理母、遺伝子操作など、新たな問題が次々と生じてくることを見越して、それに手を打とうと考えたからでした。科学アカデミーだけではなぜ駄目かというと、ここには倫理の問題が入ってくるからです。ヨハネ・バウロ2世は生命アカデミーのほかに、社会科学アカデミーも新設し、社会科学の問題についてはまた別の組織で対処する体制を整えましたが、当初、ヴァチカンが取り組もうと思った一番の課題は、この受精卵の保護の問題でした。
97年にクローン羊ドリーが誕生すると、生命アカデミーは直ちに『クローンに関する考察』という文書を出して、この中で、クローン技術は「生み出されるクローンの尊厳に反する」ということを明確に指摘します。欧州議会がそれを追ってクローンの禁止決議を出します。
ところが翌年、クローン胚からES細胞を作成する研究目的のクローニング――当初、「治療目的のクローニング(セラピューティック・クローニング)」という言葉が使われましたが――、の研究計画が提示されます。クローン胚を作って、そこからES細胞を作ることができるということになりますと、生殖目的のクローンには反対するとしても、拒絶反応のない再生医療の進歩のために、ES細胞を作成するためのクローニングを合法化しようとする動きが生じます。欧州議会は1998年に、生殖目的のクローニングのみを禁止する追加議定書を出します。生命アカデミーのほうでは、2000年に「ES細胞の作成と科学的・治療的使用に関する宣言」を出して、これに対抗する態度を明確に表明します。この文書の大半は、生物学の専門的な議論を扱っています。ヒトの生命の始まり、受精のメカニズムに関する生物学の議論が徹底的に検証されています。ヨーロッパでは当時、分子生物学者、発生学者、ヒト遺伝学者がこの議論の主たる担い手でした。この議論を踏まえて、哲学者や倫理学者が後に参入します。
2003年に生命アカデミーは、もう1つ別の文章を出します。これは当時、国連でヒトクローニングの是非をめぐる議論が紛糾していたのを見て、国連の議論に影響力を及ぼそうと考えたのです。「国際的な議論におけるクローニングの禁止」。これは当時展開されていた議論をひとつひとつ取り上げて、批判検討を加えたものですが、これも科学、倫理、法律の3段階の構成になっていて、それぞれ別の章を設けて議論していくのです。まず生物学的な事実はこう、それをもとにして倫理を考えるとこう、さらにそれをもとにして法律を考えるとこうなる、ということを3つの段階に分けて議論していくのです。
2004年にヴァチカンの国務省――外務省に当たる機関です――が、対外向けに、国連の議論にいっそう影響力を及ぼす目的で、生命アカデミーの文書を踏まえて、もう少し短いコンパクトな文書「ヒトクローン個体産生禁止に関する国際協議に向けて」を作成します。功奏して、2005年に国連でクローン全面禁止宣言が出ますが、条約にはなりませんでした。このような国際的な動向の中で、イタリアでは国連宣言の前年に生殖補助医療に関する法律が成立しますが、これは先ほど申し上げたように、クローンを全面禁止し、ヒト胚を用いた実験もすべて禁止という厳格な立場を取っています。
2006年に生命アカデミーが「着床前の段階のヒト胚」というパンフレットを出します。これは一般の人向けの平明なもので、ヒト胚に関する科学的事実と法的保護の必要性について記した、広報活動というか、教育活動のためのものです。そして2008年に教理省、これは先ほど言ったヴァチカンの教えを司る、一番権威のある部署なのですが、そこが「人格の尊厳・生命倫理の幾つかの問題について」という文書を公表して、この中で体外受精、それから代理母の問題、生殖医療等の個別の問題についてコメントしています。
ですから、今後、カトリック教会の生命倫理の公式の見解として冒頭に掲げられるべきなのは、今、最後にご紹介した教理省の文書なのですが、これまで述べてきた基本構造は一つも変更されていません。科学と倫理、そして始まりのときから尊厳と人権を守ること、生命権だけではなく他の重要な人権も守ることです。
以後のスライドは、生物学、シエンツァのさらに詳しい説明を書いたものです。簡単にご覧いただければと思います。 これはギルバートの発生生物学の教科書に掲載されている写真です。権威のある生物学の教科書なのですが、この中で人の始まりは――わかりづらいかもしれませんが――上段左が受精前の卵子です。上段中央が人の始まりです。卵子の核が成長して前核を形成します。ここでは卵子のイオン構造が全部変化して、カルシウム波が受精卵全体を覆います。新たな人の個体の発生の時点です。私は見たことがありませんが、この瞬間は、顕微鏡を通して肉眼で見ると、一目でわかるのだそうです。卵子の状態が一遍に変わるのだそうです。卵子のイオン構造が一挙に変わるということは、そこで別の個体が発生するということなのだそうです。先ほどの小門先生のフランスのお話では、医師会が割合好意的だということでしたが、医師たちは普段こういうものを目にしていますので、人の始まりが受精のときだということを、多分自分の感覚として知っているのだろうと思います。
次のスライドは詳しく書いただけのものですので、後でご覧いただくことにして、問題は、科学的事実をめぐって議論が戦わされたということに先ほど触れましたが、その事情を少しご説明したいと思います。ヒトの始まりが受精時であることに異論を唱えたのは、マコーミック、彼はイエズス会の神父で、ジョージタウン大学ケネディ研究所の倫理神学教授です。彼は医学の専門家ではありませんでしたが、生物学者グロブシュタインと共同で、14日目までの胚はまだ胚以前の段階のpre-embryoであると主張する論文を執筆しました。
イギリスで世界で初めてヒト胚研究の道を開いたのはウォーノック委員会でしたが、その委員として一番発言力を持ったのはマクラーレンでした。マクラーレンはノーベル章も受賞している発生生物学者で、日本でES細胞の研究をしている中辻教授の先生でもあります。ウォーノック委員会は様々な専門家を集めた委員会で、生物学の知識にみんな乏しかったところで、マクラーレンがこのプレエンブリオという概念を持ち込んだのです。受精卵もエンブリオですから、「エンブリオの前」を表すプレエンブリオという語は、まだ新たな人ではないということを含意します。「受精後14日目までエンブリオは存在しない」ことを示す、そういう新しい「プレエンブリオ」概念を作って、ヒト胚を使った実験を推進したい人たちに研究推進の口実を与えました。
ノーマン・フォードもカトリックの生物学者ですが、14日目までの胚は一卵性双生児を生ずる可能性があるから、まだ人の個体ではないと主張しました。先ほどの、個人を重視する自己観の持ち主にとっては、個人かどうかは非常に重要です。フォードは、一卵性双生児を生ずる可能性のある受精卵はまだヒトの個体、すなわち個人とは言えないから、「まだ細胞の塊にすぎない」と主張しました。
フォードの見解は、日本でも大きな力を発揮したと思います。日本での議論も14日目まではまだエンブリオではないということを前提に、簡単にゴーサインが出たと思います。要するにヒトの生物学的な始まりがいつか、この点が決定的なポイントなのです。人間の尊厳や人権を守るべきということについては、おそらくみんなの合意が得られると思いますが、受精卵に人という身分を与えなければ、簡単に実験材料にすることができるわけです。ヒト胚研究の是非について、科学の議論が一番大事だったのはこのためです。受精後14日目までは、まだ人が発生していないというのは科学的な誤謬(ごびゅう)です。プレエンブリオという言葉も、今日ではすでに発生学では用いられていません。一卵性双生児のメカニズムはまだ実証されておらず、フォードの見解も一つの仮説にすぎません。生命アカデミーの見解では、受精時にすでに個体が確立している。しかし初期の胚は可塑性に富んでいるので、なんらかのアクシデントで2つに分かれたとき、もう1つの個体が発生する可能性がある、ということです。シャム双生児のように、14日目以降でも一卵性双生児が発生する例もあります。
以下のスライドは、もう一つのコシエンツァについての説明です。これは国際法と生命倫理原則の確認です。世界人権宣言には、人間である限り、誰でも例外なく人間の尊厳と基本的人権を認められるべきである、との原則が記されています。人間の尊厳原則の起源は、世界人権宣言の半世紀前、1890年に発されたローマ教皇レオ13世の回勅『レールム・ノヴァルム-資本家階級と労働者階級の権利と義務』でした。19世紀最大の社会的不正義は、労働者の問題でした。労働の搾取の問題です。労働は人間の営みの1つであり、人間の生活と切り離せないものです。ですから、経済効率だけを追求してはならないので、人間らしい働き方というものがあるはずなのです。今日では労働基本法が整備されていますが、当時、労働者の権利は保障されておらず、経済発展のために大規模な労働の搾取が行われていました。その不正を糾弾したのが『レルーム・ノヴァルム』でした。
先ほど社会科学アカデミーの話をしましたが、今日のカトリック教会の社会正義についての基本文書が、この『レルーム・ノヴァルム』です。「人間は経済発展の手段ではない」。今日の生命倫理問題もこの応用編です。「人間は科学の発展のための手段ではない」。両者はまったく同じ構図です。「人間の尊厳」原則は、戦後、国際的な医学研究倫理の最高原則にもなっています。世界人権宣言自体、ナチスの医師たちの人体実験に対する反省から生まれたものなのですが、世界医師会もヘルシンキ宣言を出して――これはヒポクラテスの「医の倫理」の現代化と言うことができると思います――、医学を発展させなければならないけれども、被験者の利益を優先しなければならないことを明確にしています。
最近の国際的な医学研究倫理の一つとして、96年の生命倫理条約を挙げることができます。生命倫理条約というと、一体どのような内容のものかわかりませんが、正式なタイトルは「生物学と医学の適用に関する人権および人間の尊厳の保護のための条約・人権と生物医学条約」というのです。「人権と人間の尊厳の保護のための条約」であることが明確にされています。
次のスライドのクローニングの国際規制については先ほど触れましたが、ここでは生殖目的のクローニングがどのように人間の尊厳に反するかを、少しご説明致します。これはハンス・ヨナスというユダヤ人哲学者の言葉です。「ヒトクローニングは、方法においてこの上なく専断的であり、目的においてこの上なく奴隷的な遺伝子操作の形態である」。ヴァチカンの文書もこれを引用しています。別の言葉で言うと、ヒトクローニングは「優生計画である」。優生計画という言葉もヨナスの表現ですが、ここで問題にされているのは、クローン技術によって作成されるクローン人間の尊厳と権利です。どのような権利が侵害されるかというと、異性の両親から生まれる権利、それから家族や親族を持つ権利です。生きる権利だけではなくて、どのようにして生まれてくるか、生まれ方に関わる権利です。人は誰でも自然の生殖においては、お父さんとお母さんから生まれてきます。家族や親族を持つ権利は、水平方向と垂直方向、両方の方向の家族・親族関係を持つ権利です。クローン羊ドリーの母親は、年の離れた双子の姉です。父親はありませんが、父方と母方の祖父母が遺伝学上の父母に当たります。ドリーは垂直方向の子孫との関係も、水平方向の親族関係も複雑な環境で人格形成をしなければなりません。
それから、クローン胚の自己決定権も問題にされています。卵子がどうやって受精するのか、どの遺伝子をどのようにプログラミングするのかは、誰かが決めるのではありません。第三者が恣意(しい)的に決める、あるいは操作するのではなくて、その卵子自体が選び取っていきます。偶然に定まるというよりは、卵子とその精子の出会いによって、いろいろなことが決まっていく。人はみんなそのように、誰かに決定されたり干渉されたりしないで生まれてくる権利があるのに、クローン技術で生まれてくる人間は、最初から操作されて、遺伝子を決定されて生まれてくる。これは「優生計画」である。そして、これとほぼ同じ論理で、着床前診断も非難されることになるのです。
クローニングの禁止をめぐる国連での議論の際、アメリカはクローンに反対する側に回ったのですけれども、実は、反対の理由をまったく見出すことができませんでした。同じく日本の刑事法学者の間でも、クローン禁止の根拠について多くのものが書かれましたが、どれも歯切れが悪いのです。個人主義の立場をとる限り、クローン禁止の根拠を見出すのは無理です。個人の自己決定権を認め、受精卵の人権や尊厳を認めないのであれば、子どもを持つ権利、リプロダクティブ・ライツを主張する側が勝つに決まっていますので、クローニング禁止の根拠は出てきません。しかし、生命の開始時から人権や尊厳を認めれば、クローン禁止の根拠は全部きれいに説明できるわけです。アメリカが全面禁止に賛成したのは、結局、当時のブッシュ政権が保守的な立場を採用していたためでした。フランスは戦勝国でもあり、優生思想に対して割合寛容なためか、反対に回りましたが、ドイツとイタリアは優生思想に対する反省――敗戦国ですので――が効いていて、人間の尊厳原則にも非常に敏感であるという事情などもあるのではないかと思います。
人間の尊厳原則に対する異論は、人の倫理的地位、すなわち人格概念をめぐって展開されます。これは哲学の分野では大変な論争になっているところです。人格とは何か――この議論にはもうあまり立ち入りたくないのですが――今度は生物学の議論から離れたところで、生物学ではそうかもしれないけれども、「人格とは何か」という問題は必ずしも生物学のみに縛られないのではないか、独自の人格概念があってもいいのではないかが議論されます。しかしそのようなことを誰かが言い出しますと、それはもう100人いたら100とおりの人格概念が生まれても不思議ではないわけです。
代表的な見解は、自意識を重視する立場です。「人格とは理性的な、自意識のある存在だから、自意識または人格性を示す他の外面的な行為、態度、能力を持たない人は人格ではない。したがって尊厳と人権も持たない」と主張します。3歳児、植物状態の人は人格とは認められないので、生きる権利もない。したがって自由に殺してもかまわない、少なくとも生命権の侵害はないことになります。この論理でいくと、ヒト胚ももちろん人格とは認められません。では、3歳まで人格ではないのか。そう主張する見解もありますが、多くは、14日目までの初期胚は、少なくとも知覚能力をつかさどる神経細胞の元である原始線条がまだ発生していないから、当然人格ではない、と主張します。しかしこうなってくると、人格の開始時点については、本当にいくらでも線が引けるので、いろいろなバリエーションが考えられることになると思います。反論するほうも大変です。
しかし、この考え方の一番の問題点はどこかと言うと、この論理は、奴隷制を肯定するための論理と同じであるところです。ヴルテニウスという法律家(1565年~1632年)は、奴隷制を肯定するために、初めて法律の領域にこの人格概念を持ち込みました。そして人格性をそなえた者の尊厳だけを認めようとしました。人格でない人間は、物扱いしてもよいことになります。これは、奴隷制を許す論理なのですが、同じように、14日目までのヒト胚を物扱いすることを許す論理が、今、復活していると言うことができます。
これに対する反論として、レジメにはグアルディーニの見解を挙げました。「本来の人格概念は、自己支配、人格的責任、真理と道徳秩序のうちに生きる能力を意味する。それは、年齢、身体、心理状態、自然的素質によるものではなく、存在に関わるもの(existential)であり、精神と身体の統合体である人間の本質を構成する精神的霊魂(spiritual soul)によるものである」。大事なのは「存在」であって、人間の尊さは「精神と身体の統合体である人間の本質を構成する精神的霊魂」だとされています。すなわち、人間は物質、DNAだけで構成されているわけではない。物質と、物質でないもの、すなわち身体と精神との両方から構成されている。そして人間の本質は精神の部分にある。しかし両者は不可分に結びついて切り離すことができません。肉体があるところに即ち精神がある。この考え方は、ときどき誤解されるように、精神だけを大事にして肉体を軽視するものではありません。
これはシスティーナ礼拝堂の天井に描かれているミケランジェロの「アダムの創造」です。アダムは立派な肉体をしていますが、力がありません。まだ精神が宿っていないからです。今、右側にいる父なる神――キリスト教の「三位一体」の神である、「父」と「子」と「聖霊」の「三位」のうちの「父」――が、アダムに精神を吹き込んでいるところです。それによって命あるもの、生きるものにしたのです。アダムは神が創造した最初の人間で、これが「クリエイション(創造)」です。神はその後、人間の創造を人間の男女に委ねたので、人間は現在、生殖によって新しい命を創造しています。それで、人間の生殖をプロクリエイションと言います。
このフレスコ画では、肉体が先にあって、後から精神を吹き込んでいますから、ここには少しインターバルがあります。トマス・アクィナスは今日のカトリック神学の基礎を築いた16世紀の神学者ですが、彼が唱えた「遅延入魂説」をめぐって、――我々には信じがたいことですが――神学者や哲学者の間では、今日かなりさかんな議論が見られます。しかし、トマスが遅延入魂説を唱えた当時、まだ卵子は発見されておらず、ヒトの生殖のメカニズムは、精子が女性の子宮に入ると、子宮内の血液が凝固してヒトのもとになると考えられていました。つまり、精子が女性の胎内に入って血液が凝固するまで、新しいヒトの発生まで、数日間のインターバルがあると考えられていたのです。遅延入魂説は、このような誤った生物学を前提にして唱えられものだったので、1827年に卵子が発見され、受精の生物学的メカニズムが解明されると、ほとんどの神学者によって放棄されました。ところが、遅延入魂説は後世の倫理学者によって再び取り上げられます――中絶合法化を根拠づけるため、そして今また初期胚の実験利用を合法化するために。
これは、ヒト胚をテーマに2006年に開催された生命アカデミーの国際会議のプログラムの表紙に使われた14世紀の絵です。右側の赤い服を着ているのがマリアです。マリアのおなかの中にはイエスがいます。そして左側にいる女性、エリサベトのおなかの中には洗者ヨハネという預言者がいて、2人が出会ったとき、おなかの中の子が喜び躍った、と聖書には記されています。
この絵を生命アカデミーが使ったのは、生まれる前の子どももコミュニケーションしていること、人と人とのかかわりをしていることを示したかったからだと思います。そして、次のような人格概念を提示します。「個人」だけが孤立してあるのではなくて、人と人とのかかわりが人格にとって不可欠な要素である。その人格的なかかわりは、自意識のレベルに限られません。ヨハネと洗者ヨハネは、母胎内にあって自意識はなかったかもしれないけれども、何かを察知してコミュニケーションしていた。それは、精神的なコミュニケーションなのですが、それを示したかったのだと思います。
生命アカデミーの文書は、この絵について直接解説しているわけではありませんが、先ほど水野先生がおっしゃっていた「胎児と母のコミュニケーション」が生化学のレベルで行われていることを、子細に証明しています。受精卵、胚が子宮に着床する時期はごく短期間に限られていて、子宮はこの期間を過ぎれば胚を受け入れません。この着床期の子宮の受精卵に対する許容状態は窓にたとえられて「着床ウィンドウ」と呼ばれています。このウィンドウが開くのに合わせて、胚も着床できる状態に変化するのだそうです。このように、母と子の間では、生化学レベルで非常に猛烈な対話が交わされています。したがって、着床は、母親が一方的に決めるのではなくて、子どもと子宮との間のクロストークなのです。双方の条件が整わなければ着床は起こらないことが、生物学的に明らかにされています。ヴァチカンは胚が母との間でこのような生化学的なコミュニケーション、物理的な対話が交わされることを証明して、胚が人格であることを示そうとしているのです。
時間がなくなってしまいましたが、最後に生殖補助医療についてお話させていただきます。これも、シエンツァとコンシエンツァの両面から考察する必要があります。
まず、シエンツァ、科学面。技術的な問題のほうでは、生殖補助医療技術はまだ研究段階にあることが明らかにされます。もしそうだとすると、ヒポクラテスの誓いに書かれているように、「害するな」が優先します。科学を発展させることはよいことですが、しかし害してはならないのです。まだ実験段階にあるということは、母親も胎児も、この技術によって害する可能性があるということです。
母親に対する害としては、まず第一に、妊娠率が非常に低いことが挙げられています。95%の成功率を得ようと思ったら、平均15回の施術を繰り返さなければならない。それは母親に強度のストレスを与え、多くの者がうつ状態に陥ります。不成功に終わる女性の8割が深刻な損害を被るのだそうです。
先ほど、大した問題ではないように言われていましたが、過剰排卵症候群というのは、死亡する場合もある、極めて危険な状態です。排卵誘発剤を使って一度に多くの卵子をつくり、それを体外に取り出すことは、後にホルモンのバランスが狂うなどして、かなり大きな負担になるようです。また、着床前診断を経た場合、妊娠率は非常に低くなります。着床前診断によって選別された胚の出生率は3%未満です。普通の生殖補助医療技術の場合は20%程度ですから、妊娠率は極めて低い。これもまだまったくの実験段階ということができます。
顕微授精は、人間の体軸を恣意的に決定します。精子が卵子に入り込む位置が、背骨の位置になります。それを、適当な場所に注射針を刺して精子を注入しても大丈夫なのか。恣意的に体軸の位置を決めてしまってもいいのか、このような人為的な操作は許されるのか。
他方、生まれてくる子どもに対しても深刻な損害を及ぼします。自然流産、早産、低出生体重児、――この低出生体重児というのは、要するに成長が不全だということですので、重い病気になりやすいなど、将来子どもにさまざまな負担を与えることになります。それから凍結。凍結されることで、受精卵は何らかの損傷を被る可能性があります。さらに、健全な人格形成の困難。先ほど言った親戚関係の複雑化などです。ヴァチカンは生殖に対する医療技術の介入はすべて否定されるべきだと言っているのではなくて、科学はもっと別の方法を探求すべきだと言いたいのです。科学というのはそんなに弱いものではない。倫理の限界に行き当たっても、別の道が開けるはずなのです。ですから、現在の生殖補助医療技術を無理に押し進めるのではなくて、倫理を曲げないで解決する方法はないのか。
今、ゲノム・プロジェクトの成果によってかなりの不妊の原因が特定できているのだそうです。これは、親のほうの遺伝子治療を可能とするものです。そしてこれこそが不妊の根本的な解決につながる本筋なので、こちらを一生懸命にやりなさいと、専門の研究者に働きかけるようなことをしています。
次にコシエンツァ、倫理面。「生殖の尊厳」を唱えます。英語ではdignity of procreation で、先ほど触れたとおり、reproductionではありません。物質レベルでは動物と同じreproduceかもしれませんが、生殖の結果もたらされる人間はreproduction(複製品)ではありません。人間は精神的な別の次元を帯びているので、procreationという別の言葉を使います。
カトリック倫理は、愛と生殖の一致を説きます。身体の一致と精神の一致は同時に存在すべきである。愛の実りが新しい命の創造でなければならない。産児が科学技術の成果やリプロダクションであってはならないのです。それは、物質面だけを推し進めるものであって、優生学と同じだ、と言うのです。ですから、労働の精神性、労働の尊厳を労働問題に持ち込んだのと同じように、生殖の精神性をどう考えるか、生殖補助医療にどのように盛り込むのか。この「プロクリエイションの尊厳」の考え方によっては、各論レベルではカトリックほど保守的でない別の答えがあるのかもしませんが、原理的にはこういう考え方が取られています。大事なのは、生殖の精神的な次元を重視すると、どうなるかということです。ここに何を盛り込むかは、それぞれの宗教や文化的事情によって多少変わってくるのだろうと思います。
イタリアの生殖補助医療法は、基本的にはカトリックの考えをほぼフォローしたものになっています。男女の愛と生命の創造の一致ということは書かれておりませんが、その考え方が背景にあります。
法施行後の実施状況なのですが、昨年4月に施行5年後の報告書が出ました。3年後の報告書も出されましたが、最も注目されるのは、受精卵が何人救われたかという、その詳細なデータが示されていることです。報告書は、もし法律が施行されていなければ凍結されていたであろう受精卵の数を各医療機関ごとに割り出して、5年間で大体12万人救ったということを記しています。そして、凍結される胚の数を減らしても、妊娠率に差はなかったのだそうです。ですから、技術の効率に変わりはない。2009年のレポートの課題は、母親の負担の軽減が数字に表れていないことです。先ほど言った過剰排卵症候群など、母親の負担はこの法律では解消できないから、今後これからどうするかということを考えるべきだ、そういう方向が示されています。
すみません、大急ぎでしたが、以上で終らせていただきます。
質疑応答へ続く
水野先生がおっしゃっていた自由主義が日本では著しいのですが、私はその自由主義生命倫理とは反対の立場、人格主義生命倫理についてお話させていただきます。
今、皆さんの自己紹介をお聞きしていて、法哲学の方もいらっしゃいますし、法律学の方、社会学の方もいらっしゃいますので、先ほどきちんとお話しなかったのですが、なぜ刑法を専攻していて、生命倫理を研究することになったかを簡単にお話させていただきます。特に、なぜカトリックの生命倫理を研究することになったのかを――もう少し今日の話をご理解いただけるのではないかと思いますので――お話させていただきます。
大学院では刑法を専攻しておりまして、安楽死の問題を修士論文で扱いました。このとき、当時の日本の刑法学は自己決定権と自由主義の立場を最初から土台にしていました。その土台を問うのは法哲学ですが、私は法哲学を勉強せずに刑事法を専攻しましたので、自己決定権の立場からの結論しか出てこないのです。つまり1つの世界観が最初から前提にあって、その上に組み立てていく議論しかできなかったのです。
富山大学に赴任しましてから、かなり自由な研究環境に恵まれましたので、そのとき出した自由主義の結論、つまり、自殺の権利を認めるという結論で本当にいいのかどうかを、法哲学にさかのぼって少し考えてみようと思い、独学で法哲学を勉強し始めました。
出身が上智大学でしたので、キリスト教倫理の専門家が周囲に大勢いました。修士論文の審査のときに教会法担当の神父がおり、専門の立場から自殺についてのレクチャーをしてくれたのです。当時はドイツの法律を調べておりましたが、判例の文言の中に、キリスト教の伝統的な倫理ではこういう考え方をする、ということが普通に書かれています。ドイツの刑法の背景にキリスト教の倫理があること、その意義深さをこのとき実感しました。
日本で今、問題になっている安楽死や、受精卵の実験、生殖補助医療の問題もそうですが、これは倫理の問題です。それについてドイツやフランスやイタリアでは一応倫理学の議論を見て、その後でそれを踏まえて法律学者が議論するという仕組みになっていると思うのですが、日本では、法律の人がいきなりそれを議論しています。では日本の倫理学者はどうしているかと言うと、どうもあまり法律学とは連動していない。
それで、富山に参りまして間もなく半年間の在外研究の機会を与えられましたので、ヨーロッパの法律の土台にあるキリスト教の倫理をしっかりやってみたいと思ったのです。しかし在外研究先に選んだのはアメリカのジョージタウン大学でした。ジョージタウン大学は、ご存知のとおり、自由主義生命倫理学を始めた本拠地です。しかしその研究所に半年間勉強に行くプログラムを組んでくれたのは上智の生命倫理の先生でした。アメリカに行く前にスペインとイタリアにも立ち寄りました。イタリアはちょうど生命倫理の国際会議があったのでその様子を見るだけの予定だったのですが、たまたま訪れたローマの大学、教皇庁立のグレゴリアン大学ということころだったのですが、世界中から生命倫理の研究者が来ており、「カトリックの生命倫理をやりたいならなぜアメリカに行くのか。アメリカの生命倫理は自由主義で、カトリックとは反対の立場だ。私は伝統的な生命倫理を学ぶためにイタリアに来た」というようなことをアメリカの学者に言われて、はじめて事態に気づいたのですが、それを全然知らずに行ったわけです。結局、行き先を変更して、イタリア語もできないのに半年そこにおりました。
要するに、生命倫理という言葉が使われたのはアメリカが最初ですが、生命倫理の実体はヒポクラテスの時代からあり、それを実質的に発展させてきたのがカトリックの倫理神学という分野だということに、そこで気付きました。その後、やり始めてしまったことでもあるし、特にカトリックの立場としてそれをやるとか、そういうことではなくて、日本では全然知られていない――私自身もそうでしたが――欧米には個人主義の生命倫理しかないと思っていたのですが、そのリベラルな生命倫理のカウンターパートが実はヨーロッパにちゃんとあって、――それが今、保守的と言われているカトリックの生命倫理です――それを紹介しようと思ったのです。ところがそれは、実際にはかなり大変な作業でした。まず、自由主義の強い日本で紹介しても、保守的な倫理の話は誰も聞きたくないわけですし、刑法は脱道徳化が戦後のうたい文句になっています。刑法と道徳が日本では分離されておりますので、倫理学をやっても法律に反映するまでに非常な距離があります。
もっとも最近は少し風向きが変わってまいりまして、カトリックの考え方を随分いろいろなところで紹介させていただけるようになりました。聞いてくださるのは、特にほかの宗教の方、それから主に実務に就いている臨床医です。2006年に富山で人工呼吸器の取り外しの事件(射水市民病院事件)が発覚し、自己決定権に基づいた決定がなされようとしましたが、事態は急展開して、そうではない、人格主義的な解決がなされました。それは、自由主義とは別の考え方、倫理主導の伝統的な考え方に基づくものです。先ほど水野先生が医者の本能とおっしゃいましたが、本能というよりも、職業倫理上の使命感かもしれません。
ヒポクラテスの「医の倫理」というものがあります。患者のために自分の技能を使って奉仕するという徳の倫理なのですが、これが個人主義、自由主義、自己決定のカウンターパートです。私はこのカウンターパートの方を調べて紹介してきたのですが、カトリック倫理そのものを提示するといろいろと反発が強いので、イタリアの例を紹介することもしてきました。イタリアはヴァチカンのおひざ元にあり、かなりカトリックの影響が強い。そして、医者の組織が非常に強いところでもあります。イタリアで生命倫理を担っているのは、倫理神学の養成を受けた医者です。私がローマで教えを請うているのは、大体が医学者です。受精卵の問題については、ヒト遺伝学の世界的権威の医学部教授が神父でもあります。ですから、倫理神学の養成があり、医療倫理が実践でできてという人が大体担い手になっているので、非常に科学的であり、しかも伝統倫理にのっとった――カトリック倫理という言い方をしないで、普遍的な自然道徳法などいろいろな言葉が使われていますが――カトリックだけではなくて、普遍的に使えるものにする取り組みを、カトリックでは非常に熱心に追求しています。法哲学の方は、自然法の立場をお取りになると大体接点があるというか、同じ立場に行きつくのだろうと思います。前置きが長くなりました。
人格主義生命倫理というのは、カトリックで使っている名称で、リベラルな自由主義生命倫理の対概念としてつけられたものです。英語ではパーソナリスティック・バイオエシックスです。西洋の生命倫理には2つあって、個人主義と人格主義、これは単純な図式化といってよくお叱りを受けるのですが、こうでもしないと日本で生命倫理と言うと、左側の個人主義がすべてだと思われてしまいます。上智大学はカトリックの大学ですが、そこでも生命倫理の研究をしたいと言ったらアメリカに行くように言われたということが、すべてを如実に物語っています。何年か前の日本生命倫理学会でフランス人の教授がヨーロッパの伝統的な生命倫理について講演したのですが、そのとき著名な日本の倫理学者が、「西洋に別の考え方があるのを知らなかった」ということを公の場で発言されたのは非常に印象的でした。
生命倫理は1960年代にアメリカで始まったとされています。それ以前は生命倫理という言葉自体はありませんでした。しかし、この個人主義生命倫理というのは、実は右側の人格主義生命倫理を否定して、そのアンチテーゼとして生まれてきたものです。つまりゼロからのスタートではなくて、既存の考え方とは反対の立場を取って、伝統を切り捨てる立場を取っているのが個人主義だということです。最高原理は個人の自己決定権ですが、この反対が人間の尊厳です。人格主義は人間の尊厳が最高原理です。
本日はわざわざご説明するまでもないかもしれませんが、バイオエシックスの誕生は、アメリカでちょうど公民権運動が盛んだった時代です。ビートルズの時代、ウーマンリブの時代です。先ほどどなたかリプロダクティブ・ライツの話をなさいましたが、社会的弱者が社会的強者に対して反抗するという、そういう社会革命が公民権運動です。男性に対して女性、黒人に対して白人、学生に対して教師――学生運動です――、そして患者さんが医者に対して、反抗します。
アメリカは人種のるつぼですので、共通の倫理がないと言っては語弊があるかもしれませんが、ピューリタンの倫理もあれば、様々な国からの入植民の倫理もあって、人種も社会的身分もまちまちですので、合衆国としてみんなで一緒にやっていくためには、憲法が最低限のルールになります。合衆国憲法がすべてで、そこを起点にします。
ですから、弱者が強者に対して戦うときに何を目標にするかと言うと、合衆国憲法に勝ち取った権利を書き込むことです。どんな権利を勝ち取るか。女性の中絶権、自分で決める権利、個人情報をコントロールする権利、――加藤尚武先生は「愚行権」という言葉を造られましたが――愚かなことをする権利。いろいろな権利が新しく考え出されました。リプロダクティブ・ライツ、子どもを持つ権利もそうです。男同士であっても、女同士であっても、技術でそれができるのであれば、そういう権利もあっていいわけなので、どんどんそういう権利を主張し、勝ち取っていきます。このようなムーブメントの中で患者の自己決定権というものも出てきました。
ここには合衆国の建国の理念が反映されていて、個人を大事にします。もともとイギリスで国教会の迫害を受けたピューリタンが、新天地を求めてアメリカに脱出してきたわけですので、権威に対して非常に反抗するし、自分たちで新しい国を造るとき、自分たちを迫害したような公権力に頼らない。アメリカでは「小さい政府」ということを言いますけれども、個人が自分のイニシアチブを発揮できることが一番大事ですので、自由の権利が強調されます。同時に、アメリカで一番大事にされるのはプライバシーの権利だと言われます。このプライバシーの権利というのは、個人が公権力から干渉されない権利です。公権力の干渉をできるだけ排除します。アメリカではプライバシー権が憲法上の最高の権利と言われますが、これはヨーロッパの憲法には出てきません。公権力と個人とをこのように対立関係でとらえるのは、アメリカ独特の考え方です。
何が言いたいかと言いますと、ここでわざわざ申し上げるまでもないのですが、アメリカは独特な政治状況の中で、独特の人格概念を醸成してきたということです。ハーバード大学ロースクールの法律学の教授、グレンドンがこのことを指摘しています。ドイツの憲法に描かれている人格は、人と人との関係を大事にする。それは孤立した個人を対象にしていない。それに対してアメリカの人格は、個人のイニシアチブを大事にする。1人にされる権利、1人でいることを許してもらう権利、人から干渉されない権利を求める孤立的な自己、それを対象にしていて、その人格概念に大きな違いがある。これは合衆国憲法の話です。ジョン・ロックの政治思想にそれが描かれているのですが、これをそのまま生命倫理の問題に適用してもいいか、そこには無理があるのではないか、とグレンドンは指摘するのです。
このようなアメリカの独特な人格概念、アメリカの「人格」は、しばしば法的権利主体と同視されます。ですから生まれた後の人を指します。人格という言葉は、もともと法的権利主体を指すだけのことばではないのですが、アメリカの新しい個人主義生命倫理は、人格を最初から法的な権利主体を表す語としてのみとらえ、この法律上の概念である「人格」を倫理でも採用する。個人主義生命倫理の大きな特徴です。
個人主義生命倫理の想定する自己像として、「孤立的自己」と書きましたが、これについて、最近面白い文献を見つけました。東大医学部の名誉教授、大井玄先生が書かれた本の中に「文化心理学」という割合新しい学門分野の紹介があって、その文化心理学によると、世界には2つの自己観、「孤立的自己観」と「関係的自己観」がある。この「関係的自己観」は割合普遍的な考え方で、「孤立的自己観」は、アメリカに特異な考え方なのだそうです。もちろんアメリカ以外でも、移民やニューフロンティアの状況を想起していただきたいのですが、非常に広大な土地に人間がいて、――隣の家まで何キロもあるような――、自分の力で土地を切り開いていくような環境があって、このような自己観の形成が初めて可能になる。日本では北海道の人にこのような自己観の持ち主が多いという調査結果もあるのだそうです。ところが、1人ひとりにこのような広大な空間が与えられていないところでは、長屋やマンションなどに住み、お隣と密接にかかわっていて、親戚も知り合いも身近に大勢いる、そういう閉鎖的な社会では関係的自己観が形成されます。ここでは「孤立した個人」というものはイメージしづらくて、大体、何かを自己決定すると言われても、実際には自分だけで決めていない。周りのことを考えて決める。安楽死の問題についてもそうです。もし自分が何か人に迷惑を掛ける状態になったら死にたい。それは人に迷惑を掛けるから死にたいのであって、アメリカ人は、自分がもう、1人で自立できない、自分1人で決められない、イニシアチブを発揮できない。そのことがつらいから、だから死にたいのだという答えが返ってくるのだそうです。しかし日本人はいつも他者とのかかわりの中で決定をします。そして世界的に見ると、インドもそうだし、アフリカもそうだし、日本人のような反応がむしろ標準的であって、孤立的自己観はごく特殊な地域で見られるにすぎないのだということです。
戦後の日本は、刑法学もそうですが、個人主義が急に入ってきて、今までの関係的自己の持ち主が、孤立的自己――大井先生の言葉では「アトム的な自己」――を確立できないで、いろいろな葛藤があるところから、鬱状態になったり、自殺が増えたり、ひきこもりになったりするのではないかというような感じがするのですが、いずれにしても、個人主義生命倫理も、この孤立的自己像をモデルにして、個人の自己決定権を最重視します。
それに対して人格主義のほうは、存在論に立脚します。存在論においては、個人にとって大事な価値、自己決定、自意識、理性の働きなどではなくて、存在そのものの価値を重視します。自己決定しなくても、自意識がなくても、人間の尊さというものをそれとは違うレベルで見ていくわけです。例えば、自意識の働きがない人に対しても、なんらかのつながりを持てればその人を大事に思うかもしれないし、その人の存在そのものの価値を認めます。つまり、自意識によって、理性によって自分の能力を発揮するなど、そういう考え方でいきますと、何が人間にとってよいことかということを考えますので、功利主義につながりますが、そうではなくて、存在そのものの価値、人間の内在的な価値というものを認めていくと、それが人間にとって利益になるかどうかではなくて、ともかく人間なので大事にしようと、そういう考え方になるわけです。
考え方の基礎を築いたのは、ジョセフ・フレッチャーというプロテスタントの神学者で、大谷いづみ先生が彼を取り扱った本を最近出されています。フレッチャーが1954年に出した『倫理学と医学』という本は、「カトリック以外で医療における倫理問題を取り上げた最初の書籍」といううたい文句になっています。彼はこの中で初めて安楽死を合法化し、正当化します。これが日本にも入ってきて、私が大学院時代に悩んだ、自己決定権による自殺の合法化につながります。日本でも宮野彬という刑法学者が積極的安楽死の合法化を唱えますが、彼もフレッチャーに影響を受けておりましたし、それから「日本安楽死協会」を作った太田典礼もこのフレッチャーの書物からヒントを得ていたのだそうです。
個人主義生命倫理について、スライドに「反宗教的」と書きました。この点については、あとでまた詳しくご説明致しますが、個人主義生命倫理は、要するに伝統的なカトリック倫理ではなく、世俗的な哲学に立脚しているということで、日本の哲学者がこれを組織的に輸入したのです。そして、教育現場にもこれをそのまま持ち込みます。アメリカの大学では大規模な教育プログラムを組んで在外研究者や留学生を受け入れました――私がジョージタウン大学に行こうと思ったのも、この教育プログラムを受講するためでした。そして個人主義生命倫理は日本にもすごい勢いで広がりました。
右側の人格主義のほうはどうかと言うと、先ほども申し上げましたとおり、生命倫理という言葉自体はありませんでしたが、その元になっているのは、伝統的なヒポクラテスの「医の倫理」です。これは紀元前のもので、非常に簡単です。要約すれば2つのことしか書かれていません。ヒポクラテスは、科学的医学を始めた人です。「科学」というのが1つめのキーワードです。もう1つは、「目の前の患者の善」です。科学を大事にします。科学的知識の行使は特殊技能ですので、これを守り、弟子に伝えて発展させます。医者はそういう任務も担うし、もう1つの任務も担うのです。目の前の患者を助けることです。では、科学を発展させるために目の前の患者を犠牲にしていいかと言うと、答えははっきりしていて、常に目の前の患者を助けることが優先されるのです。ですから、「科学」というのがキーワード。もう1つは「目の前の患者の善」。そして「目の前の患者の善」が常に優先します。
あとはこの応用問題というか、この原則を当てはめればよいのです。この「科学」プラス「倫理」、それを個別の問題に当てはめて応用問題を解いていきます。方程式はずっと同じです。イタリアではこのヒポクラテスの「医の倫理」を現代化する取り組みが続けられてきました。イタリアの話が日本の医者になぜ受けるのか。イタリアでの議論は、ヒポクラテスの「医の倫理」を共有している医者には理解しやすいからです。ヒポクラテスの「医の倫理」を継受したのはカトリックだけではありません。ヒンズー教とイスラム教、ユダヤ教にも継受されました。東洋とのつながりも指摘されています。「医は仁術」と言います。仁慈は儒教の最高倫理です。ヒポクラテスの「医の倫理」は東洋の徳の思想ともつながっています。
このように、ヒポクラテスの「医の倫理」自体は宗教とは無関係の世俗的なものだったのですが、ただ、多くの宗教はこれをこぞって継受して発展させました。それを最も組織的に学問体系に構築してきたのが、最近500年くらいの間のカトリック倫理学でした。私が個人主義生命倫理の反対の立場を研究しようと思って、カトリック倫理学を見なければならなかった理由は、ここにあります。ただ、カトリック倫理学は、ヴァチカンがほとんど世俗的な権力を失った現在、その実定法としての展開を見るためには、その影響を受けている国の法律を見ることが必要になります。イタリアの法律は、私の見る限り、生殖補助医療法もそうですが、カトリック倫理に一番忠実な形で展開されているので、イタリアの医療倫理や法律の文献も読まなければならなくなったわけです。
今の話を、時系列というほどではありませんが、一応上から順番に並べると、まずヒポクラテスの「医の倫理」があって、ここから積極的安楽死の禁止、またここには書きませんでしたが、人工妊娠中絶の禁止が導かれます。なぜかと言うと、人を殺すからです。「殺すなかれ」というのが第一の原則ですので、殺さないのです。イスラム、ユダヤ、カトリック、儒教がこれを採用して、16世紀ごろからカトリック医療倫理が体系的な学問として発展します。これを今、個人主義に対抗して人格主義と名付けて、カトリックが熱心に普及活動をしています。1954年にプロテスタント神学者のフレッチャーが――プロテスタントというところが肝心かもしれません、カトリックに反抗する立場です。フレッチャーはアメリカで一番政治的に力のある長老派の牧師です――カトリックでない医療倫理の書を初めて刊行します。積極的安楽死の合法化です。
84年に生命倫理学の体系的な教育機関が2つ創られます。ジョージタウン大学のケネディ研究所と、もう1つはヘイスティングス・センターです。そこで教育を受けた最初の卒業生は、ロバート・ヴィーチですが、彼が84年に書いた論文のタイトルは非常にわかりやすい。「ヒポクラテスの倫理は死んだ」。これが個人主義生命倫理学ですので、両方の立場は相いれない立場です。もっとも、有力な人格主義生命倫理学者はアメリカにもいます。かつてケネディ研究所の所長も務めたペレグリーノは、有名な生命倫理学者であり、医者でもあるのですが、保守的なブッシュ政権の下で大統領生命倫理諮問委員会の委員長を務めました。彼が最近書いたものをこの間翻訳したのですが、その中に、最近の個人主義生命倫理学は「脱宗教的」、つまり単に世俗的であるばかりでなく、「反宗教的」、「宗教敵対的」でさえあるということが書かれています。
以上から申し上げたいことは、この2つの真反対の立場が今、世界にあって、――単純化し過ぎかもしませんが――、この2つの構図を見ながらいろいろな問題を読み解いていくと、対立の根本にあるものが何か、割合わかりやすいのではないかと思って、私は大体この図式に当てはめて、普段ものを考えています。
今日は、代理出産の話ということでご依頼をいただいたのですが、代理出産については、お手元にレジメがあると思いますが、最後のところで生殖補助医療についてお話する中で触れさせていただきます。先に終わりのほうを見ていただいたほうがいいかもしれません。
スライドの31番にイタリアの生殖補助医療法について記しましたが、今日は本当にごく簡単に総論だけしかできないと思います。総論の基本コンセプトを読みます。
「生殖補助医療にかかわるすべての主体の権利を保障する」。先ほどから両親のことは話題に出ておりますが、「すべての主体」は、生まれてくる子どもの権利を含みます。では生まれてくる子どもの権利はいつから保障されるかと言うと、一番初めの受精のときからです。そうすると、体外受精も難しくなるし、今、日本では、iPS細胞から生殖細胞を作って、子どもを作っていいかどうかということが先ごろから議論されているようですが、ここでは、先ほど問題になっていた、卵子を摘出するときの女性のリスクなどは全く生じません。将来、人工孵卵器ができたら問題のありかがいっそう明確になるかもしれませんが、受精のときから子どもの人権を認めるとすると、人はどのように受精されるべきか、どのように生み出されるべきかという問題まで入ってきます。イタリアの生殖補助医療法は、「子どもの権利を一番最初から認める」ことをうたい、「その生命の開始、すなわち受精時から法的主体として保護する」という、これはかなり大胆というか、ある意味で論理必然なのですが、そういう立場を取ります。これは、生命科学技術の進展に対して、生まれてくる子どもの善を優先するという、伝統的な医療倫理に基づいた一つの明確な態度決定を示したものと言うことが出来ます。
32番を見ていただきたいのですが、2009年6月、受精時から人を法的主体とする民法改正案が提出されました。これは、「倫理を法に格上げする」という言い方をイタリアではよくするのですが、アメリカで倫理の議論が法律の議論に還元されてしまったのとは対照的に、イタリアはその逆方向が目指されます。倫理を明確にして、それを法に格上げするということをやっているのです。
このコンセプトにのっとるとどういう結論が導かれるかというと、大体のものは刑事罰で禁止です。胚の商品化、代理出産もそうです。人のクローニング、研究目的のヒト胚の作成と利用です。
フランスではなぜリベラルなのかということを先ほどご質問致しましたが、受精卵がまだ「人」でなければ、人間の尊厳原則に抵触せずに実験に使えるわけなので、そこが一番大事なポイントになります。あとでご説明するとおり、カトリックは科学的事実を重視して、生物学の議論を徹底的に尽くした上で、人の生物学的な始まりは受精時だということを認めます。
子どもが人として生まれてくることのためには、恣意的に作られてはいけないというような論理もそこから出てきます。優生目的の胚の選別と操作、それからハイブリット、キメラの作成、多胎妊娠における減数も駄目です。胚の凍結、破壊も駄目です。余剰胚の作成も駄目、ほとんどのことが禁じられることになります。行政罰で禁止されているのは、第三者の配偶子の使用、インフォームドコンセントをとらなかった場合、不認可の手術を適用した場合等などですが、イタリア生殖補助医療法が一番重視しているのは、子どもの権利です。それも、生きる権利だけではなくて、人格権も保護する。両親から生まれる権利等を保護する。そのような話になっています。
今日お話する内容のポイントは以上のとおりです。代理出産がなぜ駄目かというと、生まれてくる子どもの権利を侵害するからだ、ということなのですが、それをもう少し詳しく見るとどうなのか、前のスライドに戻りたいと思います。
人格主義生命倫理学の基本構造、6番です。科学的事実の承認。ヒポクラテス以来の科学的医学に立脚する立場を貫きますので、まず科学的事実をしっかり確認することです。ヒトの生命は受精時に始まります。「ヒト」とカタカナで書いたのは、生物学上の表記が「ヒト」だからです。まず生物学の議論を尽くします。その次に倫理の議論が来ます。その実質的な内容は「人間の尊厳」原則の確認です。
この「人間の尊厳」原則が何かということについては、もうさまざまな議論があるのですが、できるだけ立ち入らずにすませたいと思います。一言で言えば、それは、「誰でも例外なく人間の尊厳と基本的人権を認められるべきだ」という原則です。なぜ人間に人権があるかというと、尊厳があるからです。人権の前提が尊厳なのですが、先ほど申し上げたヒポクラテスの医の倫理、目の前の患者さん、目の前の人――その始まりの時から――を最大限に尊重する原則、と考えていただいて構わないと思います。両方を合わせると、「受精時から人間の尊厳と人権を例外なく保護しましょう」。これが人格主義生命倫理の基本構造です。
「科学的事実の承認」のあとに記したscienzaは、イタリア語で「科学」の意味です。そして「人間の尊厳原則の確認」のあとに記したcosciencaは、良心という意味です。良心と科学は日本語ではまったく別の言葉なのですが、語源が一緒なのです。つまり、科学はそれだけであるのではなくて、coという接頭詞は、それに伴うという意味ですので、コシエンツァは、シエンツァがあるところに、それに伴ってあるものです。後でまたご説明しますが、人間は肉と霊から出来ています。肉だけではない、目で見えるものの背後に必ずスピリチュアルなものがあります。その目に見えるものと見えないものが一緒になったのが人格です。同じように、科学は目に見えるシエンツァ(scienza)ですが、それが人間の技であるとき、そこには必ず目に見えない次元が入ってきます。スピリチュアルな次元、良心の次元、倫理の次元です。これは自然科学ではありませんので、良心や倫理の問題は自然科学の問題には還元できません。ですから、科学ではできるけれども、それを使ってよいか、どう使うかというのはコシエンツァの問題で、人間が科学をやるときに必ずそれに伴って良心の問題が出てくるという意味です。この良心の中身、ヒポクラテスの目の前の患者優先の態度を言いかえたのが「人間の尊厳」原則だと思っていただければ、大体よろしいのではないかと思います。
カトリックの最近の文献に『いのちの福音』というヨハネ・パウロ2世――前の教皇ですが――の回勅というものがあって、信者あての手紙なのですが、これは信者だけではなくて、全世界の善意の人に向けて書かれたものです。この中に「卵子が受精したときから新たな人の生命が始まる。現代遺伝学はこの不変の事実に貴重な確証を与えた」と書かれています。この箇所は、先ほどのシエンツァ、科学的な事実を記しているだけです。これはただ科学の事実を承認しているだけですが、このことのためにヴァチカンでは多大な精力をつぎ込んでいます。科学アカデミーという1603年にできた組織があるのですが、世界中から招いたノーベル賞受賞者が40人ぐらい含まれています。そういうアカデミーを持っていて、そこで現代科学の最新の事実を厳密に調べるということをヴァチカンはしているのです。こうして現代遺伝学の詳細な議論を踏まえた上で「卵子が受精したときから新たな人の生命が始まる」ということを言っているわけです。
コシエンツァのほうはどうかというと、「人は身体と精神の全体であり統合であるから、身体的に新たに存在し始めた初期胚には、既に精神的霊魂が宿っていると考えられる」と記されています。これは科学ではありません。これはカトリックの信仰なのか、良心の問題なのか、あるいはカトリックもゼロから始まったわけではなくて、その前にプラトンがありますので、プラトンの考え方もこれと同じだと言われていますが、それ以前からある宗教に基づくものなのかもしれません。いずれにしても科学的に解明できない部分ですが、このような人間観に立ちます。要するに、人というのは、身体と精神の全体であり統合である。両方は一緒になっていて、分離できない。でも、両方の次元がある。この人間観が出発点になっています。これを認めないと次に書かれているようなヴィジョンは出てきません。「したがって、人は受精時から人格として扱われるべきであり、また不可侵の生きる権利が認められなければならない」。
この中に日本語に訳すと、「人」という言葉と、それから「人格」という言葉と、「人間」の尊厳という言葉と、「個人」という言い方もあります。日本語では普通、ヒューマン・ビーイング(human being)という語を「人」に、パーソン(person)という語を「人格」に置き換えますが、人間という語は外国語にありませんので、人格と同じでいいのかどうか、いつも翻訳するときとても迷うところです。しかし「人間」というときは大体、その身体と精神の全体であり統合である人格のことを指していると考えられるように思います。一方、「人」という語は、法律用語でもあり、法的な権利主体のことを刑法でも「人」と言いますので、日本でもよく見られる、どこから「人」かという議論は、生物学のシエンツァの議論なのか、それとも倫理のコシエンツァの議論なのか、両者の区別はとても大事な問題です。
ヴァチカンの立場は、まず生物学的な事実を認めます。そして、自然科学ではないところで、人間にはスピリットもあると考えますので、人が物理的に存在すればそこにはスピリットが宿っていると考えて、そのスピリットの部分において人間は尊いと考えます。この考え方はいろいろなところで誤解されていますが、後で「パーソン論」が出てきますので、そこでまたご説明します。
2005年に現在の教皇ベネディクト16世に変わり、カトリックの教えを要約する文書が公表されました。現在の教皇は、前の教皇の時代に教理省という省庁でカトリックの教義を形成する仕事に従事してきた有名な神学者ですが、彼自身が用意したこの文書の中に、「個々人の譲ることのできない生存権は、その受精のときから、市民社会と法律を成り立たせる一つの要素です。国家がすべての人の権利、特に弱者、中でも出生以前の受精卵・胎児の権利の保護のためにその力を行使しないなら、法治国家の基礎そのものが脅かされることになります」(「カトリック教会のカテキズム要約(コンペンディウム)」カトリック中央協議会訳)という文言があります。
ここで主張されていることは、ヨハネ・パウロ2世もそうだったのですが、命の問題や性の問題などについて、よく誤解されるように、カトリック教会は、何か神の領域に人間が手を出してはいけないと命じているなど、よくそのようなことを言われるのですが、そういうことではまったくなくて、「受精卵のときから人権を守らなかったら、平和が守れない」と言っているのです。
ですから、生命倫理を社会倫理の問題と結びつけたところにヨハネ・パウロ2世の功績があった、独自性があったというように、今日では評価されているのですが、その路線を現在の教皇も推し進めているということです。ヴァチカンは今、領土を持っていませんので、国益を追求する必要からも解放され、純粋に世界の平和を追求する立場から、道徳的な指導者として、いろいろなところで政治の問題にも口をはさんでいます。今日のカトリック生命倫理は、単に信者さんに対して正しい性のあり方を説くというようなものではなくて、「弱い人の人権をどう守るかということが世界平和にとって大事なのだ」という、社会正義と結びつけた議論をしているということです。
ヴァチカンの公式見解と書きながら〔スライドに〕欧州議会やドイツの話を書いてすみません。一応色を変えたのですが、お配りしたレジメは白黒ですので全部一律に並んでいます。一緒にすべきではないかもしれませんが、歴史的に並べるとわかりやすいのではないかと思って、今回作ってみました。
1968年にパウロ6世の当時の教皇の回勅、信者あての手紙、これは全世界の人々に向けたものではなく、カトリック教徒のみに向けたものですが、『人間の生命-適正な産児の調整について-』という文書が公表されます。一般に普及した避妊方法を禁止するなど、非常に保守的な内容を含んでいるため、アメリカで新しい生命倫理を構築する運動が起きたきっかけの1つがこの回勅であると言われています。しかしこれ以前にも、哺乳(ほにゅう)類の卵子が発見されるのが1827年なのですが、1864年にピオ9世が受精のときから人であるということを最初に公式に認めた文書を出しているようです。島薗先生が文献の中で引用されているのですが、原典を確認しておりませんので、ここには書きませんでした。その後もピオ12世が、体外受精をしてはいけないということを再三注意している、そういう文献も見られるのですが、この問題についてまとまった文書が公表されたのが、68年のパウロ6世の回勅ということです。
74年に教理省から「中絶に関する宣言」が出されます。この中にも「受精のときから人だ」ということが記されています。そして「中絶は人を殺すことなのでしてはいけない」ということが記されています。87年にやはり同じ教理省から「初期の人間の生命の尊重と生殖の尊厳」という文書が出されます。「生殖の尊厳」というのは聞き慣れない言葉かもしれませんが、カトリック倫理は人間の行為について「尊厳」という言葉をよく使います。後で「労働の尊厳」が出てきます。人間も馬も労働するし、生殖行為もするのですが、人間の行為についてはスピリットの部分が関与しますので、動物の行為とは違う意味合いがあるのです。物理的には同じ行為であっても、そこには別の次元が伴います。
人間の生殖にリプロデュース(reproduce)ではない、プロクリエイト(procreate)という言葉を使うのもこのためです。「生殖の尊厳」を含意する言葉です。教理省が1987年にこの文書を出した理由は、1978年に世界初の体外受精児ルイーズ・ブラウンが誕生したためです。不妊に悩んでいた人々にとっては福音でしたが、ヴァチカンは、体外で生産されるヒト胚にとっては、その後のさまざまな干渉を予測させる脅威的な出来事である、ととらえます。つまり、この時点で、この後、ヒト胚にもたらされる大規模な侵害を懸念していたのです。実際にこの懸念は現在、現実のものとなっています。余剰胚を使った実験は日本ではゴーサインですし、体外の受精卵に対しては誰でも容易にアプローチが可能です。研究用に体外受精卵を作成することさえ許されています。
ですから、教理省のこの文書、あるいはパウロ6世の回勅もそうですが、ここで考えられていることは、人間の受精卵は、通常であれば、お母さんのおなかの中で、お母さんに守られた状態で生を受けます――もちろんお母さんが中絶するということもありうるのですが、これはまた別な事態です。しかし母体外で作成された受精卵は、外からアプローチできる状態で生を受けます。外部の攻撃から身を守るものは何もありません。「容易に危害にさらさる環境で、最も弱い状態の人間を存在させてもいいのか」、そういう問い掛けをするのです。実際に今、一番弱い立場、無防備な立場の者が搾取の道具になっています。それを予見したのが87年の教理省の文書でした。
あとはこの路線が一貫して推し進められるのですが、この考え方に基づいて1989年にヨーロッパ議会で「体内および体外の人工生殖に関する決議」、それから「遺伝子操作の倫理的・法的問題に関する決議」が出されます。体外で受精卵を作ることができれば、これを操作する話はすぐに出てきますので、ヨーロッパ議会でこれへの警戒が示されます。1990年にはドイツで胚保護法が成立します。ドイツの対応が早いのは、人間の尊厳についての歴史的反省があるからです。ドイツはナチスの時代に優生学を推し進めました。これについては後に触れます。
95年にヨハネ・パウロ2世の『いのちの福音』が公表されます。ヨハネ・パウロ2世はこの『いのちの福音』の中で、生命倫理に関する諸問題を網羅的に扱っていますが、特に気にかけていたのが受精卵の問題でした。私が在外研究でイタリアを訪れたのは1995年の秋でした。『いのちの福音』が出されたのは3月でしたが、当時イタリアでは、人の始まりがいつかという議論で持ちきりで、安楽死の研究に来たと言ったら、それはもう解決済みで、今しなければならないのは体外受精卵の問題だ、と言われて、いろいろな研究者からヒト胚に関する文献を紹介されて面食らったことをよく覚えています。
ヨハネ・バウロ2世が生命アカデミーという新しい機関を、1603年に創設された科学アカデミーとは別に新設したのは、将来、現在のような事態、生命科学技術の進展に伴って、着床前診断や代理母、遺伝子操作など、新たな問題が次々と生じてくることを見越して、それに手を打とうと考えたからでした。科学アカデミーだけではなぜ駄目かというと、ここには倫理の問題が入ってくるからです。ヨハネ・バウロ2世は生命アカデミーのほかに、社会科学アカデミーも新設し、社会科学の問題についてはまた別の組織で対処する体制を整えましたが、当初、ヴァチカンが取り組もうと思った一番の課題は、この受精卵の保護の問題でした。
97年にクローン羊ドリーが誕生すると、生命アカデミーは直ちに『クローンに関する考察』という文書を出して、この中で、クローン技術は「生み出されるクローンの尊厳に反する」ということを明確に指摘します。欧州議会がそれを追ってクローンの禁止決議を出します。
ところが翌年、クローン胚からES細胞を作成する研究目的のクローニング――当初、「治療目的のクローニング(セラピューティック・クローニング)」という言葉が使われましたが――、の研究計画が提示されます。クローン胚を作って、そこからES細胞を作ることができるということになりますと、生殖目的のクローンには反対するとしても、拒絶反応のない再生医療の進歩のために、ES細胞を作成するためのクローニングを合法化しようとする動きが生じます。欧州議会は1998年に、生殖目的のクローニングのみを禁止する追加議定書を出します。生命アカデミーのほうでは、2000年に「ES細胞の作成と科学的・治療的使用に関する宣言」を出して、これに対抗する態度を明確に表明します。この文書の大半は、生物学の専門的な議論を扱っています。ヒトの生命の始まり、受精のメカニズムに関する生物学の議論が徹底的に検証されています。ヨーロッパでは当時、分子生物学者、発生学者、ヒト遺伝学者がこの議論の主たる担い手でした。この議論を踏まえて、哲学者や倫理学者が後に参入します。
2003年に生命アカデミーは、もう1つ別の文章を出します。これは当時、国連でヒトクローニングの是非をめぐる議論が紛糾していたのを見て、国連の議論に影響力を及ぼそうと考えたのです。「国際的な議論におけるクローニングの禁止」。これは当時展開されていた議論をひとつひとつ取り上げて、批判検討を加えたものですが、これも科学、倫理、法律の3段階の構成になっていて、それぞれ別の章を設けて議論していくのです。まず生物学的な事実はこう、それをもとにして倫理を考えるとこう、さらにそれをもとにして法律を考えるとこうなる、ということを3つの段階に分けて議論していくのです。
2004年にヴァチカンの国務省――外務省に当たる機関です――が、対外向けに、国連の議論にいっそう影響力を及ぼす目的で、生命アカデミーの文書を踏まえて、もう少し短いコンパクトな文書「ヒトクローン個体産生禁止に関する国際協議に向けて」を作成します。功奏して、2005年に国連でクローン全面禁止宣言が出ますが、条約にはなりませんでした。このような国際的な動向の中で、イタリアでは国連宣言の前年に生殖補助医療に関する法律が成立しますが、これは先ほど申し上げたように、クローンを全面禁止し、ヒト胚を用いた実験もすべて禁止という厳格な立場を取っています。
2006年に生命アカデミーが「着床前の段階のヒト胚」というパンフレットを出します。これは一般の人向けの平明なもので、ヒト胚に関する科学的事実と法的保護の必要性について記した、広報活動というか、教育活動のためのものです。そして2008年に教理省、これは先ほど言ったヴァチカンの教えを司る、一番権威のある部署なのですが、そこが「人格の尊厳・生命倫理の幾つかの問題について」という文書を公表して、この中で体外受精、それから代理母の問題、生殖医療等の個別の問題についてコメントしています。
ですから、今後、カトリック教会の生命倫理の公式の見解として冒頭に掲げられるべきなのは、今、最後にご紹介した教理省の文書なのですが、これまで述べてきた基本構造は一つも変更されていません。科学と倫理、そして始まりのときから尊厳と人権を守ること、生命権だけではなく他の重要な人権も守ることです。
以後のスライドは、生物学、シエンツァのさらに詳しい説明を書いたものです。簡単にご覧いただければと思います。 これはギルバートの発生生物学の教科書に掲載されている写真です。権威のある生物学の教科書なのですが、この中で人の始まりは――わかりづらいかもしれませんが――上段左が受精前の卵子です。上段中央が人の始まりです。卵子の核が成長して前核を形成します。ここでは卵子のイオン構造が全部変化して、カルシウム波が受精卵全体を覆います。新たな人の個体の発生の時点です。私は見たことがありませんが、この瞬間は、顕微鏡を通して肉眼で見ると、一目でわかるのだそうです。卵子の状態が一遍に変わるのだそうです。卵子のイオン構造が一挙に変わるということは、そこで別の個体が発生するということなのだそうです。先ほどの小門先生のフランスのお話では、医師会が割合好意的だということでしたが、医師たちは普段こういうものを目にしていますので、人の始まりが受精のときだということを、多分自分の感覚として知っているのだろうと思います。
次のスライドは詳しく書いただけのものですので、後でご覧いただくことにして、問題は、科学的事実をめぐって議論が戦わされたということに先ほど触れましたが、その事情を少しご説明したいと思います。ヒトの始まりが受精時であることに異論を唱えたのは、マコーミック、彼はイエズス会の神父で、ジョージタウン大学ケネディ研究所の倫理神学教授です。彼は医学の専門家ではありませんでしたが、生物学者グロブシュタインと共同で、14日目までの胚はまだ胚以前の段階のpre-embryoであると主張する論文を執筆しました。
イギリスで世界で初めてヒト胚研究の道を開いたのはウォーノック委員会でしたが、その委員として一番発言力を持ったのはマクラーレンでした。マクラーレンはノーベル章も受賞している発生生物学者で、日本でES細胞の研究をしている中辻教授の先生でもあります。ウォーノック委員会は様々な専門家を集めた委員会で、生物学の知識にみんな乏しかったところで、マクラーレンがこのプレエンブリオという概念を持ち込んだのです。受精卵もエンブリオですから、「エンブリオの前」を表すプレエンブリオという語は、まだ新たな人ではないということを含意します。「受精後14日目までエンブリオは存在しない」ことを示す、そういう新しい「プレエンブリオ」概念を作って、ヒト胚を使った実験を推進したい人たちに研究推進の口実を与えました。
ノーマン・フォードもカトリックの生物学者ですが、14日目までの胚は一卵性双生児を生ずる可能性があるから、まだ人の個体ではないと主張しました。先ほどの、個人を重視する自己観の持ち主にとっては、個人かどうかは非常に重要です。フォードは、一卵性双生児を生ずる可能性のある受精卵はまだヒトの個体、すなわち個人とは言えないから、「まだ細胞の塊にすぎない」と主張しました。
フォードの見解は、日本でも大きな力を発揮したと思います。日本での議論も14日目まではまだエンブリオではないということを前提に、簡単にゴーサインが出たと思います。要するにヒトの生物学的な始まりがいつか、この点が決定的なポイントなのです。人間の尊厳や人権を守るべきということについては、おそらくみんなの合意が得られると思いますが、受精卵に人という身分を与えなければ、簡単に実験材料にすることができるわけです。ヒト胚研究の是非について、科学の議論が一番大事だったのはこのためです。受精後14日目までは、まだ人が発生していないというのは科学的な誤謬(ごびゅう)です。プレエンブリオという言葉も、今日ではすでに発生学では用いられていません。一卵性双生児のメカニズムはまだ実証されておらず、フォードの見解も一つの仮説にすぎません。生命アカデミーの見解では、受精時にすでに個体が確立している。しかし初期の胚は可塑性に富んでいるので、なんらかのアクシデントで2つに分かれたとき、もう1つの個体が発生する可能性がある、ということです。シャム双生児のように、14日目以降でも一卵性双生児が発生する例もあります。
以下のスライドは、もう一つのコシエンツァについての説明です。これは国際法と生命倫理原則の確認です。世界人権宣言には、人間である限り、誰でも例外なく人間の尊厳と基本的人権を認められるべきである、との原則が記されています。人間の尊厳原則の起源は、世界人権宣言の半世紀前、1890年に発されたローマ教皇レオ13世の回勅『レールム・ノヴァルム-資本家階級と労働者階級の権利と義務』でした。19世紀最大の社会的不正義は、労働者の問題でした。労働の搾取の問題です。労働は人間の営みの1つであり、人間の生活と切り離せないものです。ですから、経済効率だけを追求してはならないので、人間らしい働き方というものがあるはずなのです。今日では労働基本法が整備されていますが、当時、労働者の権利は保障されておらず、経済発展のために大規模な労働の搾取が行われていました。その不正を糾弾したのが『レルーム・ノヴァルム』でした。
先ほど社会科学アカデミーの話をしましたが、今日のカトリック教会の社会正義についての基本文書が、この『レルーム・ノヴァルム』です。「人間は経済発展の手段ではない」。今日の生命倫理問題もこの応用編です。「人間は科学の発展のための手段ではない」。両者はまったく同じ構図です。「人間の尊厳」原則は、戦後、国際的な医学研究倫理の最高原則にもなっています。世界人権宣言自体、ナチスの医師たちの人体実験に対する反省から生まれたものなのですが、世界医師会もヘルシンキ宣言を出して――これはヒポクラテスの「医の倫理」の現代化と言うことができると思います――、医学を発展させなければならないけれども、被験者の利益を優先しなければならないことを明確にしています。
最近の国際的な医学研究倫理の一つとして、96年の生命倫理条約を挙げることができます。生命倫理条約というと、一体どのような内容のものかわかりませんが、正式なタイトルは「生物学と医学の適用に関する人権および人間の尊厳の保護のための条約・人権と生物医学条約」というのです。「人権と人間の尊厳の保護のための条約」であることが明確にされています。
次のスライドのクローニングの国際規制については先ほど触れましたが、ここでは生殖目的のクローニングがどのように人間の尊厳に反するかを、少しご説明致します。これはハンス・ヨナスというユダヤ人哲学者の言葉です。「ヒトクローニングは、方法においてこの上なく専断的であり、目的においてこの上なく奴隷的な遺伝子操作の形態である」。ヴァチカンの文書もこれを引用しています。別の言葉で言うと、ヒトクローニングは「優生計画である」。優生計画という言葉もヨナスの表現ですが、ここで問題にされているのは、クローン技術によって作成されるクローン人間の尊厳と権利です。どのような権利が侵害されるかというと、異性の両親から生まれる権利、それから家族や親族を持つ権利です。生きる権利だけではなくて、どのようにして生まれてくるか、生まれ方に関わる権利です。人は誰でも自然の生殖においては、お父さんとお母さんから生まれてきます。家族や親族を持つ権利は、水平方向と垂直方向、両方の方向の家族・親族関係を持つ権利です。クローン羊ドリーの母親は、年の離れた双子の姉です。父親はありませんが、父方と母方の祖父母が遺伝学上の父母に当たります。ドリーは垂直方向の子孫との関係も、水平方向の親族関係も複雑な環境で人格形成をしなければなりません。
それから、クローン胚の自己決定権も問題にされています。卵子がどうやって受精するのか、どの遺伝子をどのようにプログラミングするのかは、誰かが決めるのではありません。第三者が恣意(しい)的に決める、あるいは操作するのではなくて、その卵子自体が選び取っていきます。偶然に定まるというよりは、卵子とその精子の出会いによって、いろいろなことが決まっていく。人はみんなそのように、誰かに決定されたり干渉されたりしないで生まれてくる権利があるのに、クローン技術で生まれてくる人間は、最初から操作されて、遺伝子を決定されて生まれてくる。これは「優生計画」である。そして、これとほぼ同じ論理で、着床前診断も非難されることになるのです。
クローニングの禁止をめぐる国連での議論の際、アメリカはクローンに反対する側に回ったのですけれども、実は、反対の理由をまったく見出すことができませんでした。同じく日本の刑事法学者の間でも、クローン禁止の根拠について多くのものが書かれましたが、どれも歯切れが悪いのです。個人主義の立場をとる限り、クローン禁止の根拠を見出すのは無理です。個人の自己決定権を認め、受精卵の人権や尊厳を認めないのであれば、子どもを持つ権利、リプロダクティブ・ライツを主張する側が勝つに決まっていますので、クローニング禁止の根拠は出てきません。しかし、生命の開始時から人権や尊厳を認めれば、クローン禁止の根拠は全部きれいに説明できるわけです。アメリカが全面禁止に賛成したのは、結局、当時のブッシュ政権が保守的な立場を採用していたためでした。フランスは戦勝国でもあり、優生思想に対して割合寛容なためか、反対に回りましたが、ドイツとイタリアは優生思想に対する反省――敗戦国ですので――が効いていて、人間の尊厳原則にも非常に敏感であるという事情などもあるのではないかと思います。
人間の尊厳原則に対する異論は、人の倫理的地位、すなわち人格概念をめぐって展開されます。これは哲学の分野では大変な論争になっているところです。人格とは何か――この議論にはもうあまり立ち入りたくないのですが――今度は生物学の議論から離れたところで、生物学ではそうかもしれないけれども、「人格とは何か」という問題は必ずしも生物学のみに縛られないのではないか、独自の人格概念があってもいいのではないかが議論されます。しかしそのようなことを誰かが言い出しますと、それはもう100人いたら100とおりの人格概念が生まれても不思議ではないわけです。
代表的な見解は、自意識を重視する立場です。「人格とは理性的な、自意識のある存在だから、自意識または人格性を示す他の外面的な行為、態度、能力を持たない人は人格ではない。したがって尊厳と人権も持たない」と主張します。3歳児、植物状態の人は人格とは認められないので、生きる権利もない。したがって自由に殺してもかまわない、少なくとも生命権の侵害はないことになります。この論理でいくと、ヒト胚ももちろん人格とは認められません。では、3歳まで人格ではないのか。そう主張する見解もありますが、多くは、14日目までの初期胚は、少なくとも知覚能力をつかさどる神経細胞の元である原始線条がまだ発生していないから、当然人格ではない、と主張します。しかしこうなってくると、人格の開始時点については、本当にいくらでも線が引けるので、いろいろなバリエーションが考えられることになると思います。反論するほうも大変です。
しかし、この考え方の一番の問題点はどこかと言うと、この論理は、奴隷制を肯定するための論理と同じであるところです。ヴルテニウスという法律家(1565年~1632年)は、奴隷制を肯定するために、初めて法律の領域にこの人格概念を持ち込みました。そして人格性をそなえた者の尊厳だけを認めようとしました。人格でない人間は、物扱いしてもよいことになります。これは、奴隷制を許す論理なのですが、同じように、14日目までのヒト胚を物扱いすることを許す論理が、今、復活していると言うことができます。
これに対する反論として、レジメにはグアルディーニの見解を挙げました。「本来の人格概念は、自己支配、人格的責任、真理と道徳秩序のうちに生きる能力を意味する。それは、年齢、身体、心理状態、自然的素質によるものではなく、存在に関わるもの(existential)であり、精神と身体の統合体である人間の本質を構成する精神的霊魂(spiritual soul)によるものである」。大事なのは「存在」であって、人間の尊さは「精神と身体の統合体である人間の本質を構成する精神的霊魂」だとされています。すなわち、人間は物質、DNAだけで構成されているわけではない。物質と、物質でないもの、すなわち身体と精神との両方から構成されている。そして人間の本質は精神の部分にある。しかし両者は不可分に結びついて切り離すことができません。肉体があるところに即ち精神がある。この考え方は、ときどき誤解されるように、精神だけを大事にして肉体を軽視するものではありません。
これはシスティーナ礼拝堂の天井に描かれているミケランジェロの「アダムの創造」です。アダムは立派な肉体をしていますが、力がありません。まだ精神が宿っていないからです。今、右側にいる父なる神――キリスト教の「三位一体」の神である、「父」と「子」と「聖霊」の「三位」のうちの「父」――が、アダムに精神を吹き込んでいるところです。それによって命あるもの、生きるものにしたのです。アダムは神が創造した最初の人間で、これが「クリエイション(創造)」です。神はその後、人間の創造を人間の男女に委ねたので、人間は現在、生殖によって新しい命を創造しています。それで、人間の生殖をプロクリエイションと言います。
このフレスコ画では、肉体が先にあって、後から精神を吹き込んでいますから、ここには少しインターバルがあります。トマス・アクィナスは今日のカトリック神学の基礎を築いた16世紀の神学者ですが、彼が唱えた「遅延入魂説」をめぐって、――我々には信じがたいことですが――神学者や哲学者の間では、今日かなりさかんな議論が見られます。しかし、トマスが遅延入魂説を唱えた当時、まだ卵子は発見されておらず、ヒトの生殖のメカニズムは、精子が女性の子宮に入ると、子宮内の血液が凝固してヒトのもとになると考えられていました。つまり、精子が女性の胎内に入って血液が凝固するまで、新しいヒトの発生まで、数日間のインターバルがあると考えられていたのです。遅延入魂説は、このような誤った生物学を前提にして唱えられものだったので、1827年に卵子が発見され、受精の生物学的メカニズムが解明されると、ほとんどの神学者によって放棄されました。ところが、遅延入魂説は後世の倫理学者によって再び取り上げられます――中絶合法化を根拠づけるため、そして今また初期胚の実験利用を合法化するために。
これは、ヒト胚をテーマに2006年に開催された生命アカデミーの国際会議のプログラムの表紙に使われた14世紀の絵です。右側の赤い服を着ているのがマリアです。マリアのおなかの中にはイエスがいます。そして左側にいる女性、エリサベトのおなかの中には洗者ヨハネという預言者がいて、2人が出会ったとき、おなかの中の子が喜び躍った、と聖書には記されています。
この絵を生命アカデミーが使ったのは、生まれる前の子どももコミュニケーションしていること、人と人とのかかわりをしていることを示したかったからだと思います。そして、次のような人格概念を提示します。「個人」だけが孤立してあるのではなくて、人と人とのかかわりが人格にとって不可欠な要素である。その人格的なかかわりは、自意識のレベルに限られません。ヨハネと洗者ヨハネは、母胎内にあって自意識はなかったかもしれないけれども、何かを察知してコミュニケーションしていた。それは、精神的なコミュニケーションなのですが、それを示したかったのだと思います。
生命アカデミーの文書は、この絵について直接解説しているわけではありませんが、先ほど水野先生がおっしゃっていた「胎児と母のコミュニケーション」が生化学のレベルで行われていることを、子細に証明しています。受精卵、胚が子宮に着床する時期はごく短期間に限られていて、子宮はこの期間を過ぎれば胚を受け入れません。この着床期の子宮の受精卵に対する許容状態は窓にたとえられて「着床ウィンドウ」と呼ばれています。このウィンドウが開くのに合わせて、胚も着床できる状態に変化するのだそうです。このように、母と子の間では、生化学レベルで非常に猛烈な対話が交わされています。したがって、着床は、母親が一方的に決めるのではなくて、子どもと子宮との間のクロストークなのです。双方の条件が整わなければ着床は起こらないことが、生物学的に明らかにされています。ヴァチカンは胚が母との間でこのような生化学的なコミュニケーション、物理的な対話が交わされることを証明して、胚が人格であることを示そうとしているのです。
時間がなくなってしまいましたが、最後に生殖補助医療についてお話させていただきます。これも、シエンツァとコンシエンツァの両面から考察する必要があります。
まず、シエンツァ、科学面。技術的な問題のほうでは、生殖補助医療技術はまだ研究段階にあることが明らかにされます。もしそうだとすると、ヒポクラテスの誓いに書かれているように、「害するな」が優先します。科学を発展させることはよいことですが、しかし害してはならないのです。まだ実験段階にあるということは、母親も胎児も、この技術によって害する可能性があるということです。
母親に対する害としては、まず第一に、妊娠率が非常に低いことが挙げられています。95%の成功率を得ようと思ったら、平均15回の施術を繰り返さなければならない。それは母親に強度のストレスを与え、多くの者がうつ状態に陥ります。不成功に終わる女性の8割が深刻な損害を被るのだそうです。
先ほど、大した問題ではないように言われていましたが、過剰排卵症候群というのは、死亡する場合もある、極めて危険な状態です。排卵誘発剤を使って一度に多くの卵子をつくり、それを体外に取り出すことは、後にホルモンのバランスが狂うなどして、かなり大きな負担になるようです。また、着床前診断を経た場合、妊娠率は非常に低くなります。着床前診断によって選別された胚の出生率は3%未満です。普通の生殖補助医療技術の場合は20%程度ですから、妊娠率は極めて低い。これもまだまったくの実験段階ということができます。
顕微授精は、人間の体軸を恣意的に決定します。精子が卵子に入り込む位置が、背骨の位置になります。それを、適当な場所に注射針を刺して精子を注入しても大丈夫なのか。恣意的に体軸の位置を決めてしまってもいいのか、このような人為的な操作は許されるのか。
他方、生まれてくる子どもに対しても深刻な損害を及ぼします。自然流産、早産、低出生体重児、――この低出生体重児というのは、要するに成長が不全だということですので、重い病気になりやすいなど、将来子どもにさまざまな負担を与えることになります。それから凍結。凍結されることで、受精卵は何らかの損傷を被る可能性があります。さらに、健全な人格形成の困難。先ほど言った親戚関係の複雑化などです。ヴァチカンは生殖に対する医療技術の介入はすべて否定されるべきだと言っているのではなくて、科学はもっと別の方法を探求すべきだと言いたいのです。科学というのはそんなに弱いものではない。倫理の限界に行き当たっても、別の道が開けるはずなのです。ですから、現在の生殖補助医療技術を無理に押し進めるのではなくて、倫理を曲げないで解決する方法はないのか。
今、ゲノム・プロジェクトの成果によってかなりの不妊の原因が特定できているのだそうです。これは、親のほうの遺伝子治療を可能とするものです。そしてこれこそが不妊の根本的な解決につながる本筋なので、こちらを一生懸命にやりなさいと、専門の研究者に働きかけるようなことをしています。
次にコシエンツァ、倫理面。「生殖の尊厳」を唱えます。英語ではdignity of procreation で、先ほど触れたとおり、reproductionではありません。物質レベルでは動物と同じreproduceかもしれませんが、生殖の結果もたらされる人間はreproduction(複製品)ではありません。人間は精神的な別の次元を帯びているので、procreationという別の言葉を使います。
カトリック倫理は、愛と生殖の一致を説きます。身体の一致と精神の一致は同時に存在すべきである。愛の実りが新しい命の創造でなければならない。産児が科学技術の成果やリプロダクションであってはならないのです。それは、物質面だけを推し進めるものであって、優生学と同じだ、と言うのです。ですから、労働の精神性、労働の尊厳を労働問題に持ち込んだのと同じように、生殖の精神性をどう考えるか、生殖補助医療にどのように盛り込むのか。この「プロクリエイションの尊厳」の考え方によっては、各論レベルではカトリックほど保守的でない別の答えがあるのかもしませんが、原理的にはこういう考え方が取られています。大事なのは、生殖の精神的な次元を重視すると、どうなるかということです。ここに何を盛り込むかは、それぞれの宗教や文化的事情によって多少変わってくるのだろうと思います。
イタリアの生殖補助医療法は、基本的にはカトリックの考えをほぼフォローしたものになっています。男女の愛と生命の創造の一致ということは書かれておりませんが、その考え方が背景にあります。
法施行後の実施状況なのですが、昨年4月に施行5年後の報告書が出ました。3年後の報告書も出されましたが、最も注目されるのは、受精卵が何人救われたかという、その詳細なデータが示されていることです。報告書は、もし法律が施行されていなければ凍結されていたであろう受精卵の数を各医療機関ごとに割り出して、5年間で大体12万人救ったということを記しています。そして、凍結される胚の数を減らしても、妊娠率に差はなかったのだそうです。ですから、技術の効率に変わりはない。2009年のレポートの課題は、母親の負担の軽減が数字に表れていないことです。先ほど言った過剰排卵症候群など、母親の負担はこの法律では解消できないから、今後これからどうするかということを考えるべきだ、そういう方向が示されています。
すみません、大急ぎでしたが、以上で終らせていただきます。
質疑応答へ続く